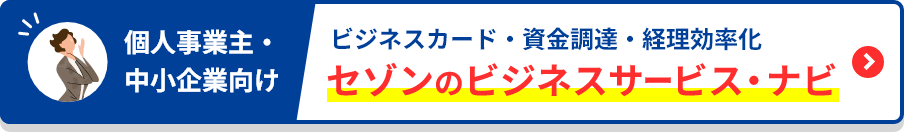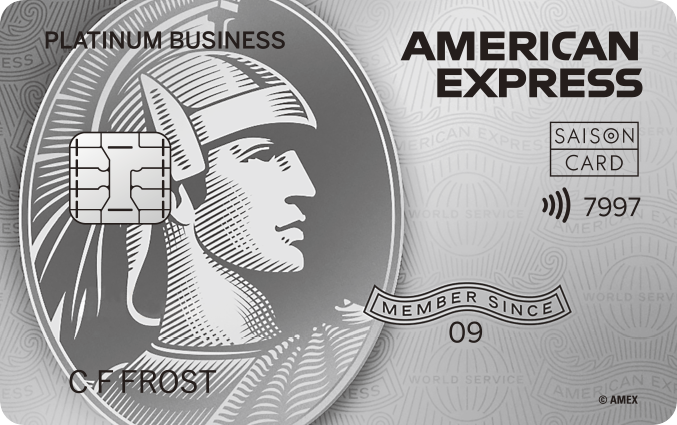債務超過の解消方法6選!赤字との違いや健全な経営を支援するサービス紹介
本記事では、債務超過から抜け出すための具体的な方法と、実際に再建を果たした企業の事例をもとに、解決への道筋をわかりやすく解説していきます。経営再建に向けた第一歩として、まずは現状を正確に把握することからはじめましょう。
business_support_loan02.png)
business_support_loan02_sp.png)
債務超過の基礎知識
債務超過は、さまざまな要因が複合的に絡み合って発生します。ここでは、債務超過の基本的な情報について解説します。
そもそも債務超過とは?
債務超過は、企業の財務状態を示す重要な指標の一つで、企業が抱える負債(債務)の総額が保有する資産の総額を上回る状態を指します。言い換えれば、企業の純資産(資産総額から負債総額を引いた金額)がマイナスになっている状況です。
この状態を具体的に確認するには、貸借対照表(バランスシート)を見ることが最も確実です。貸借対照表の資産の部の合計額から、負債の部の合計額を差し引いた金額が純資産であり、この数値がマイナスであれば債務超過である判断できます。例えば、資産総額が1億円で負債総額が1億2千万円の場合、純資産は-2千万円となり、債務超過の状態に陥っていると考えましょう。
債務超過の状態は、企業の存続に関わる深刻な問題として認識されています。この状態では企業の返済能力に疑義が生じ、取引先からの信用低下や金融機関からの新規融資の停止につながる可能性が高いためです。また、会社法上では、債務超過が2期連続で継続した場合、上場廃止となる可能性が出てきます。
ただし、決算書上で債務超過が確認された場合でも、含み資産(時価が簿価を上回る資産)の存在や、将来の収益改善の見込みなども考慮しないと、本当の深刻さは正確にわかりません。そのため、正確な財務状態の把握には、公認会計士や税理士などの専門家による詳細な分析を受けるのをお勧めします。
債務超過・赤字・資金ショートの違い
企業経営において、債務超過・赤字・資金ショートは、それぞれ異なる財務上の問題を示す概念です。これらは時として関連性を持つものの、本質的には異なる状態を言います。
債務超過は、企業の財務状態(ストック)を示すもので、負債総額が資産総額を上回る状態を指します。これは貸借対照表上で確認できる状態です。一方、赤字は企業の経営成績(フロー)を示すもので、一定期間の収益が費用を下回る状態を指します。損益計算書上では当期純損失として表示されます。つまり、債務超過の企業であっても、その期の営業活動で利益を上げることは可能であり、逆に赤字企業であっても十分な資産を持っていれば債務超過には陥らない場合もあるのです。
資金ショートは、これらとはまた異なり、日々の事業活動に必要な現金の支払いに支障をきたす状態を指します。例えば、売上は好調かつ黒字であっても、取引先からの入金が遅れることで一時的な資金不足に陥るケースなどです。キャッシュフロー計算書で把握できるこの状態は、債務超過でなく黒字企業であっても発生する可能性があります。
したがって、これら三つの状態は必ずしも同時に発生するわけではなく、それぞれに適した対策が必要となります。健全な企業経営のためには、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の三つの財務諸表を総合的に分析し、各状況に応じた適切な対策を講じることが重要です。
債務超過になると倒産してしまう?
債務超過は企業経営において深刻な状況ではありますが、即座に倒産に直結するわけではありません。ただし、債務超過の状態が継続すると、取引先や金融機関からの信用低下を招き、新規の取引や融資が困難になるなど、事業継続に支障をきたすリスクが高まることは事実です。
しかし、多くの企業が債務超過から再建を果たしている事例があるように、適切な対策を講じれば経営を立て直せる見込みは十分にあります。例えば、不採算事業の見直しや経費削減による収益力の改善、遊休資産の売却、取引先との支払条件の見直し交渉など、様々な手段を組み合わせれば、徐々に債務を返済し、健全な財務体質を取り戻す のは決して不可能ではありません。
特に重要なのは、債務超過の状態に早期に気付き、速やかに対策を講じることです。経営状態の悪化を隠すことなく、取引先や金融機関に対して誠実に現状を説明し、再建計画を示すことで、支援を得られる可能性も高まります。実際に、メインバンクの支援を受けながら経営改善に取り組み、債務超過を解消した企業も少なくありません。
つまり、債務超過は確かに経営危機のサインですが、それは同時に経営改善の必要性を示すシグナルでもあります。適切な対応と関係者の理解・協力があれば、企業を再生させ、より強固な経営基盤を築くチャンスともなり得るのです。
債務超過が起きる3つの原因

債務超過が起きる原因は様々ですが、主なものとして以下のようなものが挙げられます。
原因①赤字が続いている、創業赤字が発生している
債務超過の主要な原因の一つとして、継続的な赤字経営が挙げられます。企業が赤字を続けると、その損失を補うために借入金や買掛金などの負債が徐々に増加していき、最終的に資産を上回る状態、つまり債務超過に陥るのも時間の問題です。特に、売上が計画を下回る一方で固定費が高止まりしている場合、赤字額が急速に膨らむリスクがあります。
創業期における赤字は特に注意が必要です。新規事業を立ち上げる際は、設備投資や人材採用、広告宣伝費など、多額の初期投資が必要となる一方で、十分な売上が得られるようになるのはその後になるのが一般的です。そのため、創業1年目は赤字になることが多く、これは「創業赤字」と呼ばれます。しかし、この創業赤字が2年目以降も続くと、事業の存続自体が危ぶまれる事態となりかねません。
したがって、創業時には十分な資本金や運転資金を確保するとともに、2年目以降の黒字化を実現するための具体的な経営計画が不可欠です。例えば、売上目標の達成に向けた営業施策の実行、固定費の適正化、業務効率化による経費削減など、収益構造を改善するための取り組みを計画的に進める必要があります。
このように、赤字経営は債務超過への重大なリスク要因となりますが、早期に収益改善策を講じることで、健全な経営基盤を築くことが可能です。特に創業期においては、資金繰りと収益性の両面から慎重な経営判断が求められます。
原因②資本金が少ない
債務超過の原因には、会社設立時の資本金が少額であることも挙げられます。2006年の会社法改正により、株式会社の資本金の最低額規制が撤廃され、1円からでも会社を設立できるようになりました。この規制緩和は起業のハードルを下げ、新規ビジネスの創出を促進する効果がある一方で、財務基盤が脆弱な企業の増加をもたらす結果となっています。
少額の資本金で創業した企業は、事業開始時点から自己資本が乏しい状態にあるため、予期せぬ損失や事業環境の変化に対する耐性が低くなるものです。例えば、開業後の運転資金を借入金で賄う必要が生じやすく、売上が計画通りに伸びない場合や、予想以上の費用が発生した場合に、すぐに債務超過に陥るリスクが高まります。
特に創業初期は、商品開発や設備投資、人材採用など、多額の資金需要が発生する時期でもあります。この時期に十分な自己資本がないと、借入金への依存度が高まり、金利負担も重くのしかかります。その結果、わずかな業績の悪化でも財務バランスが崩れやすい状況に置かれることになるのです。
「このため、創業時には事業計画に基づいて必要な資本金を慎重に見積もり、可能な限り十分な自己資本を確保することが、将来の債務超過リスクを軽減する上で重要となります。また、事業の成長に応じて増資を検討するなど、継続的な財務基盤の強化も必要です。
なお、令和3年経済センサス‐活動調査の速報集計によると、全国の会社における資本金の分布では、「300万円~500万円未満」が32.6%(約57.9万社)と最も多く、次いで「1,000万円~3,000万円未満」が31.3%(約55.6万社)、「500万円~1,000万円未満」が14.2%(約25.3万社)となっています。
業種や事業内容によって必要な資本金は異なりますが、一つの目安として、300万円~500万円程度の資本金を用意できると望ましいといえるでしょう。特に製造業など設備投資や仕入れに多額の経費がかかる業種では、より多くの資本金を検討する必要があります。
原因③多額の投資をして回収ができていない
債務超過の原因として、多額の投資による資金回収の失敗も考えられます。企業が成長や競争力強化を目指して行う設備投資や新規事業への参入は、経営戦略として重要な選択ですが、時として深刻な財務問題を引き起こすことがあります。
典型的なケースとして挙げられるのは、製造業における最新設備の導入や、小売業の新規出店、IT企業の新規システム開発などです。これらの投資は、多くの場合、金融機関からの借入れや社債発行などの負債によって資金を調達します。投資時点では、将来の売上増加や業務効率化による収益改善を見込んでいても、市場環境の変化や競合との競争激化、技術革新のスピードなど、様々な要因により当初の想定通りの成果が得られないことがあります。
特に問題となるのが、投資の回収期間が想定以上に長期化するケースです。例えば、新規事業が軌道に乗るまでに予想以上の時間がかかり、その間の運転資金や既存の返済負担が重くのしかかる状況です。さらに、一度投資した設備や システムは、簿価での売却が困難なことも多く、投資額の回収が著しく困難になることもあります。
このような事態を防ぐためには、投資判断時点での慎重な市場分析と収支計画の策定、そして投資実行後の継続的なモニタリングと柔軟な軌道修正が不可欠です。また、全ての投資を借入金に依存せず、自己資本とのバランスを考慮した資金調達計画を立てることも重要になります。
business_support_loan02.png)
business_support_loan02_sp.png)
債務超過になることで考えられるリスク
債務超過は、企業にとって深刻な状況であり、様々なリスクを伴います。以下に、債務超過がもたらす主なリスクを具体的に解説するので参考にしてください。
金融機関からの融資が困難になる
債務超過に陥った企業が直面する最も深刻なリスクの一つが、金融機関からの資金調達が著しく困難になることです。債務超過にある状態は、企業の返済能力に対する重大な懸念材料となるため、新規融資の審査において厳しい評価を受ける原因になります。
既存の取引金融機関との関係においても、様々な影響が生じます。例えば、融資条件の見直しを求められ、金利の引き上げや追加担保の要求、返済期間の短縮などが行われる可能性があります。最悪の場合、既存融資の期限の利益を喪失し、一括返済を求められるケースも考えられるため、注意が必要です。
しかし、債務超過企業であっても、実現性の高い再生事業計画を提示することで、金融機関からの支援を得られるかもしれません。この再生計画では、通常3年から5年程度での債務超過解消を目標とすることが望ましいとされています。計画には、具体的な収益改善施策、コスト削減策、資産売却計画などを盛り込み、どのように債務超過を解消していくのかを明確に示さなくてはいけません。
特に重要なのは、月次での詳細な資金計画を立て、確実な返済原資の確保を示すことです。また、計画の実現性を高めるため、税理士や中小企業診断士など外部専門家の支援を受けながら策定するのも重要になります。こうした真摯な取り組みにより、金融機関の理解を得られれば、既存融資の条件維持や、場合によっては新規融資の実行も期待できるでしょう。
取引先からの信用度が低くなる
債務超過に陥った企業が直面する最も深刻な問題の一つが、取引先からの信用低下です。この信用低下は、単なる評判の問題ではなく、企業活動の様々な面に具体的な影響を及ぼし、事業継続を困難にする要因となりかねません。
特に重要な影響として、取引条件の悪化が挙げられます。これまで認められていた掛け取引が現金取引に変更されたり、支払いサイトが短縮されたりすることで、運転資金の確保が一層困難になります。また、仕入先が取引量を制限したり、新規発注を控えたりすることで、必要な材料や商品の確保が難しくなる可能性もあります。
さらに、この信用低下は連鎖的に事業機会の損失に繋がりかねません。新規の取引先開拓が困難になるだけでなく、既存顧客との取引も縮小される恐れがあります。特に、大口顧客や長期プロジェクトを請け負う場合、取引先が契約の継続や新規発注を躊躇するケースが多いです。これは将来の売上減少に直結し、財務状況の更なる悪化を招く悪循環を生み出す可能性があります。
このように、取引先からの信用低下は、即座に企業活動に影響を及ぼし、それが更なる業績悪化を招くという負のスパイラルを引き起こす危険性が高いです。そのため、債務超過に陥った際は、取引先との丁寧なコミュニケーションを通じて信頼関係の維持に努めるとともに、具体的な再建計画を示すことで理解と協力を得ることが極めて重要となります。
経営者が負債を返済する可能性も
債務超過に陥った企業の経営者が直面する最も深刻なリスクの一つが、個人資産による債務の返済義務です。これは、多くの中小企業において、金融機関からの融資を受ける際に経営者が連帯保証人となること(経営者保証)が一般的な慣行となっているためです。
連帯保証人として署名した経営者は、会社が債務を返済できない場合、個人の資産を使って返済しなければならない立場に置かれます。これは、会社の負債が経営者個人の負債となることを意味し、最悪の場合、経営者の自宅や預貯金などの個人資産が差し押さえられるリスクも発生します。さらに、このような状況では経営者の個人信用も大きく損なわれ、将来的な事業再建や新規事業立ち上げの際の障壁となる可能性があります。
特に深刻なのは、この返済義務が経営者の退任後も継続する可能性があることです。たとえ会社を離れたとしても、連帯保証人としての責任は残り続けることがあります。このため、債務超過に陥った企業の経営者は、会社の債務処理と同時に、個人の資産防衛についても真剣に検討する必要に迫られます。
このようなリスクを考慮すると、債務超過の兆候が見られた段階で、早期に専門家への相談や金融機関との交渉を行い、経営改善計画を立案することが極めて重要です。近年では、経営者保証に依存しない融資の促進も進められていますが、既存の保証契約がある場合は、慎重な対応が必要となります。
債務超過の解消方法6選【短期的手段~最終手段】

債務超過は企業にとって深刻な状況ですが、適切な対策を講じることで解消できる可能性があります。
解消方法は目的や企業の状況によって異なりますが、一般的に短期的な手段から最終的な手段まで以下のような選択肢が考えられるので、詳しく解説しましょう。
【短期的解消法】保有資産を売却する
債務超過を解消するための短期的な方法として、保有資産の売却は効果的な手段です。具体的には、購入したものの、何らかの理由で使われていない、事業活動に直接関係のない資産(遊休資産)を現金化することで、即座に債務返済の原資を確保することができます。
また、保有している投資有価証券や株式を市場で売却することで、比較的短期間で資金を調達することが可能です。不動産については、本社ビルや工場、倉庫などの事業用資産であっても、規模の適正化や賃貸物件への移行を検討しながら売却することで、多額の資金を確保できる可能性があります。ただし、これらの資産売却は一時的な対応策であり、本質的な経営改善と組み合わせて実施することが重要です。
【短期的解消法】債権者に債務免除を依頼する
債務超過を解消する短期的な方法として、債権者への債務免除の依頼が挙げられます。債務免除とは、債権者が債務者に対して借金の返済を免除することであり、あくまで法的な手続きではなく、債権者の任意の判断により行われるものです。
債務免除を受けるためには、まず現在の財務状況や経営状態、そして今後の事業計画を詳細に説明した上で、債務免除を受け、事業の継続や再建が可能となることを債権者に理解してもらう必要があります。特に、メインバンクなど主要な債権者に対しては、具体的な経営改善計画を提示するのが重要です。
ただし、債務免除は債権者にとっては債権を放棄することを意味するため、容易には認められない可能性が高いことを認識しておかなければいけません。また債務免除を受けた場合、債務免除益として課税対象となる場合もあるため、税務上の影響についても事前に検討しておきましょう。
【短期的解消法】債務を株式に転換する
債務超過を短期的に解消する方法として、DES(Debt Equity Swap:デット・エクイティ・スワップ)も有効な手段として挙げられます。これは債務を株式に転換する手法で、債権者が保有する債権を株式に振り替えることで実現します。
DESによって債務超過が解消される仕組みは以下の通りです。債務が株式に転換されると、貸借対照表上で負債として計上されていた金額が資本に振り替えられます。例えば、1億円の債務をDESで株式転換した場合、負債が1億円減少し、同時に資本が1億円増加します。この結果、純資産がプラスとなり、債務超過状態が解消されることになるのです。以下の図も参考にしてください。
なお、債権者にとってもDESには企業価値の向上による株式価値の上昇が期待できるというメリットがあり、企業再建の有効な手段として活用されています。
【短期的解消法】増資する
債務超過を短期的に解消する有効な手段として、増資による対応が挙げられます。具体的には、社長や役員からの借入金を資本金に振り替える方法です。これにより負債が減少し、同時に資本金が増加するため、債務超過の状態を改善することができます。
また、投資ファンドや外部の投資家から新たな出資を募ることも有効です。この場合、企業の将来性や事業計画の実現可能性を丁寧に説明し、投資家の理解と信頼を得ることが重要になります。投資家からの出資を受けることで、直接的に純資産がプラスとなり、債務超過が解消されます。
ただし、これらの方法を実行する際は、企業の経営状態や将来の成長戦略についても十分に検討しなくてはいけません。単に一時的な財務改善だけでなく、持続可能な経営体制の構築を目指すことが重要です。
【長期的解消法】利益を出す
債務超過を解消する長期的な方法としては、まず本業での収益力を強化し、安定的な利益を創出することが基本です。具体的には、営業力を強化して既存顧客との取引拡大や新規顧客の開拓を進め、売上高の増加を図ります。同時に、原材料費の見直しや業務効率化による人件費の適正化、在庫管理の徹底などを通じてコストを削減し、利益率の改善を目指すのが望ましいでしょう。
これらの施策を効果的に実行するためには、現状の経営課題を正確に分析した上で、具体的な数値目標を含む経営改善計画を策定することが重要です。計画では、月次や四半期ごとの進捗管理指標を設定し、PDCAサイクルを回しながら継続的な改善を進めることで、着実に債務超過を解消していきます。
また、必要に応じて事業ポートフォリオの見直しや不採算事業からの撤退なども検討し、企業全体として持続可能な黒字体質の確立を目指すのが望ましいため、税理士や中小企業診断士などの専門家にもアドバイスを求めるのをお勧めいたします。
【最終手段】民事再生法・会社更生法を活用する
債務超過を解消する最終手段として、民事再生法・会社更生法上の法的整理手続きを活用することも視野に入れましょう。民事再生法は、中小企業向けの再建型倒産処理で、経営者が引き続き会社運営に関与できる点が特徴です。債権者との合意のもと、債務の一部を免除や分割返済にすることで、事業の継続を図ります。
一方、会社更生法は主に大企業向けの手続きで、裁判所が選任した管財人が経営権を持ち、抜本的な事業再建を行います。現経営陣は退任を求められ、株主の権利も大幅に制限されるのが民事再生法との大きな違いです。債権者の同意を得て債務を整理し、更生計画に基づいて事業の再建を進めます。
いずれの手続きも、取引先や金融機関との信用関係が大きく損なわれ、事業継続に影響が出る可能性が高いため、他の再建手段を尽くしてからの選択となるでしょう。特に上場企業の場合、上場廃止になることも考慮しなければなりません。慎重な判断が必要になるため、弁護士のアドバイスのもと進めていくのが現実的な流れになります。
健全な経営をサポートする新たな資金繰り改善策「支払い.com」

健全な企業経営には適切な資金繰り管理が不可欠であり、その改善策としておすすめなのが「支払い.com」です。クレディセゾンが提供する中小企業向けの支払い管理ソリューションで、通常の銀行振込による支払いをクレジットカード決済に切り替えることができます。これにより支払期限を最長60日延長でき、一時的な資金不足を解消することが可能です。
また、「支払い.com」を使う際は、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードと組み合わせるとより効果的です。このカードは、高額な支払いにも対応できる決済枠を備え、さらに請求書支払いに特化した機能を持っています。オンラインでの簡単な登録で即時利用が可能で、書類提出や面倒な審査も不要です。手数料は一律4%と明確な上に、最短1営業日での振込にも対応しており、急な支払いにも柔軟に対応できます。資金繰り改善を検討する企業にとって、効率的な選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。