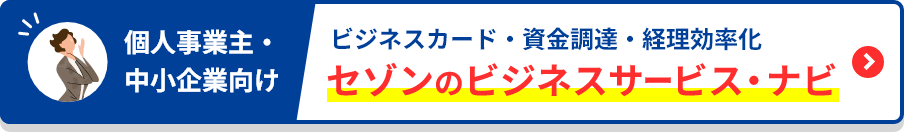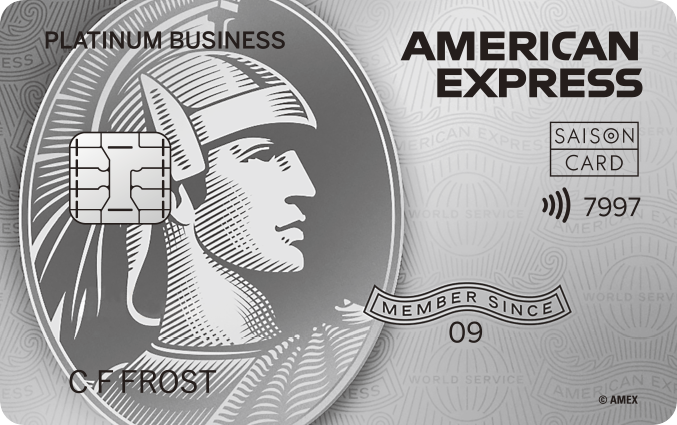起業時に活用できる補助金・助成金110選|申請の流れや注意点も解説
本記事では、「起業時に活用できる補助金・助成金10選」と題し、基礎知識や申請の流れ、さらに注意点までをわかりやすく解説します。これから起業を目指す方に向けて、有益な情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。
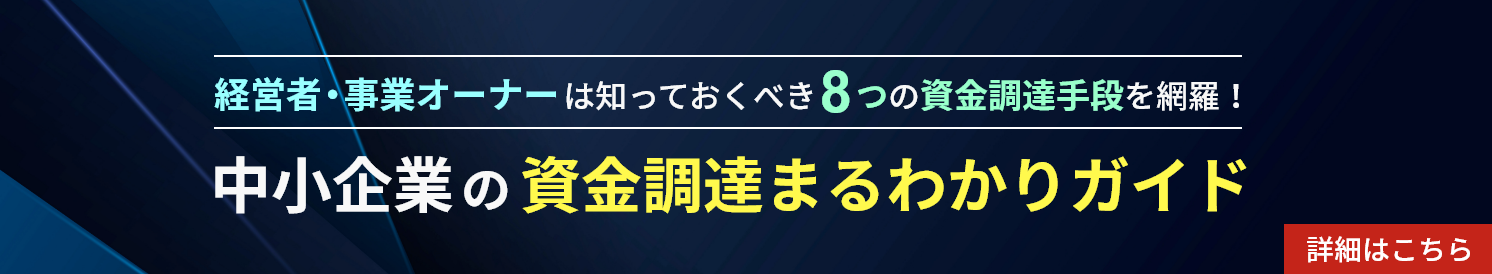

補助金・助成金の基礎知識
起業時の資金調達において、返済不要な補助金・助成金の活用は重要な選択肢となります。しかし、種類が多く内容も異なるため、制度の特徴を正しく理解することが大切です。
ここでは、補助金・助成金の基本的な違いや特徴について解説していきます。
補助金・助成金の違い
補助金と助成金は、支給方法や審査基準において大きく異なります。補助金は採択数に上限があり、応募者の中から審査によって支給対象が選ばれます。その分、支給額は大きく設定されており、長期的な事業成長を見据えた支援という特徴があります。
一方、助成金は定められた要件を満たせば高い確率で支給される制度です。主に雇用関係の支援が中心で、支給額は補助金と比べて限定的です。申請期間も補助金が1ヵ月など短期間なのに対し、助成金は随時または長期間受付という違いがあります。
また、財源面でも違いがあり、補助金は税金を財源とする制度が多いのに対し、助成金は雇用保険料を財源とするものが中心です。事業計画書の重要性も異なり、補助金では会社の長期的な成長性を示す詳細な計画が求められます。
交付金・給付金との違い
補助金・助成金に似た制度として、交付金と給付金があります。交付金は、国から地方自治体などの組織に対して、特定の政策やプロジェクトの実施を目的として交付されるものです。補助金・助成金のように直接事業主に支給されるわけではなく、複数の企業や団体で構成されるプロジェクトの中心組織に交付される点が特徴です。
給付金は、主に病気や災害による被災者支援を目的とした制度です。企業向けの補助金・助成金と異なり、個人を対象としたものが多いのが特徴です。失業給付金や育児給付金などが代表的な例として挙げられます。
いずれも返済不要という点は補助金・助成金と共通していますが、支給対象や目的が異なります。
↓補助金・助成金の返還については下記記事をご参考ください。
【関連記事】助成金の消費税分は返還が必要?仕入控除税額や補助金との違いも解説
【関連記事】補助金制度の返還事例はある?返さなければいけない場合について解説!
起業時に補助金・助成金がおすすめの理由
起業時の資金調達において、補助金・助成金の活用は非常に魅力的な選択肢といえます。その最大の理由は、融資とは異なり返済義務がないという点です。事業の立ち上げ期に返済の心配をすることなく、経営に専念できる環境を整えることができます。
特に創業間もない時期は、資金調達に課題を抱えやすい状況です。補助金や助成金を獲得することで、初期投資にかかる自己資金の負担を大きく軽減できます。賃借料や人件費、広告宣伝費など、創業時に必要となる経費の一部を補填できるため、より柔軟な事業展開が可能となります。
また、補助金・助成金の申請過程は、事業計画をより具体化するきっかけにもなります。多くの制度では事業計画書の提出が求められ、その作成を通じて自社の強みや市場性、収支計画などを改めて見直すことができます。これは補助金の獲得だけでなく、事業の成功確率を高めることにもつながります。
さらに、補助金や助成金の採択を受けることは、金融機関からの信用度向上にも寄与します。公的機関による事業性の評価を得られたことになるため、日本政策金融公庫などからの融資を受けやすくなるメリットがあります。補助金を担保として活用できるケースもあり、さらなる資金調達の可能性が広がります。
補助金・助成金の運営元は主に4つ

補助金・助成金制度は、さまざまな団体によって運営されています。それぞれの機関が異なる政策目標や支援方針を持ち、特色のある制度を展開しています。主な運営元は以下の4つです。
・ 経済産業省
・ 厚生労働省
・ 地方自治体
・ 民間団体・企業
各機関の特徴と代表的な支援制度を見ていきましょう。
経済産業省
経済産業省は、経済産業の発展と国際競争力の向上を目指し、幅広い支援制度を提供しています。とりわけ、小規模な事業者や起業家の成長を後押しする中小企業庁を通じて、多様な支援策を展開しています。地域活性化や中小企業の振興に重点を置いた補助金が豊富で、創業間もない企業の成長を支える制度が充実しています。
また、インバウンド観光客の誘致や省エネルギー推進など、時代のニーズに応じた事業支援も行っています。経済産業省の支援制度は補助金が中心で、助成金は扱っていないのが特徴です。
厚生労働省
厚生労働省は、福祉・労働・雇用分野における支援に注力しています。職業能力の向上を図る補助金や、雇用促進のための助成金を数多く設けています。高齢者や障がい者の雇用支援、第二新卒者の採用支援など、多様な人材の活躍を促進する制度が特徴的です。
地域の雇用情勢改善も重要な目的の一つとなっており、事業所の設置や労働者の雇い入れを支援する制度も用意されています。企業の成長段階に合わせて活用できる制度が多いため、創業時から将来を見据えた制度選びが可能です。
地方自治体
各市区町村は、地域特性やニーズに応じた独自の支援制度を展開しています。例えば、松本市では新規開業者向けの家賃補助制度を設ヵ月額8万円を上限に最大2年間の支援を行っています。港区では、新規開業者への賃料補助やWebサイト作成、販路開拓への補助金を提供しています。
ただし、自治体によって産業系の補助金が充実しているところと、福祉系の支援が中心のところがあります。また、その時々の政策方針により、制度の内容や金額が変更される可能性もあるため、こまめな情報収集が欠かせません。
民間団体・企業
公益財団法人や民間企業も、社会貢献の一環として独自の助成金制度を設けています。例えば、三菱UFJ技術育成財団では、新技術や新製品の開発に対して最大300万円の助成を行っています。審査基準は事業の実現可能性や革新性、社会貢献度などで、厳格な選考が行われます。
公益財団法人・助成財団センター(JFC)のWebサイトでは、さまざまな条件から助成金を提供している団体を検索できます。事業内容と親和性の高い支援制度を見つけやすい環境が整っています。
起業・創業時に活用できる主な補助金・助成金10選

起業時の資金調達において、返済不要な補助金や助成金の活用は非常に重要です。特に創業時は設立費用だけでなく運転資金も必要となるため、複数の支援制度を組み合わせることで、より安定した経営基盤を築くことができます。
以下では、活用しやすい制度を厳選してご紹介します。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の持続的な経営に向けた取り組みを支援する制度です。申請できる事業者は従業員数が商業・サービス業で5人以下、製造業やその他の業種で20人以下の小規模事業者となります。
補助上限額は通常枠で50万円、賃金引上げ枠や創業枠では200万円となっています。いずれも補助率は3分の2以内で、インボイス特例の要件を満たす場合は50万円が上限額に加算されます。
本制度の特徴は、対象となる事業範囲が広く、小規模事業者向けの補助金としては比較的ハードルが低い点です。事業計画の策定には商工会議所による指導を受けられるため、創業間もない事業者にとって心強い制度といえます。
事業再構築補助金
事業再構築補助金は、ウィズコロナ時代における事業の再構築や業態転換を支援する制度です。2024年の第12回公募では、成長分野進出型やコロナ回復加速化型など、複数の類型が設けられています。
補助金額は、中小企業の場合で最大3,000万円から4,000万円となっており、補助率は2分の1または3分の2です。建物購入や機械装置の導入、広告宣伝費など、幅広い経費が対象となります。
審査では事業計画の合理性や説得力が重視され、新規事業の有望度や実現可能性について慎重な審査が行われます。そのため、綿密な事業計画の策定が求められます。
IT導入補助金
IT導入補助金は、企業のデジタル化を促進するための支援制度です。会計ソフト、受発注システム、決済システムなどのITツール導入費用が補助対象となります。
通常枠では補助率2分の1、補助額は5万円から450万円までとなっています。インボイス対応のITツールを導入する場合は、インボイス枠として補助率が3分の2から4分の3に引き上げられます。
特徴的なのは、PCやタブレット、プリンターなどのハードウェアも補助対象となる点です。創業時のIT環境整備に活用できる実践的な支援制度といえます。
事業承継・引継ぎ補助金
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継や事業再編を契機とした新たな取り組みを支援する制度です。経営革新、専門家活用、廃業・再チャレンジの3つの事業類型があります。
経営革新枠の場合、設備費や外注費、マーケティング調査費などが補助対象となり、補助率は2分の1または3分の2、補助上限は600万円から800万円です。
事業承継や事業再編による起業を検討している場合に活用できる制度で、新たな事業展開のための経費を手厚くサポートしています。
地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)
地域中小企業応援ファンドは、都道府県や地域金融機関と中小企業基盤整備機構が一体となって実施する助成制度です。地域の特産品や観光資源を活用した事業など、地域貢献度の高い新規事業の開発を支援します。
各都道府県の産業ビジョンや重点施策によって助成対象事業は異なり、企業所在地の都道府県に該当ファンドがない場合は原則として助成を受けることができません。
ものづくり補助金
この補助金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援する制度です。特に働き方改革への対応やインボイス制度への準備、新しいサービスの開発などに活用できます。
申請枠は省力化(オーダーメイド)枠、製品・サービス後付加価値化枠、グローバル枠の3種類が設定されており、従業員数に応じて補助上限額が変動します。例えば、従業員5人以下の場合、補助上限額は100万円から750万円で、補助率は対象経費の2分の1となっています。
申請にあたっては事業計画書の策定が重視され、付加価値額や給与支給総額の増加などの条件を満たす必要があります。
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
地域の雇用機会創出を目的とした助成制度で、特に雇用が不足している地域で事業所を設置し、地域に居住する求職者を雇い入れる場合に利用できます。
この助成金は1年毎に最大3回支給され、設置費用と対象労働者の増加数に応じて助成額が決定されます。中小企業の場合は初回支給時の助成額が1.5倍になり、さらに創業と認められる場合は2倍となる特例もあります。
事前に事業所の設置・整備と求職者の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出することが必要です。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験が不足している求職者などを、正社員としての採用を前提に一定期間試行雇用する制度です。原則として3ヵ月間のトライアル期間中、1人当たり月額4万円が支給されます。
支給対象となる労働者は、1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用を希望し、ハローワーク等に求職申込をしている方です。また、過去2年以内に2回以上の離職や転職を繰り返している方、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている方などが対象となります。
研究開発型スタートアップ支援事業
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実施するこの事業は、技術シーズの事業化を目指すスタートアップ企業を支援します。シード期の研究開発型スタートアップに対する事業化支援や、認定VCによる出資を前提とした実用化開発支援などが含まれます。
支援内容は、起業家候補人材の発掘から事業化までを一貫してサポートし、ビジネスプランの構築支援や研修、コンテストなども実施しています。経済の活性化や新規産業・雇用の創出を目的としており、革新的な技術の実用化を目指す起業家に適しています。
キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するための助成金制度です。正社員化コース、障害者正社員化コース、賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コース、社会保険適用時処遇改善コースなど、様々な支援メニューが用意されています。
事前に「キャリアアップ計画」を作成し、労働組合等の意見を聴取する必要があります。例えば、正社員化コースでは、有期雇用労働者を正社員に転換した場合、1人あたり最大72万円の助成を受けることができます。創業後の人材育成や処遇改善に活用できる制度といえます。
【大都市起業向け】補助金・助成金

大都市圏での起業を考えている方向けに、東京都や大阪府などの地域独自の補助金・助成金制度が充実しています。
これらの制度は地域の特性や課題に合わせて設計されており、地域経済の活性化に貢献する事業を重点的に支援します。以下では、主要な大都市圏の支援制度について詳しく解説します。
(東京都)創業助成事業
東京都中小企業振興公社が実施するこの制度は、都内での創業を目指す方々を包括的に支援します。従業員の人件費、事務所の賃借料、広告費など、創業時に必要となる幅広い経費を対象としています。
対象となるのは都内で創業を予定している方、または創業後5年未満の中小企業者等で、TOKYO創業ステーションでの事業計画書策定支援修了者や東京都制度融資利用者などの一定要件を満たす方です。助成限度額は上限400万円、下限100万円で、助成対象経費の3分の2以内が支給されます。
助成対象期間は交付決定日から6ヵ月以上2年以下となっており、長期的な視点での事業展開をサポートします。
(東京都)若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 / 商店街起業・承継支援事業
これらの制度は、都内商店街の活性化を目指す新たな担い手を支援します。特に若手・女性リーダー応援プログラムは、女性または39歳以下の若手男性で、都内商店街での開業を目指す方が対象です。
店舗の新装・改装工事費や設備・備品購入費は助成率4分の3以内で、上限400万円までの支援を受けることができます。さらに店舗賃借料についても、3年間にわたって段階的な助成を受けられ、1年目は月額15万円、2年目は12万円、3年目は10万円を上限とした支援があります。
(大阪府)大阪起業家グローイングアップ事業
【地方起業向け】補助金・助成金

地方創生の流れを受けて、地方での起業を支援する制度が充実してきています。東京圏からの移住を伴う起業や、地域資源を活用した新規事業の立ち上げなどに対して、手厚い支援が用意されています。
以下では、地方での起業を考えている方に特におすすめの支援制度を紹介します。
起業支援金
東京圏以外の地域や条件不利地域での起業を支援する制度です。地域の課題解決に資する社会的事業を新たに立ち上げる方を対象に、事業化までの伴走支援と最大200万円の補助金が提供されます。
対象となる事業分野は、子育て支援、地域産品を活用する飲食店、買い物弱者支援、まちづくり推進など、地域の実情に応じて幅広く設定されています。補助率は対象経費の2分の1で、都道府県が選定する執行団体が事業計画の審査や立ち上げに向けた支援を行います。
実際の申請に当たっては、東京圏以外の道府県または東京圏内の条件不利地域で事業を行うこと、補助事業期間完了日までに個人開業届または法人設立を行うこと、そして起業地の都道府県内に居住または居住予定であることが求められます。
移住支援金
東京23区からの移住者の地方定着を促進するユニークな支援制度です。東京圏外または東京圏内の条件不利地域へ移住し、起業や就業などを行う方に対して、都道府県と市町村が共同で交付金を支給します。
支給額は世帯の場合100万円以内、単身の場合は60万円以内で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円が加算されます。
この制度を利用するには、移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23区へ通勤していた実績が必要です。また、移住後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があることも求められます。地方での起業と移住を同時に考えている方にとって、有力な支援制度となっています。
起業者向け補助金・助成金の活用事例
ここでは、実際に補助金を活用して起業に成功した事例を紹介します。人材採用サービスを提供するA社の例を見ていきましょう。
サービス業として創業したA社は、中小企業の人材不足という地域課題に着目しました。前職での営業経験から、多くの中小企業が採用活動に苦心していることを知り、企業と求職者を結ぶマッチングサービスを立ち上げることを決意しました。
補助金の活用方法として特徴的だったのは、大手人材会社との契約締結と自社ホームページの制作に補助金を充てた点です。求職者データベースへのアクセス権を獲得し、効率的な人材スカウト体制を構築。同時に、商談時の説明ツールとして活用できる自社ホームページを開設しました。
このホームページには求人票のデータ管理機能や求職者の進捗管理機能も実装され、事業運営の効率化にも貢献しています。補助金がなければ、これらの初期投資を抑制せざるを得ず、サービスの立ち上げに時間がかかったかもしれません。
A社の代表は「創業時には様々なイニシャルコストがかかる中、補助金があることで広告宣伝費を削減でき、事業のコストパフォーマンスを高められました。また、補助金の申請過程で受けたビジネスサポートにより、経営者としてのマインドセットができました」と語っています。
この事例から、補助金は単なる資金援助以上の価値があることがわかります。申請時の事業計画作成や専門家からのアドバイスを通じて、事業の方向性を見直したり、新たな気づきを得たりする機会にもなるのです。
補助金・助成金の申請条件

補助金や助成金の申請には一定の条件が設けられています。受給資格を得るためには、これらの条件を事前に確認し、要件を満たしておく必要があります。
雇用保険適用事業所の事業主である
補助金や助成金を受給するための基本的な要件として、雇用保険適用事業所の事業主であることが挙げられます。労働者を1人でも雇用する事業主は、事業形態が個人事業主か法人かにかかわらず、雇用保険への加入が求められます。
新たに従業員を採用した場合は、速やかに管轄のハローワークで雇用保険の被保険者資格取得の手続きを行う必要があります。この手続きが遅れると、助成金や補助金の申請に支障をきたす可能性があるため、注意が必要です。
支給のための審査に協力する
助成金・補助金は公的資金による支援制度であるため、適切な審査協力が不可欠です。具体的には、支給や不支給を決定する審査に必要となる書類の整備と適切な保管が求められます。
また、管轄労働局から書類提出の要請があった場合には、速やかに対応することが重要です。さらに、労働局などによる実地調査が実施される場合もあり、その際は誠実な対応が必要となります。
申請期間内に申請する
補助金・助成金の申請には、定められた期間内での手続き完了が必須となります。申請期間を過ぎてしまうと、たとえ条件を満たしていたとしても申請を受け付けてもらえません。時間指定で締め切られる事業もあるため、余裕を持った対応が大切です。
書類提出方法には「郵送のみ」や「持参のみ」と指定がある場合もあり、事前予約が必要なケースもあります。また、書類の不備があった際の修正時間も考慮し、できるだけ締切直前の申請は避けることが望ましいでしょう。
受給対象外となる条件
以下の条件に該当する事業主は、補助金・助成金を受給することができません。
1. 不正受給から3年以内に支給申請をした事業主、または支給申請日後から支給決定日までの間に不正受給をした事業主
2. 支給申請日の属する年度の前年度より前の労働保険料を納入していない事業主
3. 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
4. 事業主または役員等が暴力団と関わりのある場合
5. 事業主または役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れのある団体に属している場合
6. 倒産している事業主
7. 不正受給が発覚した際の事業主名等の公表について、同意していない事業主
補助金・助成金の申請の流れ

補助金や助成金の申請から交付までには、一連の手続きが必要です。具体的には、以下の6つのステップで進められます。
1. 申請書をダウンロード
2. 交付申請書を提出
3. 審査
4. 交付決定通知
5. 事業開始
6. 補助金・助成金の交付
最初のステップとして、各制度のWebサイトから募集要項と申請書類をダウンロードします。募集要項をよく確認し、自社が対象となる条件を満たしているか精査することが重要です。申請書は正確な情報を入力し、必要な書類を漏れなく用意しましょう。
次に、準備した交付申請書を指定の窓口へ提出します。提出方法は制度によって異なり、郵送・電子申請などさまざまな方法があるため、要項で確認が必要です。
提出された申請書は受理され、審査へと進みます。審査では、事業内容や計画の実現性などが評価されます。審査をクリアすると、交付決定の通知が届きます。
交付決定通知を受け取った後、いよいよ事業をスタートすることができます。事業は申請時の計画に沿って進めていくことが求められます。また、実施状況を示す実績報告書などの提出も必要になります。
最後のステップとして、実績報告書などの確認を経て、補助金・助成金が交付されます。計画通りに事業が進められ、必要な報告が完了していることが交付の条件となります。
このように、補助金・助成金の申請から交付までには複数のステップがあり、各段階での適切な対応が求められます。事前に全体の流れを把握し、計画的に進めることが重要です。
個人事業主の開業時でも補助金・助成金を申請できる?
個人事業主の開業時も、さまざまな補助金や助成金を活用することができます。法人格を持たない個人事業主でも申請可能な制度として、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金、IT導入補助金などが挙げられます。
例えば小規模事業者持続化補助金は、従業員数5人以下(製造業は20人以下)の小規模事業者を対象としており、個人事業主も申請が可能です。補助対象となる経費の3分の2以内、最大50万円までの補助を受けられます。
ただし、U・Iターン創業応援事業のように個人事業主の法人成りを対象外とする制度も存在します。また、すでに開業届を提出していたり、創業から一定期間が経過していたりすると対象外となる場合もあります。
そのため、個人事業主が補助金や助成金の活用を検討する際は、申請要件を慎重に確認することが大切です。特に地域限定の制度では、移住に関するルールなども把握しておく必要があります。
このように、個人事業主でも活用できる支援制度は豊富に用意されています。自身の事業に合った補助金や助成金を見つけ、効果的に活用することで、事業の成長を加速させることが可能です。
関連記事:【最新】フリーランス・個人事業主向けの助成金・補助金を一覧で紹介!
起業向け補助金・助成金を受けるときの注意点

起業時の資金調達手段として魅力的な補助金・助成金制度ですが、申請から受給までには注意すべき点がいくつか存在します。以下で主な注意点を解説します。
原則として後払い
補助金や助成金は、基本的に後払いで支給される仕組みとなっています。特定の経費の一部を補助する補助金の場合、まずは事業者が対象となる経費を一旦負担する必要があります。その後、補助対象経費の確認などが行われ、問題がなければ支給される流れです。
給付までの期間は制度によってさまざまですが、数か月から1年ほどかかるケースも少なくありません。そのため、資金繰りには十分な余裕を持たせた計画が求められます。
また、補助金や助成金を事業資金の主軸として考えるのではなく、あくまでも補助的な支援制度として活用するのが賢明です。事業の継続性を考慮すると、手元資金や他の資金調達手段と組み合わせた柔軟な資金計画が重要になります。
採択されないと支給されない
補助金などは全体の予算が決まっており、予算の範囲内で支給する対象者を決める仕組みとなっています。そのため、申請要件を満たしたうえで申請しても、採択されず補助金を受給できないケースも発生します。
特に補助金は助成金と比べて競争率が高い傾向にあり、採択のハードルは決して低くありません。高倍率の補助金では、事業の実現性や社会的意義など、さまざまな観点から厳しい審査が行われます。
事業計画が優れているだけでなく、その内容を申請書で的確に表現することも重要です。説得力のある申請書の作成には、事業計画の具体性や数値目標の設定なども求められます。場合によっては中小企業診断士や税理士などの専門家に相談することも検討に値するでしょう。
準備に時間と労力がかかる
申請する助成金や補助金によって、提出しなければならない書類は異なります。事業計画書や収支計画書、応募申請書類など、制度への応募には多くの書類の準備が不可欠です。
特に補助金の申請では、高い倍率を勝ち抜くためには事業を実施する価値があると認識してもらえるようなアピールが必要です。すでに創業している場合は、創業から現在までの各種帳簿が必要になることもあります。
さらに、書類作成には専門知識が求められることもあり、予定外の費用が発生する可能性もあります。必要な書類を整備し、適切に保管する体制を整えることも重要です。申請期間も限られているため、充実した内容の書類を作成するには、早めの準備開始が欠かせません。
公募が変更・廃止される場合がある
補助金や助成金は、毎年度の予算配分や政策により、金額の変動や公募の有無が変わることがあります。現在応募を検討している制度であっても、次年度には公募されない可能性や、支給条件が大きく変更される可能性があります。
制度の改定は予告なく行われることもあるため、常に最新の情報をチェックすることが重要です。特に地域限定の制度では、その地域の政策方針によって支援内容が大きく変わることもあります。
このような状況に備えて、補助金・助成金以外の資金調達方法も並行して検討しておくことをおすすめします。融資や出資など、複数の選択肢を持っておくことで、事業の継続性を高めることができます。
複数受給ができないケースも
税金を財源とする政府系の助成金・補助金は、複数の制度を同時に受給できないケースがあります。特に、対象となる同一の経費に対して複数の助成を受けた場合など、実際に拠出した経費よりも受け取る金額が多くなってしまう可能性がある場合は、厳格なルールが定められています。
ただし、応募自体は同時に複数行うことが可能です。申請書類にも共通する項目が多いため、同時に書類を作成していくつかのプログラムに応募し、採択されてから選択するという方法も考えられます。
事前に各制度の併給制限を確認し、最適な組み合わせを検討することが重要です。不明な点がある場合は、各制度の運営窓口に問い合わせて確認するようにしましょう。
補助金・助成金以外で起業資金を調達する方法
補助金や助成金は返済不要な資金として魅力的ですが、採択の不確実性や後払いといった特徴があります。そのため、他の資金調達手段と組み合わせて活用することをおすすめします。
ここでは、補助金・助成金以外の主な資金調達方法について解説します。
創業融資
起業時の資金調達方法として、融資を活用するのも有効な選択肢です。政府系金融機関による創業融資では、一般の金融機関と比べて低金利で長期の返済期間が設定されており、創業時の負担を軽減できます。
例えば日本政策金融公庫の創業融資では、事業計画の実現性や返済能力などが審査されますが、補助金とは異なり予算枠による制限がないため、要件を満たせば融資を受けられる可能性が高くなります。また、補助金と併用することも可能です。
さらに、創業前であっても事業計画が具体的であれば、融資の対象となることがあります。事業開始時の設備投資や運転資金など、必要な資金を確実に確保できる点が大きなメリットです。事業計画書の作成など、準備に時間がかかる面はありますが、補助金よりも迅速に資金を調達できます。
【関連記事】起業・開業時におすすめの創業融資とは?新規開業資金や制度融資について解説
【関連記事】創業融資の審査基準とは?落ちる原因や事前にできる準備を解説
クラウドファンディング
クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数の人から資金を募る方法です。事業のコンセプトや目的に共感した支援者から直接資金を集めることができ、創業資金の調達手段として注目を集めています。
プロジェクトの内容と支援金額に応じたリターン(返礼品)を用意し、支援者を募ります。実現したい事業の社会的意義や独自性をアピールすることで、資金調達と同時にマーケティング効果も期待できます。
資金調達の成否は、プロジェクトの魅力や支援者へのリターンの設定、プロモーション方法などによって大きく左右されます。プロジェクトの準備には時間と労力が必要ですが、事業の認知度向上にもつながる効果的な資金調達手段といえます。
【関連記事】クラウドファンディングとは?仕組みや募集方式とメリット・デメリット
起業では思わぬ出費に備えることも重要
事業を展開していく中では、予期せぬ支出が発生することがあります。そのような場合に備えて、即座に資金を用意できる体制を整えておくことが重要です。
一定の与信枠を確保できるビジネスカードローンは、急な資金需要に対応できる有効な選択肢です。必要な時に必要な金額だけ借り入れできる柔軟性の高さは、起業時の資金繰りの強力な味方となります。
ただし金利は金融機関によって異なり、一般的な融資より高くなる場合があります。複数の金融機関のサービスを比較検討し、自社に適した条件のものを選択することが大切です。また、事業が安定してきた段階で、より有利な条件の資金調達手段に切り替えることも検討しましょう。
このように、起業時の資金調達は複数の手段を組み合わせることで、より安定した事業運営が可能となります。補助金・助成金と他の資金調達手段を効果的に組み合わせ、柔軟な資金計画を立てることをおすすめします。
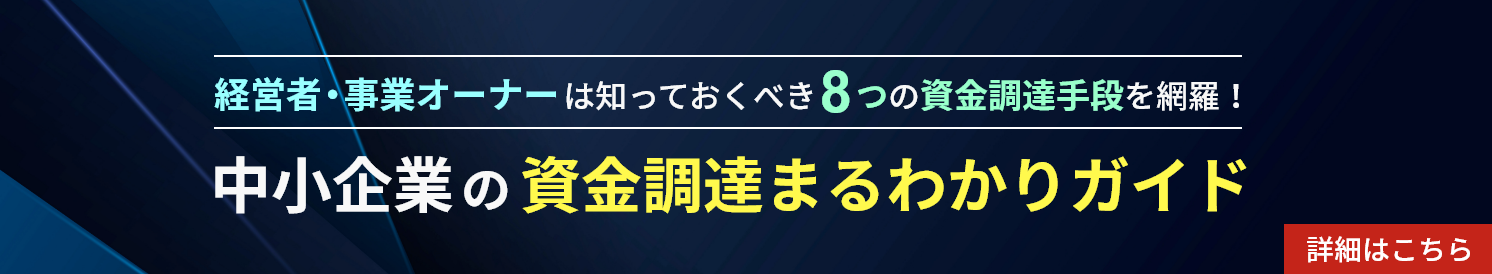

起業では思わぬ出費に備えることも重要
起業時の補助金・助成金は、返済不要な資金として大変魅力的な制度です。しかし、後払いが基本であることや採択の不確実性を考慮すると、他の資金調達手段と組み合わせて活用することが賢明といえます。
ビジネスを展開していく中では、予期せぬタイミングでの支出も発生します。そのような場合に備えて、即時に利用できる資金調達手段を確保しておくことをおすすめします。
例えば、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードは、プラチナ会員専用のコンシェルジュサービスや各種優待特典が利用できる法人カードです。経費管理から資金管理まで、経営者にゆとりと安心をもたらすサービスが充実しています。登記簿がなくても個人与信で審査が可能なため、創業間もない事業者でも利用しやすい特徴があります。


また、ビジネスサポートローンは、最大950万円までの融資枠と優遇金利を備えた融資サービスです。キャッシングよりも低金利の2.8%~9.6%で、まとまった資金を調達できます。審査から最短翌日での融資も可能なため、急な資金需要にも対応できます。
このように、補助金・助成金による資金調達に加えて、ビジネスカードやビジネスローンなど、即時性の高い資金調達手段を組み合わせることで、より安定した事業運営が可能となります。それぞれの特徴を理解し、自社に最適な資金調達手段を選択することが、事業の成長につながるでしょう。