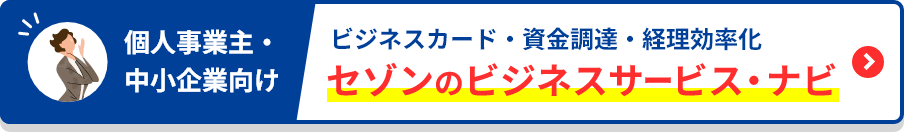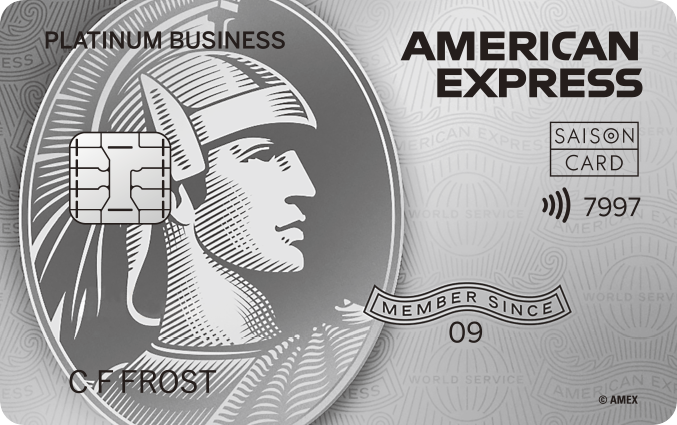NDA(秘密保持契約)の作り方を解説!作成のタイミングやチェックポイントもご紹介
特許を申請したり、取引相手が不正競争防止法に違反する行為をした際に損害賠償請求訴訟を提起したりする際に、NDA(秘密保持契約)の締結の有無によって特許庁や裁判所の判断が左右されることがあります。
しかし、「NDA(秘密保持契約)」という単語を耳にしたことがあっても、どのような文面の契約書を作成すれば良いのかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、NDA(秘密保持契約)についてわかりやすく解説し、秘密保持契約書の作成方法や、取引先が契約に違反した際の対処法についてもご紹介いたします。

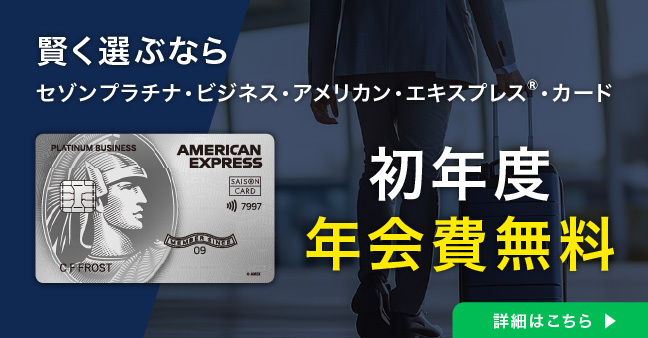
NDA(秘密保持契約)とは?

NDA(秘密保持契約)とは、取引で知った営業秘密や顧客の個人情報などを取引の目的以外に利用したり、他人に開示したり、漏洩させたりすることを禁止する契約を指します。
「Non-Disclosure Agreement」の略称で、日本語では「秘密保持契約」と訳されています。
具体的な内容や対象の範囲は契約ごとに異なるため、NDA(秘密保持契約)を締結する際は契約書の内容をしっかりと確認しましょう。
NDAを締結する目的
NDA(秘密保持契約)を締結する目的は、大きく分けて下記の3つが挙げられます。
■不正競争を防止するため
■情報漏洩を防ぐため
■個人情報保護法の遵守のため
情報開示が自社に不利益をもたらすことがないように、事前にNDA(秘密保持契約)を締結しておきましょう。
以下、それぞれの項目について詳しく説明していきます。
①不正競争を防止するため
不正競争とは「不正競争防止法」で定められた行為を指し、定義のなかには「営業秘密の侵害」も該当するとされています。
例えば自社が開発中の商品・サービスの情報を第三者が不正に入手し、その情報に依拠した商品・サービスを作った場合は「営業秘密の侵害」に該当します。
このような侵害を受けた場合には、差止請求や損害賠償請求が可能です。
ただし、営業秘密を開示した相手方とNDA(秘密保持契約)を締結しておらず、かつ開示した情報が客観的に見て秘密ではないと判断されるような場合、該当の行為が不正競争防止法における「不正競争」として認定されないリスクが生じます。
不正競争防止法における「営業秘密」と認められるためには、NDA(秘密保持契約)を締結するなどの措置によってその情報が「秘密」として管理されていることが条件とされる点に留意しましょう。
②情報漏洩を防ぐため
社外への業務委託時、事前にNDA(秘密保持契約)を締結しないと、重要な情報が自社のコントロールできない場所で流出してしまう可能性があります。結果、発表タイミングを別に定めている商品戦略の失敗が起きたり、顧客からの信頼の低下なども発生しかねません。
また、開発中の商品に関する技術(発明)について特許出願を行う予定がある場合も、その技術情報の開示先とNDA(秘密保持契約)を締結しておくことは極めて重要です。
というのも、出願前に「不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明」は「公然と知られた発明」であるとして特許を受けられないとされています。
このような事故を防ぐためにも、NDA(秘密保持契約)の締結が重要となっているのです。
なお、こちらも①と同様にNDA(秘密保持契約)の締結に限らず、開示する情報を秘密情報として管理する必要がある点にご注意ください。
③個人情報保護法の遵守
取引の相手方と特定の個人を識別することができる「個人情報」を含む情報をやりとりする場合には、その取り扱いに際しては個人情報保護法を遵守しなければなりません。
情報流出に発展する危険性もあるため、氏名や生年月日といった個人情報を取り扱う際には細心の注意を払う必要があります。
社外の委託先に個人情報を含むデータを送信する場合は、あらかじめNDA(秘密保持契約)を締結しておきましょう。
NDA(秘密保持契約)を結ぶタイミング
「取引先に自社の秘密情報を開示する予定になっているけれども、NDA(秘密保持契約)をどのタイミングで締結すべきなのだろうか」とお悩みのケースもあるのではないでしょうか。
NDA(秘密保持契約)は、自社の秘密情報を取引先へ開示する前に結ぶ必要があります。
また、商談の材料として秘密情報を提示する際は、商談の成立前であっても結ぶべきです。「契約成立時に締結」では、タイミングが遅いケースもあることにご留意ください。
経済産業省が公開している秘密保持契約書のひな形
不正競争防止法を所管する経済産業省が作成している「秘密情報の保護ハンドブック」には、秘密保持契約書の「ひな形」と呼べるものが収録されています。契約書を作成する際の参考にしてはいかがでしょうか。
■「参考資料2 各種契約書等の参考例」の「第4 業務提携の検討における秘密保持契約書の例」
ただしひな形をそのまま使うのではなく、情報を提供する側なのか受領する側なのかによって文面を変える方が良いでしょう。
情報を提供する側はリスクを負う立場なので厳格な内容の文面を相手方に提示すべきであり、逆に情報を受領する側としては責任を減らすために緩い内容の文面を相手側に提示すべきです。
契約を締結する前には、弁護士からアドバイスをもらうことをおすすめします。
NDA(秘密保持契約)を結ぶ手順
NDA(秘密保持契約)を結ぶ手順は以下のとおりです。
1.当事者間の認識に違いがないか確認する
2.NDA(秘密保持契約書)を作成する
3.調印をする
それぞれの項目について解説します。
当事者間の認識に違いがないか確認する
契約を結ぶ前に当事者間に認識の違いがないか確認することが重要です。ひな形も当事者間で協議してどちらのひな形を使用するか決めましょう。
相手のひな型を使用する場合は、秘密情報の定義や、情報を利用できる範囲などを確認してから契約するようにします。懸念される項目があり、ご自身で判断が難しい場合は、弁護士にリーガルチェックを依頼しましょう。
NDA(秘密保持契約書)を作成する
双方が契約に合意できた場合は、契約書の原案を作成します。
秘密保持契約書が完成した後は、事前に協議した内容と違いがないか確認するようにしましょう。
調印をする
秘密保持契約書は契約の当事者の数だけ必要となり、作成したうえで、それぞれ当事者が調印して割印することで契約の締結となります。
割印とは印鑑を2つ以上の文章にまたがるように押すことで、文書の関連性を示す押印方法です。ただし、契約の締結が電子署名の場合は割印が不要となっています。
NDA(秘密保持契約書)に記載する項目
NDA(秘密保持契約書)に記載する項目の例を、経産省の公開しているひな型をはじめとした資料を元に表にまとめました。
| 記載すべき項目 | 記載内容の詳細 |
|---|---|
| 秘密情報の定義・帰属 | どのような情報が「秘密情報」に該当するのか、秘密情報はどこに帰属するのか |
| 使用目的 | 秘密情報を用いてどのような行為を行えるか |
情報複製の制限 |
秘密情報を含む資料(顧客名簿や企画書、研究中のデータや関連書類など)の複製可否(取引の目的の範囲内に限る)や、情報取扱管理者を定めて厳重に管理する旨など |
返還および消去 |
秘密情報を含む記録媒体・物件が不要になった場合や相手から請求があった場合に「媒体・物件を返還する義務」、また「自己の保有する記録媒体などに複製していた場合は消去・破棄する義務」など |
| 損害賠償および差止請求 | 秘密情報の不正使用や漏洩時に損害賠償・差止請求を行う旨 |
| 人物 | 誰に対して秘密保持義務が課せられるのか |
| 期間 | いつからいつまで秘密保持義務が課せられるのか(プロジェクト終了後や退職後に不正開示・使用しないことを誓約する旨) |
| 協議事項 | 契約に定めのない事項について、または、契約に疑義が生じた場合は協議のうえ解決する旨 |
| 管轄裁判所 | 紛争が発生した場合に第一審を行う、専属的合意管轄裁判所はどこか |
これら以外にも自社の状況に応じて必要な項目があれば、秘密保持契約書に盛り込んでください。
秘密情報となるかどうかの判断のポイントは、「情報開示側に損害を被る可能性がある情報であるかどうか」です。
ただし、締結時にすでに公表されている内容はもちろん、情報を開示された側の責めに帰すべき事由によらずに漏洩した情報については、秘密情報とみなされないことがある点にご注意ください。
「何を記載すべきか判断できない」という場合は、弁護士などに相談することをおすすめします。
NDA(秘密保持契約書)作成時の注意点
NDA(秘密保持契約)は、当事者双方で協議しながら作成していきましょう。契約内容は、情報を提供するのが一方なのか双方なのかによって変わります。
片方が一方的に情報を提供して、もう片方は受領するのみであれば、受領する側のみが秘密保持義務を負う一方向の契約で問題ありません。
しかし、双方が情報を提供するのであれば、互いに秘密保持義務を負う双方向の契約にする必要があります。
署名・記名押印の必要性
契約書には署名もしくは記名押印が必要で、契約の重要性によっては実印の押印、印鑑証明書の添付を求められるケースもあります。
なお、近年は紙からデジタルデータによる作成に移行しつつあり、電子契約の利用も選択肢のひとつです。
契約内容の合意に達したら、必要部数を作成し、署名もしくは記名・押印を行います。
記名時・押印時には、同一文書であることの証明・改竄防止の観点から、「原本」や「写し」を重ねてから少しズラして両方にまたがるように押印する手法(割印)が用いられます。
また、複数枚にわたる契約書に対しては、ページの連続性を示すために、見開き部分に両ページにまたがるように印鑑を押す「契印」という手法を用いることも覚えておきましょう。
郵便を用いる契約の場合、普通郵便ではなく簡易書留で送付し、相手に返送を依頼しましょう。作成した秘密保持契約書は、紛失したり破損したりすることがないように、双方が厳重に保管しておかなければなりません。
収入印紙の必要性
秘密保持に関する合意のみを盛り込んだ契約書であれば、収入印紙は不要です。
ただし、「請負に関する契約」など、秘密保持以外の事項を盛り込んでいる場合は、収入印紙が必要となるケースがあります。
例えば、秘密情報を用いたソフトウェア開発や、広告に関する契約を締結する場合、これらは「請負に関する契約書」に該当するため、契約額に応じた金額の収入印紙を貼り付けなければなりません。
締結する契約が該当するか不安であれば、国税庁への相談をご検討ください。
NDA(秘密保持契約書)作成時のチェックポイント
NDA(秘密保持契約書)を作成する際にチェックすべきポイントの例を示します。
■秘密情報の定義が明確になっているか
■どのような目的で秘密情報を開示するのかを正確に記載しているか
■情報が流出した際の損害賠償の内容が明記されているか
万が一、情報が流出してしまった場合に備え、何が秘密情報に該当するかを明確にしておかなければ、流出の責任有無をめぐって争いが発生するかもしれません。
また、どのような目的で秘密情報を開示するのかを正確に記載しておかなければ、秘密情報の目的外使用に該当するかどうかに関して見解の相違が起こる可能性があります。合わせて、損害賠償の内容についても記載しておきましょう。
秘密保持契約書に記載されている内容は千差万別です。「社内でチェックするだけでは不安」という場合は、弁護士などにご相談ください。
NDA(秘密保持契約)に違反した場合の対処方法
契約違反が発生した際の一般的な対処方法は、以下の2つです。
■損害賠償請求
■契約の解除
NDA(秘密保持契約)に違反した場合について、各対処法の説明をしていきます。
損害賠償を請求する
NDA(秘密保持契約)を締結していても、絶対に安全というわけではなく、相手側が情報を不正に持ち出して利用したり漏洩させたりする可能性は否定できません。
そのような問題が発生した際には、刑事告訴を行ったり、民事訴訟を提起して損害賠償を請求したりすることが可能です。
加えて秘密情報の利用をやめさせることを目的とした差止請求を行えます。
ただし民事訴訟においては原告側が秘密情報漏洩によって生じた損害額を立証しなければなりません。
損害額を立証するのは困難なケースが多いため、あらかじめ秘密保持義務違反が発生した際の賠償額を定めておくと良いでしょう。
契約を解除する
一般的に契約違反の際の救済措置として、「契約の解除」という手段が存在します。
しかし、相手方が秘密漏洩した際に契約を解除してしまうと、相手方はさらに秘密保持義務から逃れる結果となるため、通常、秘密保持のみを目的とした契約書においては、契約違反の場合の救済措置としての契約解除の規定は盛り込まれません。
NDA(秘密保持契約)を締結する際は顧問弁護士の確認も入れると安心
NDA(秘密保持契約)を締結する際は顧問弁護士の確認も入れると安心です。相手のひな形を使用して契約する場合は、契約書の有利不利を法律の知識から判断してくれるため、契約をしてから不利な項目に気づくリスクを軽減してくれます。
ご自身で秘密保持契約書を作成する場合は、完成してから顧問弁護士の確認を入れることで事前にリスクのある条文を把握できるようになり、契約を進める前に修正することが可能です。
秘密保持契約の締結によって発生するトラブルを未然に防ぎやすくなります。
法人向け顧問弁護士サービスが付帯しているビジネスカード
NDA(秘密保持契約)を締結するにあたっては、顧問弁護士の確認を入れると安心になりますが、どのように探せば良いのかわからない方もいらっしゃるかもしれません。ビジネスカードには、法人向け顧問弁護士サービスが付帯しているものもあります。
セゾンのビジネスカードは、顧問弁護士サービスを含めたビジネスに関する特典が充実しているので、秘密保持契約の締結を含めたさまざまなビジネスに対して活用できます。
法人向け顧問弁護士サービスが付帯しているセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードについて詳しく紹介します。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
| 年会費 | ・年会費33,000円(税込) |
|---|---|
| 国際ブランド | American Express |
| 入会資格 | 個人事業主・経営者をはじめ、安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(学生、未成年を除く) |
| ポイント還元率 | 1,000円(税込)の利用につき1ポイント |
| 発行までの期間 | 最短3営業日後 |
| 主な特典 | ・リーガルプロテクト(※1)の優待 ・「デジタル会員証(プライオリティ・パス アプリ)」に年会費無料でお申し込み可能(通常年会費469米ドル/プレステージプラン) ・SAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)への無料登録 ・コンシェルジュ・サービス |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、年会費33,000円(税込)でビジネスに関するさまざまな特典が付帯しています。
ポイントの還元は1,000円(税込)の利用につき1ポイントですが、海外利用では2倍になります。税金の支払いも通常の還元率でポイントを獲得可能です。
ベリーベスト法律事務所が提供する法人向け顧問弁護士サービス「リーガルプロテクト(※1)」の優待が付帯しており、利用料が割引されます。
NDA(秘密保持契約)の締結を含めたさまざまな法務に対応できるだけでなく、弁理士・司法書士・税理士・行政書士も在籍していることから、税務や労務など幅広いニーズにも対応可能です。
また、相談内容のニーズに合わせて第一東京弁護士会を通じて弁護士を紹介するセゾン弁護士紹介サービスを実施しており、紹介料は無料となっています。
ほかにもさまざまなビジネスに役立つ優待・特典が付帯しており、以下のようなサービスが利用可能です。
■国内最大級のビジネス情報サービス「G-Searchデータベースサービス」:2年間無料
■法人向けモバイルWi-Fi「No.1モバイル」:特別価格で利用可能
世界に広がる1,700ヵ所以上の空港ラウンジをご利用いただける「デジタル会員証(プライオリティ・パス アプリ)」(通常年会費469米ドル/プレステージプラン)に年会費無料でお申し込みいただけますので、高い頻度で海外への出張を行う方にはおすすめです。
JALのマイルを貯めたい方は、SAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)に無料登録ができるため、ビジネスカードの利用で効率的にJALのマイルが貯められます。
法人向け顧問弁護士サービスをはじめとするビジネスに関連する優待・特典が充実したビジネスカードとなっています。
(※1)顧問契約に関するご相談ではない場合、弁護士との面談時に、相談料金が発生する可能性がございます。
相談料金につきましては、ベリーベスト法律事務所のスタッフにお問い合せください。
(※)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
まとめ

営業秘密に該当する情報をやり取りする場合、あらかじめ取引先とNDA(秘密保持契約)を締結しておくべきです。
NDA(秘密保持契約)を締結しておかないと、特許を申請したり、相手方が不正競争防止法に違反した時や情報漏洩が起きた時、損害賠償請求を行う際に不利になる可能性があります。
秘密保持契約書の内容は、双方で協議しながら、最低限、「情報複製の制限」「損害賠償および差止請求」「人物」「期間」といった項目を盛り込んでいきましょう。
NDA(秘密保持契約)を締結しておけば、相手が秘密保持義務に違反した場合に、より厳格に損害賠償を請求できます。
なお、通常NDA(秘密保持契約)には契約違反の救済措置としての契約解除の規定を入れません。
NDA(秘密保持契約)に記載する内容は契約によって異なるため、経済産業省が公開しているひな形をそのまま使用するのではなく、弁護士などに相談しながら作成することをおすすめします。
「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」は「セゾン弁護士紹介サービス」や顧問弁護士サービス「リーガルプロテクト(※)」が付帯しているので、秘密保持契約書のリーガルチェックを依頼する弁護士を探す際にぜひご活用ください。
最終的に契約内容の合意に達したら、必要部数を作成し、割印や契印を施してください。
また、NDA(秘密保持契約)を締結した際には現場レベルの社員への通達も忘れずに行うことが大切です。
(※)顧問契約に関するご相談ではない場合、弁護士との面談時に、相談料金が発生する可能性がございます。
相談料金につきましては、ベリーベスト法律事務所のスタッフにお問い合せください。
(※)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
この記事を監修した人

【保有資格】
弁護士、宅地建物取引士