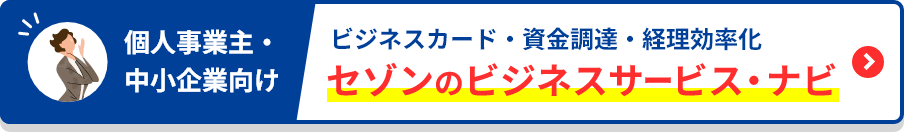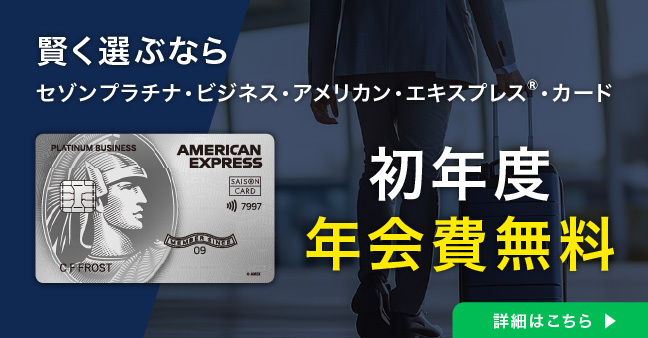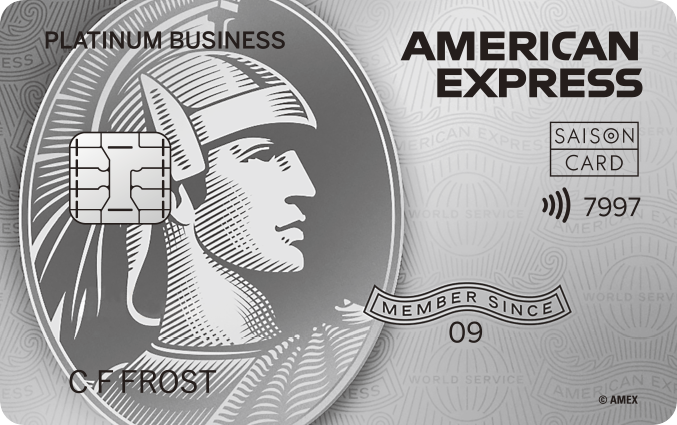個人事業主とは?自営業・法人との違いやメリット・デメリットを解説
「会社に所属せずに自身の腕一本で生計を立てていく人」のようなイメージはありますが、具体的によくわからないまま目指すのは不安です。
また、実際に個人事業主になるために必要な手続きや、会社員との違いなどを知っておくことも重要なポイントになります。
本記事では、個人事業主の定義や自営業・法人との違い、個人事業主のメリットやデメリットなどを説明します。
個人事業主とは?
個人事業主とは、法人を設立せずに個人で何らかの事業を営んでいる方のことを指します。
会社員として働いている場合は勤務先と雇用契約を結んでいますが、個人事業主の方は特定の会社や組織に属しているわけではありません(個人事業主同士の自助団体に属しているようなケースは除く)。
個人事業主になるには、税務署に「開業届」を提出して事業の開始を申請するだけでOKです。
自身の技術一本でいろいろな企業と契約をしながら仕事をする方を「フリーランス」と呼ぶこともありますが、フリーランスも個人事業主の一種です。
個人事業主と自営業の違い
個人事業主も自営業も、自身で事業を経営している点では共通しています。
異なるのは、自営業の場合は法人化して事業を経営しているケースもある点です。例えば、家業の生花店(法人)を引き継いだ事業者や自身で法人を設立した事業者などが該当します。
個人事業主の場合、法人化した形態の事業者は含みません。「法人ではない」ことが、個人事業主の大きな特長です。
個人事業主と法人の違い
個人事業主と法人の主な違いは、それぞれの事業形態にあります。
先述したように、個人事業主とは法人を設立せずに個人で事業を営む方のことです。一方で、法人とは一定の社会的活動を営む組織体であり、人と同じ権利や義務を法律によって認められた組織のことをいいます。
また、個人事業主は税務署に開業届を提出するだけで事業を開始できる一方で、法人を設立するには法人登記が必要だったり、資本金が必要だったりと、さまざまな準備を行う必要があります。
さらに、課せられる税金の種類も個人事業主と法人で異なります。
個人事業主のメリット

個人事業主は、会社に所属して働く会社員とは雇用形態が大きく異なるので、働くうえでのメリットやデメリットも異なります。
個人事業主のメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
・開業届を提出するだけですぐになれる
・働き方が自由なうえに実力次第で収入を大きく増やせる
・青色申告を行うことで特別控除を受けられる
・最大3年間の赤字繰り越しが可能
上記のメリットを順番に説明します。
開業届を提出するだけですぐになれる
会社員や公務員として働くためには、就職活動や入社試験、面接などをクリアする必要があるため、誰でも会社員や公務員として働けるわけではありません。
一方、個人事業主は、税務署に開業届を提出しさえすればすぐになることが可能です。
法人化するのであればいろいろと複雑な手続きを行わなければなりませんが、個人事業主は、すぐに始められることがメリットのひとつです。
働き方が自由なうえに実力次第で収入を大きく増やせる
会社員や公務員の場合、勤務時間や勤務曜日が決められており、場合によっては残業しなければならないこともあります。
個人事業主は働く時間や曜日だけでなく、働く場所や一緒に仕事をする相手なども自由に決められるため、仕事に対する自由度は高いでしょう。
また、給料は明確に決められているわけではなく、仕事内容に応じて取引相手と柔軟に交渉できることが多いので、自身の技術によっては高収入を得ることも可能です。
そのため、個人事業主としてやっていける実力があれば、会社員時代より働いている時間は短いのに収入は会社員時代よりも多いケースも十分あり得ます。
青色申告を行うことで特別控除を受けられる
個人事業主は「売上(収入)-必要経費」で計算される所得によって、支払わなければならない住民税・所得税・個人事業税が決まります。
しかし、青色申告で確定申告を行うと、最大で65万円の特別控除を受けられます。
青色申告を行わずに白色申告で確定申告をする場合は、10万円の基礎控除しか受けられない点には注意が必要です。
最大3年間の赤字繰り越しが可能
個人事業主は1年間の赤字を申告(損失申告)すると、最大3年間まで所得の相殺を行えます。赤字を繰り越すことで納税額を抑えることが可能です。
例えば、個人事業主として独立した1年目に200万円の赤字が出て、損失申告をしたと仮定します。
1年目の所得は0円ですから、所得に応じて課税される住民税・所得税・個人事業税も当然0円となります。
2年目・3年目に100万円ずつ利益が出た場合、本来であれば100万円に対して課税されるところですが、2年目・3年目の利益は1年目に申告しておいた200万円の損失と相殺が可能です。
個人事業主として独立して間もないころは、事業も軌道に乗らず赤字を出してしまうケースも多々あります。
しかし、確定申告をしておけば赤字を繰り越し、将来発生する利益と相殺できるので、個人事業主を目指す方は覚えておきましょう。
個人事業主のデメリット

個人事業主のデメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
・税務署に申請が必要
・青色申告を行うためには複式簿記での記帳が必要
・毎年確定申告を行う必要がある
・失業保険がない
上記のデメリットを順番に説明します。
税務署に申請が必要
個人事業主になるには税務署に申請を行わなければなりませんが、わずかな手続きさえ面倒に感じることもあるものです。
開業届や青色申告承認申請書など、提出しなければならない書類の書き方がわからない場合は、最初の一歩を踏み出すことさえ億劫になってしまうかもしれません。
青色申告を行うためには複式簿記での記帳が必要
青色申告を行うことで最大65万円の特別控除の対象になり、納税額を減らすことができますが、そのためには複式簿記で帳簿を付けなければなりません。
事務職の経験などがない方であれば複式簿記を付けたこともほぼないと思われるので、手間を面倒に感じる可能性が高く、多くの方が挫折しがちです。
先ほど少し触れたように、クラウド型経費精算サービスや会計ソフトを利用すれば比較的楽に経費管理を行ったのち、複式簿記で帳簿を付けることができます。
毎年確定申告を行う必要がある
会社員として働いていれば自身で確定申告を行う必要はありませんが、個人事業主は毎年自身で確定申告を行わなければなりません。
確定申告では1年分の収支に関する情報をミスなくまとめて申告する必要があるため、時間と手間がかかります。
確定申告の時期直前になって準備を始めると間に合わない可能性があるので、普段から少しずつ用意しておくのが良いでしょう。
用意する書類は以下になります。
・給与や年金収入がある場合は源泉徴収票
・医療費控除等の明細書
・各種保険等の証明書
・小規模企業共済等掛金の証明書(加入している場合)
収入の保証がない
個人事業主は会社員ではないため、収入の保証がありません。そのため、取引先から依頼が停止すれば収入が減る可能性があり、取引先の入金が遅延すると自身で督促を行う必要もあります。
また、トラブルの内容によっては、弁護士への相談や法的措置などを検討しなければなりません。トラブルを想定して、複数の取引先を持つ、あるいは取引先とこまめにコミュニケーションをとるなどの対策を行いましょう。
失業保険がない
個人事業主には会社員のような失業保険がないので、仕事がなくなってしまった場合のセーフティーネットがありません。
会社員よりも収入が安定しないにもかかわらず万一の際の保険もないのは、個人事業主として働くうえでの大きなデメリットのひとつです。
仕事がなくなって収入が途絶えてしまった場合に備えて、会社員以上に貯金をしておくなどの対策を心がけましょう。
個人事業主になる場合に行うべきこと

実際に個人事業主になる場合は、税務署への開業届の提出をはじめ、いくつか行うべきことがあります。以下では、 個人事業主になる場合に行うべきことを紹介します。
クレジットカードや住宅ローンの契約
個人事業主は会社に所属していないため、個人事業主として独立したあとに個人でクレジットカードの発行や住宅ローンの契約の際、審査に通過するのが難しくなってしまうことがあります。
会社員として働いている間に、クレジットカードや住宅ローンの契約は済ませてしまうのがおすすめです。
開業届の提出
個人事業主になるには、税務署に開業届を提出する必要があります。下準備を済ませたら、早い段階で税務署に開業届を提出しましょう。
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類のことです。開業届の提出期限は、原則として開業してから1ヵ月以内と決められており、未提出でも罰則はありません。
ただし、提出をしないと確定申告の際に青色申告ができないため、最大65万円の控除はなくなり、確定申告時における最大3年間の損失繰越の適用も受けられなくなってしまいます。
初年度の確定申告を行うまでは、開業届が個人事業主として証明できるものになるので、きちんと保管しておかなければなりません。
また、屋号を付けて事業を行いたい場合は、提出する開業届に屋号を記入しましょう。
個人事業主として活動するうえで、屋号は必須ではありません。しかし、屋号を付けておくと、「屋号付きの銀行口座を作成できるようになる」「法人化する際はそのまま商号として使える」などのメリットを得られます。
青色申告承認申請書の提出
個人事業主の確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、受けられる控除の金額が異なります。
白色申告で受けられる控除は基礎控除の10万円だけですが、青色申告で確定申告を行うと基礎控除の10万円に加えて55万円の特別控除を受けられます。
青色申告を行うためには帳簿を複式簿記で記帳しなければならないなどの条件があるものの、65万円の控除は大きいので、できるだけ青色申告承認申請書を提出して青色申告を行うのがおすすめです。
クラウド型経費精算サービスや会計ソフトなどを利用すれば、日々の経費管理の手間が軽減されるほか、簿記に関する知識があまりなくても複式簿記での記帳を行えるので、青色申告をする方は利用を検討しましょう。
青色申告承認申請書は開業後2ヵ月以内に税務署に提出する必要がありますが、もちろん開業届と同時に提出しても問題ありません。
国民健康保険や国民年金への加入
会社をやめて個人事業主になる場合の保険は、国民健康保険に加入するか、今まで働いていた会社の健康保険を任意継続するかを選択します。
ただし、業界によっては、業界に特化した健康保険組合がある場合もあるので、自身が加入できる保険を把握したうえでそれぞれの選択肢を比較検討して、最適なものを選ぶようにしましょう。
年金も厚生年金から国民年金に変わるので、自身で加入手続きを行わなければなりません。
厚生年金と比べた場合、国民年金の将来の年金受取額は少なくなるので、老後の資金に関しては自身で備える必要があります。
国民年金だけでなく国民年金基金やiDeCo・NISA・小規模企業共済などの活用も検討しましょう。
個人事業主としての事務面での作業を行う
仕事内容や業種によっては必要ない場合もありますが、個人事業主としてのウェブサイトやブログを開設したり、名刺をつくったりしておくことも重要です。
ウェブサイトやブログで情報発信を行うことによって仕事の受注につながることもあり、事業を行う際に効果的なことが多いです。
個人事業主の主な職種
個人事業主が営む事業にはさまざまな職種があります。
職種の例としては以下のようなものが挙げられます。
●飲食業:レストランやカフェ、ラーメン店など
●IT業:エンジニア、WEBデザイナーなど
●小売業:輸入雑貨店、小物店など
●教育関連事業:学習塾、パソコン教室、フラダンス教室など
●不動産事業:アパート経営、マンション経営、駐車業経営など
近年はインターネット環境が整備されてきたこともあり、ショッピングサイトに自身のネットショップを開設し、商品やサービスを販売する個人事業主も増えています。
個人事業税の税率に関わる法定業種
個人が営む事業のうち、地方税法で定められた以下の業種に対しては個人事業税がかかるため、覚えておきましょう。
| 区分 | 税率 | 事業の種類 |
|---|---|---|
第1種事業 (37業種) |
5% |
物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業 |
| 第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
第3種事業 (30業種) |
5% |
医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業 弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業 |
| 3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、そのほかの医業に類する事業、装蹄師業 |
業種により、個人事業税の税率は異なります。
また、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)の事業主控除があります。
個人事業主の年収
個人事業主の年収はどのくらいの水準にあるのか気になる方も多いでしょう。会社員の年収が給与所得であるのに対し、個人事業主の年収は事業所得となります。
国税庁が公表している「令和5年分申告所得税標本調査結果」によると、令和5年の事業所得者の平均所得金額は483万円です。
また、事業所得者の数を所得金額ごとに分類すると下記の表のようになります。
| 区分 | 申告納税者数(千人) | 構成割合(%) |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 132 | 7.9 |
| 100万円超200万円以下 | 388 | 223.3 |
| 200万円超300万円以下 | 346 | 20.8 |
| 300万円超500万円以下 | 397 | 23.9 |
| 500万円超1,000万円以下 | 272 | 116.3 |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 82 | 4.9 |
| 2,000万円超5,000万円以下 | 37 | 2.2 |
| 5,000万円超1億円以下 | 7 | 0.4 |
| 1億円超 | 2 | 0.1 |
事業所得の金額が300万円以下の構成割合を合計すると52%になっており、全体の50%を超えています。事業所得者の半数を超える方が、年間の事業所得が300万円以内にある結果となっています。
個人事業主を続けていくために必要なこと
個人事業主を長く続けていくためには、次のようなことを意識しておくと良いでしょう。
● 個人事業主を続けるため、あるいは成功するための正解はない
● 常にお金を稼ぐ意識を持つ
● 1回の失敗であきらめず、挑戦する心意気を持つ
● 従来のやり方にこだわらず、新しいことを始めたり、柔軟に対応したりする
● 許容できるリスクを想定し、思い切った行動、新しい挑戦も検討する
● 赤字が続いても続けられる生活資金を確保する
● 常に自身の能力を磨く努力を怠らない
● 商品、サービスの独自性を確立する
● 常に新しい情報を手に入れる姿勢
● 多くの人と良好な関係を築く
● 複数の取引先・収入源を確保しておく
個人事業主は個人の実力によってリターンは大きくなりますが、常にリスクがあるため、その点をよく考えて事業を進めるようにしましょう。
リスク回避のために準備できること
個人事業主がリスクを回避するために大切なことは、計画的な資金繰りを行うことです。
資金繰りが悪化してしまうと、廃業の恐れがあります。日本政策金融公庫や信用金庫などの金融機関と関係を構築し、場合によってはクラウドファンディングを検討するなど、複数の資金調達方法を準備しておきましょう。
また、事業や販路拡大のため、業界内外での人脈の構築や情報収集も重要です。
そのほか、老後の生活を考えると、国民年金に上乗せして加入できる「国民年金基金」や廃業時・退職時の生活資金を積み立てられる「小規模企業共済」への加入も検討すると良いでしょう。
個人事業主も売り上げに関連する支出は経費計上できる
個人事業主は、事業に関する支出の経費計上が可能です。必要経費を計上すると、所得税が課される所得(課税所得)を少なくでき、節税につながります。
以下では、所得税の計算で計上できる必要経費の種類や、必要経費の計算で役立つ「家事按分」を解説します。
必要経費で計上できる金額
必要経費で計上できる金額は、下記の2つです。
| ●総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 |
| ●その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 |
「総収入金額に対応する売上原価」は、商品の仕入れにかかった費用や製造にかかった費用のことです。また、仕入れや製造に伴う費用や販売費、一般管理費など事業で必要な費用も経費として認められます。
具体的には、商品の製造に必要な材料費や部品費、仕事で利用するパソコンやプリンターの購入費用、取引先を訪問するための交通費、出張に伴う費用などが経費に計上できる金額です。事業に必要な費用は業種・業態で違ってきます。
必要経費で計上できる金額がわからないときは、国税庁の「タックスアンサー」も参考にしてみましょう。
自宅を事務所とするときは家事按分を考慮する
個人事業主が自宅を事務所とする場合、光熱費や家賃の一部も必要経費として計上できます。ただし、必要経費として計上できるのは「事業で必要な費用」です。生活で利用している電気やガスなどの料金は区別しなければなりません。
家事按分は、光熱費や家賃など、生活費と必要経費が一体となっている費用を一定のルールの基で振り分けることを指します。
家事按分には一定の要件がありますが、光熱費や家賃などを必要経費に計上できるメリットがあります。自宅を事務所とするときは、必要経費を計上する際に家事按分を考慮しましょう。
面倒な書類づくりはクラウド型経費精算サービスや会計ソフトがあると便利
個人事業主にはメリットだけではなく、デメリットがあることも事実です。確定申告時には申告に必要な書類を自身で作成する必要があり、作成作業を面倒に感じる方も多いでしょう。
しかし、クラウド型経費精算サービスや会計ソフトなどを導入しておけば、そういった作業もスムーズに行うことができます。
また、会計ソフトによっては、クレジットカードと連携させることが可能です。
連携させるとクレジットカードの利用履歴が会計ソフトに自動で取り込まれ、そのデータをソフト内で処理してくれます。経費の支払いをクレジットカードにまとめたうえで、会計ソフトと連携させれば、経費処理の手間を大きく減らせます。
そのため、会計ソフトを利用する際はクレジットカードも一緒に活用することをおすすめします。
個人事業主におすすめのクレジットカード

個人事業主の方がクレジットカードを作る場合は、ビジネスに利用できるサービスが数多く付帯しているビジネスカードがおすすめです。
ビジネスカードがあれば、家計や趣味用のクレジットカードとはご利用明細が混ざらずに済みます。また、ビジネスカードと会計ソフトを連携して自動記帳していれば、確定申告時の仕分けもほぼ自動になるため、経理の手間が大幅に軽減します。
以下では個人事業主の方におすすめのセゾンカードとして、セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードと、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの2枚を紹介します。
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
| 年会費 | 無料 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 海外利用で2倍(※1)(※2) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay™、QUICPay™(クイックペイ) |
| 追加カード | 年会費無料で9枚まで発行可能 |
| 主な特典 | ・「かんたんクラウド(MJS)」月額利用料 2ヵ月無料ご優待 ・4倍ポイントサービス ・セゾンビジネスサポートローン ・福利厚生サービス「セゾンフクリコ」 ・エクスプレス予約サービス(プラスEX会員) ・エックスサーバーご優待 |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、年会費無料で利用できるビジネスカードです。
申込時は決算書や登記簿謄本の提出が不要なため、起業して間もない会社や個人事業主の方でも気軽に申し込めます。
また、一時的な増額申請に対応しているため、高額になりやすい税金も無理なく支払えます。支払額に対してはポイントが還元され、節約や経費削減につながります。
このほか、会計・給与計算のクラウドサービス「かんたんクラウド(MJS)」の月額利用料2ヵ月無料という特典が付帯しているのも魅力です。本サービスには自動仕訳作成機能が搭載されており、経理業務の効率化を行えます。
さらに、特定のビジネス関連のサービスでカードを利用すると、通常のポイント還元率0.5%(※1)(※3)の4倍である2%のポイント還元が受けられます。以下は、ポイント4倍サービスの対象になるサービスの一例です。
● アマゾンウェブサービス(AWS)
● エックスサーバー
● お名前.com
● かんたんクラウド(MJS)
● クラウドワークス
● サイボウズ
● マネーフォワード クラウド
● モノタロウ(事業者向けサイトのみ対象)
● Yahoo!ビジネスサービス
日常生活で役に立つセゾンカード会員限定の特典も充実しており、例えば、毎週木曜日に全国のTOHOシネマズでお好きな映画を1,200円(税込)で鑑賞いただける「セゾンの木曜日」があります。
セゾンカードのスマートフォンアプリ「セゾンPortal」からクーポンを取得いただき、WEB(インターネットチケット販売“vit®”)または劇場でのチケット購入時にクーポンをご利用いただくことで特別料金で映画鑑賞が可能です。
(※1)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
(※2)小数点以下は繰り上げになります。
(※3)ほかカードにてSAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)へご入会いただいている方は本サービスの対象外となります。
>>詳細はこちら
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
| 年会費 | 初年度無料、2年目以降は33,000円(税込) |
|---|---|
| ポイント還元率 | 海外利用で2倍(※1)(※2) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay™、QUICPay |
| 追加カード | 年会費3,300円/枚(税込)で9枚まで発行可能 |
| 主な特典 | ・コンシェルジュ・サービス ・プライオリティ・パスに年会費無料で登録可能 ・セゾン弁護士紹介サービス ・法人向け顧問弁護士サービス「リーガルプロテクト」ご優待 ・各種のビジネスサポート特典 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、手厚いビジネス向けの特典が付帯したプラチナビジネスカードです。
プラチナカードならではの特典として、専任スタッフが24時間365日対応(※3)する「コンシェルジュ・サービス」が利用でき、ビジネスでもプライベートでもサポートが受けられます。
世界中の空港ラウンジを利用できる「プライオリティ・パス(通常年会費469米ドル/プレステージ会員)」には年会費無料で登録でき、フライト前の待ち時間もゆったり過ごせます。
ビジネス向けの特典としては「セゾン弁護士紹介サービス」が利用でき、弁護士に相談したいときには第一東京弁護士会を通じて弁護士の紹介を受けることが可能です。
ほかにも、ビジネスに役立つさまざまなサービスを優待価格で利用できる「ビジネス・アドバンテージ」も付帯しています。
さらに、日常生活で役に立つ特典も充実しており、「セゾンの木曜日」の利用で映画がお得に楽しめたり、「セゾンフクリコ」が入会費・年会費無料で利用できたりします。
「セゾンフクリコ」とは、全国25,000以上の施設を最大66%OFFで使える優待割引サービスです。特別優待として映画鑑賞券が1,300円(税込)からご購入可能です(お一人様20枚/年まで)。
ほかにも、レジャーやグルメ、トラベルなどさまざまな優待割引を、専用サイトからいつでもご利用いただけます。
(※1)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
(※2)小数点以下は繰り上げになります。
(※3)「カードのご利用に関するお問い合わせ」のみ、10:00〜17:00の対応とさせていただきます。
>>詳細はこちら
個人事業主に関するよくある質問
ここからは、個人事業主に関するよくある質問と回答を紹介します。
Q1 個人事業主になれない人はいる?
個人事業主には、税務署に開業届を提出するだけでなれます。ただし、個人事業主の事業を副業として行う場合、本業の規則によっては個人事業主になれない場合もあります。
例えば、副業を禁止する企業で働いている会社員や公務員は、個人事業主としての事業を副業で行えません。
Q2 個人事業主が納める税金の種類は?
個人事業主が納めなければならない主な税金としては、所得税や消費税、住民税、個人事業税が挙げられます。
節税をするには、「控除を利用する」「青色申告を行う」などの工夫が必要です。
Q3 個人事業主は社会保険に加入できる?
一般的に、社会保険とは「健康保険」「厚生年金」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つの保険を指します。
このうち、健康保険と厚生年金、雇用保険、労災保険は会社員に向けた制度なので、個人事業主は加入することができません。
まとめ

個人事業主は税務署に開業届を提出するだけで誰でも簡単になることができますが、個人事業主として生計を立てていけるかどうかは人それぞれです。
働き方や働く時間・曜日などがすべて自由であり、報酬の取り決めも取引相手との契約次第なので、好きなときしか働いていないにもかかわらず、会社員のときより収入が多いこともあり得ます。
ただし、実力次第の世界でもあり、仕事がとれずに路頭に迷ってしまう可能性もあるため、個人事業主として働くかどうかを事前によく考えたうえで決断しなければなりません。
個人事業主として働くうえでは、ビジネス向きのサービスが数多く付帯しているビジネスカードがあると便利です。
クレディセゾンでもセゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードやセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードなどのビジネスカードを取り扱っているので、ビジネスカードの発行を検討している場合はぜひご検討ください。
(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
(※)Apple、Appleのロゴ、Apple Payは、Apple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。TM and © 2025 Apple Inc. All rights reserved.
(※)Google Pay 、Google Pay ロゴ、Google Play 、Google ロゴ、Android はGoogle LLC の商標です。
(※)Google Pay は、おサイフケータイ(R) アプリ(6.1.5以上)対応かつAndroid5.0以上のデバイスで利用できます。
(※)「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
(※)「QUICPay」「QUICPay+」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。
この記事を監修した人

【保有資格】
弁護士、宅地建物取引士