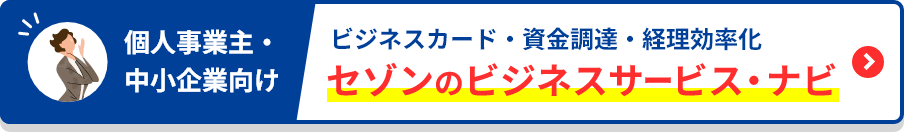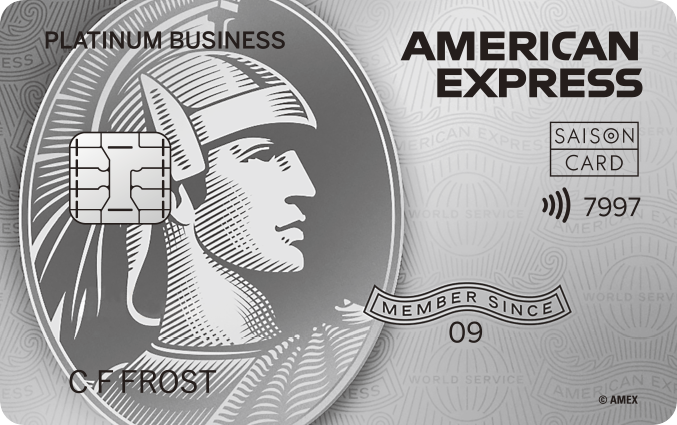個人事業主が法人化するメリット・デメリットは?最適なタイミングや設立方法を解説
また、法人設立には準備が必要となるため、設立までの流れも理解しておくと良いでしょう。
本記事では、個人事業主が法人化するメリット・デメリットや法人化のタイミング、設立方法などを解説します。

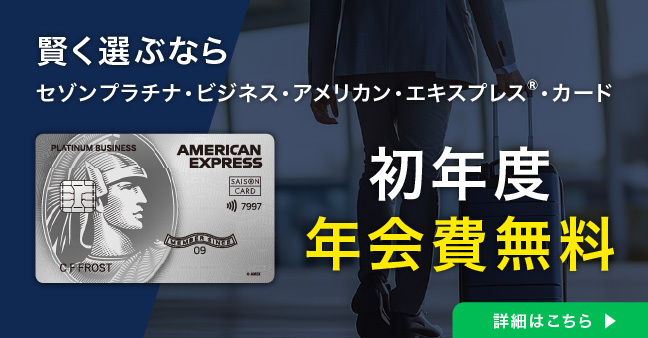
個人事業主の法人化とは
個人事業主の法人化とは、個人事業を廃業して新たに法人を設立することで、法人成りとも呼ばれます。
法人化には社会的信用が高くなる、節税効果が見込めるなどのメリットがある一方、社会保険への加入が必要になるなど、個人事業主では発生しなかった手間や費用が生じます。
個人事業主と法人はどちらが良いということはなく、法人化したほうが良いかはケースバイケースのため、違いやそれぞれのメリット・デメリットを把握することが大切です。
個人事業主と法人の違い
個人事業主と法人の主な違いは以下のとおりです。
| 個人事業主 | 法人 | |
|---|---|---|
| 設立費用 | なし | 資本金によって相場が異なる |
| 資本の引き出し | 自由 | 用途を明確にする必要がある |
|
納める国税
|
所得税 | 法人税 |
| 消費税 | 消費税 | |
| 復興特別所得税 | 法人特別所得税 | |
|
納める地方税
|
個人住民税 | 法人住民税 |
| 地方消費税 | 地方消費税 | |
| 個人事業税 | 法人事業税 | |
| 責任の範囲 | 無限責任 | 有限責任 |
法人の設立には設立費用がかかり、その相場は会社の形態や資本金の額によって異なります。
個人事業主は、個人のお金と事業のお金を明確に分けることが義務付けられていませんが、法人は会社のお金を資本金として個人のお金と分けて管理する必要があり、資本金を利用する場合は用途を明確にする必要があります。
法人とは「法人格」とも呼ばれる法律上の人としての資格です。つまり、法人設立とは法律上の人が生まれるもので、その資格に対する税金が新たに発生します。
法人は法人税、法人住民税、法人事業税に加えて、消費税・地方消費税を納める必要があります。
事業における責任の所在も法人と個人事業主で異なり、個人事業主は事業における全責任を負う無限責任です。
しかし、法人の責任は、法人格と経営者個人の責任を切り離して考えることになっており、法人の財産の範囲内でのみ責任を負う有限責任となっています。
個人事業主が法人化を判断するポイント

法人化を判断するポイントは以下のとおりです。
● 売上増加による所得税の負担増
● 事業拡大における金融機関からの融資が必要
● 新規事業で共同出資者や従業員を確保する
● 個人事業では許認可が下りない事業を開始する
個人事業主が法人化を検討するタイミングで最も多いのが売上の増加です。先に説明したように売上が増加すると所得税が増えることから、節税対策として法人化を考えます。
また、将来的な事業計画を立てるうえで法人化を推進することも珍しくありません。事業拡大における設備投資や人材確保などで資金が必要な場合は、銀行などの金融機関の融資が必要です。
しかし、金融機関は個人事業者への融資に慎重なケースも多く、ここでも法人が有利です。
新規事業を開始するにあたって共同出資者や知識のある従業員を雇用するためにも、個人事業よりも法人のほうが有利な傾向が見られます。
個人事業主が法人化するメリット
個人事業主が法人化するメリットは5つ挙げられます。
● 金融機関や取引先からの社会的信用が高くなる
● 所得税率が法人税率より高くなると節税効果が高まる
● 社会保険に加入できる
● 交際費以外の経費計上範囲が広くなる
● 決算の時期がずらせる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
金融機関や取引先からの社会的信用が高くなる
法人化することで社会的信用が増し、融資を受けやすくなる場合があります。
法人が個人事業主よりも金融機関や取引先からの信頼を得やすくなるのは以下の理由が考えられます。
● 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に情報が記載されている
● 個人ではなく組織として見られる
● 事業の継続が期待できる
法人を設立する際には法人登記申請が必要であり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には登記申請をした法人の情報が掲載されています。法務局に申請をすれば誰でも閲覧可能です。公的な機関に情報が記載されていることは、取引先からの信頼を得る要素の1つになります。
また、法人化すれば少数で行っている事業であっても、個人ではなく組織として見られやすいことや、個人事業主とは異なり設立にも廃業にも複雑な手続きが必要なことから、継続が期待できる点も信頼につながる可能性があります。
所得税率が法人税率より高くなると節税効果が高まる
個人事業主が支払う所得税は累進課税となっており、所得が増えるほど税率があがる仕組みです。一方で、法人が払う法人税の税率は基本的に一律となっています。
つまり、収入が増加し所得税率が上昇すれば、法人税率と逆転するため、税負担が軽くなる場合があります。
それでは、具体的に法人化を検討する所得について考えるために所得税率と法人税率を比較していきましょう。
所得税率
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
法人税率(資本金1億円以下、過去3年の年平均所得金額が15億円以下)
| 課税所得金額 | 法人税 |
|---|---|
| 年800万円以下の部分 | 15% |
| 年800万円を超える部分 | 23.2% |
上記の表を参考に自身の所得に当てはめて所得税と法人税を計算すれば、節税効果を概算できます。
法人化にはさまざまな諸経費がかかり、税務作業を中心とした事務作業も複雑化するため手間もかかるので、節税効果が法人化で想定される手間やコストと比較して割に合わない場合があります。
法人化を検討するなら節税効果だけでなく、法人化にかかる諸経費や手間も考えた上で、慎重に検討する必要があります。
社会保険に加入できる
法人化すると事業主、従業員を含めて社会保険に加入します。
個人事業主であっても従業員が5人以上の場合は従業員を社会保険に加入させる義務が発生しますが、事業主自身は法人化しなければ社会保険に加入できません。
社会保険に加入すると保険料は高くなりますが、国民年金から厚生年金に切り替わることで老後の年金の増加が期待できます。
また、従業員を社会保険に加入させることによって、社会保障が手厚くなり、事業の拡大に伴う人材の確保にも有利に働くことが期待できます。
交際費以外の経費計上範囲が広くなる
法人化すると社員への福利厚生や賞与・退職金など、個人事業主では経費として認められにくい内容も経費として計上できるようになります。
基本的に経費の計上範囲は個人事業主よりも法人のほうが有利ですが、交際費に限っては個人のほうが有利になる場合があります。交際費とは事業を行ううえで必要な飲食、接待、贈答などの経費のことです。
資本金1億円以下の法人の場合は、年間で800万円までは交際費として損金処理が可能であり、1億円を超える場合は、交際費に含まれる飲食代に限り半分(50%)が経費に計上できます。
一方で、個人事業主は業種によっては認められない交際費もありますが、経費の額に関して制限はなく、交際費の範囲も飲食代に限りません。
決算の時期がずらせる
個人事業主の決算日は12月31日となっており、原則、毎年3月15日までに確定申告をして税金を納める必要があります。
法人化すると決算期は、会社の都合に合わせて自由に決められます。
事業の繁忙期が年末年始と重なる場合は決算期をずらすことも可能です。
個人事業主が法人化するデメリット
個人事業主が法人化するとメリットが生まれますが、なかにはデメリットも存在します。
特に法人は社会的な信用が得られる代わりに、責任も発生することを忘れてはなりません。法人化のデメリットは以下のとおりです。
● 法人化に伴う費用が発生する
● 赤字でも法人住民税の支払いが必要になる
● 社会保険の加入が義務付けられる
● 事務手続きの負担が高まる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
法人化に伴う費用が発生する
法人化には初期費用が必要です。会社の形態によって必要な費用は異なりますが、例えば、株式会社を設立する場合は以下のような費用がかかります。
● 印紙代:4万円
● 定款認証の手数料:5万円
● 定款謄本証明書:1枚250円
● 登録免許税:払込資本金の0.7%(最低15万円)
● 株式払込事務取扱手数料:払込資本金の0.25%
● 司法書士などに支払う費用:内容により変動
法人化を検討する場合、事前に必要な費用を確認し、準備しておくことをおすすめします。
赤字でも法人住民税の支払いが必要になる
個人事業主の税金は所得に対して発生するものであるため、利益がなければ税金を納める必要はありません。
一方で、法人は所得の有無にかかわらず、赤字の場合であっても法人住民税がかかります。
赤字であっても税金の支払いが必要になる理由は、法人住民税の均等割が資本金や従業員の数に応じて課税されるからです。
社会保険の加入が義務付けられる
個人事業主が法人化すると自身と従業員を含めて社会保険の加入が義務付けられます。
従業員にかかる社会保険料は、会社と従業員で折半して保険料を納める必要があるため、加入義務のない個人事業主と比較して費用がかさみやすくなります。
ただし、加入せずに放置すると年金事務所から加入申請が届き、立入検査の警告・過去に遡った保険料の徴収、罰則の適用も考えられるので、法人化する場合は必ず加入するようにしましょう。
事務手続きの負担が高まる
法人の税務処理は、大きく分けて決算書の作成、法人税の申告、決算書類の保存があります。1人で行う場合は、事務手続きが複雑で負担が大きくなります。
そのため、法人の税務処理は税理士に依頼するのが一般的ですが、依頼料などのコストも考える必要があります。
個人事業主が法人化を行う手順

個人事業主が法人化を決意した場合の手順をまとめます。
①法人設立の準備
②定款作成・認証
③設立登記
④各種申請
それぞれ詳しく解説します。
①法人設立の準備
法人を設立する際は、事前の準備が大切です。特に、以下の項目は重要となるため、しっかりと準備しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社形態 | 株式会社と合同会社のどちらを設立するか決定します。株式会社は最も一般的な形態で、社会的な信頼性が高い傾向があります。一方、合同会社は設立費用が安く、経営の自由度も高いことが特徴です。 |
| 商号(会社名)・本店住所 | 会社名を決定し、ゴム印と実印・銀行印を作成しましょう。 |
| 目的(事業の内容) | 現在の業務だけでなく、将来参入したい業務についても含めると、のちの修正が必要なく効率的です。ただし、多すぎると金融機関からの印象があまり良くない傾向があります。 |
| 資本金 | 1円でも設立可能ですが、会社の信用を考慮すると100万円以上が望ましいです。 |
| 決済月 | 一般的には3月決算が多いですが、税理士の繫忙期や事業の閑散期などを考慮する必要があります。特に、閑散期を決算月に設定すると資金繰りが苦しくなる可能性があるため注意しましょう。 |
| 法人の銀行口座開設 | 法人口座は、個人のように容易に開設できないことが多いため、事前によく確認しましょう。 |
そのほかに定款の作成も必要です。準備は自身で行っても問題ありませんが、悩むようなら税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
②定款作成・認証
法人設立に必要な書類・定款を準備します。主に必要な書類は代表者などの印鑑証明書、法人の実印、定款、就任承諾書、発起人決議書などです。
また、株式会社を設立する場合は、定款を公証役場で認証してもらう手続きが必要です。
③設立登記
書類などの準備が整ったあとは、それらを持って法務局で設立登記を申請します。登記には登録免許税が必要で、資本金の0.7%(最低15万円)を支払います。
④各種申請
無事に法人が設立されたら各種申請を行います。申請は税金関係、社会保険関係、労働関係などで、それぞれ税務署、自治体、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークで行います。
現在、「法人設立ワンストップサービス」が開始されており、国税、地方税、年金、雇用・労働保険などの手続きがオンラインでできるようになりました。将来的には法務局の登記についてもオンライン化される予定です。
法人設立の手続きは専門家に依頼すべきか?
法人設立の手続きは専門家に依頼するケースが多いですが、自身で行っても問題ありません。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、事前に把握したうえで選択しましょう。
| 手段 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 専門家に依頼 | ・正確な内容で手続きできる ・手続きの手間が少ない |
・依頼に費用がかかる ・専門家を探す手間がある |
| 自身で行う | ・費用を抑えられる ・会社設立までの知識が身に付く |
・不備が生じる可能性がある ・手続きに手間がかかる |
また、法人設立の相談は、各自治体の相談窓口や商工会議所などでも行っています。
相談自体は無料でできるケースが多いため、疑問や悩みがある場合は一度相談してみましょう。
法人化するならビジネスカードの発行も検討しよう!
個人事業主が法人化するならビジネスカードの発行も検討しましょう。ビジネスカードを利用するメリットは下記のとおりです。
● 経費精算がしやすくなる
● 社員カードをつくれば利用経費を一括で管理できる
● 経費の支払いに対してもポイントが付く
法人の経費をすべてビジネスカードで支払うようにすれば経費精算がしやすくなり、従業員に対しても社員カードをつくれるので、利用経費も一括で管理できるようになります。経費の支払いに対してもポイントが付くので経費の削減につながります。
また、ビジネスカードはカードごとに付帯サービスも異なるため、事業に役立つサービスを提供しているカードを選ぶことが重要です。
クレディセゾンのビジネスカードは付帯サービスが充実しており、発行の際には登記簿謄本や決算書の提出が不要です。個人与信で審査できることから、個人事業主の方や、まだスタートアップして間もない企業の経営者の方にもおすすめです。
今回は、法人化を検討している個人事業主の方と法人化したばかりの経営者に適しているクレディセゾンのビジネスカードを紹介します。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
| 年会費 | ・初年度無料 ・通常年会費33,000円(税込) |
|---|---|
| 国際ブランド | American Express |
| 入会資格 | 個人事業主・経営者をはじめ、安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(学生、未成年を除く) |
| 主なサービス | ・SAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)への登録可能 ・国内旅行傷害保険 ・海外旅行傷害保険(※) ・国内空港ラウンジの無料利用 ・「デジタル会員証(プライオリティ・パス アプリ)」に年会費無料でお申し込み可能(通常年会費 469米ドル/プレステージプラン) ・コンシェルジュ・サービス ・ビジネス・アドバンテージ ・カード不正利用補償(オンライン・プロテクション) |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| 追加機能 | 社員用追加カード:年会費3,300円(税込)(9枚まで)/ETCカード(5枚まで) |
| 電子マネー | Apple Pay/Google Pay™/QUICPay™(クイックペイ) |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは初年度年会費無料、2年目以降は年会費33,000円(税込)のビジネスカードです。
審査は代表者の個人与信、法人口座を引き落とし口座に設定できることから、個人事業主、企業の経営者を対象に広く利用しやすいビジネスカードとなっています。
社員用カードは年会費3,300円(税込)で本会員と同様の機能を有した追加カードを9枚まで発行可能です。
付帯サービスでは、さまざまな経費の支払いが優待価格になるビジネス・アドバンテージや、ベリーベスト法律事務所が提供する法人向け顧問弁護士サービス「リーガルプロテクト」の優待などがあります。交通系ICカードの履歴を読み込むこともできるので、交通費の経費計上も簡単です。
ほかにも、世界に広がる1,700ヵ所以上の空港ラウンジを利用できる「デジタル会員証(プライオリティ・パス アプリ)」に年会費無料でお申し込みいただけます(通常年会費 469米ドル/プレステージプラン)。
仕事で海外出張や飛行機をよく利用する方にもおすすめの1枚です。
(※)航空券代や宿泊費などの支払いに本カードを利用した場合に適用されます。
>>詳細はこちら
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
| 年会費 | 無料 |
|---|---|
| 国際ブランド | American Express |
| 入会資格 | 個人事業主またはフリーランス、経営者の方(高校生を除く) |
| 主なサービス | ・4倍ポイントサービス(※) ・エックスサーバーご優待 ・カード不正利用補償(オンライン・プロテクション) ・かんたんクラウド(MJS)の2ヵ月無料優待 |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| 追加機能 | 社員用追加カード(9枚まで)/ETCカード(5枚まで) |
| 電子マネー | Apple Pay/Google Pay™/QUICPay |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、個人事業主・フリーランス・経営者向けに発行されている年会費無料で利用できるビジネスカードです。
付帯サービスは、インターネット上の不正利用による損害を保証するオンライン・プロテクションに加えて、会計・給与クラウドサービスのかんたんクラウド(MJS)が2ヵ月無料で利用可能です。
引き落とし口座は、個人名義口座と法人名義口座より選べるため、法人名義口座に設定すれば経費精算の利便性が向上します。
法人で発生する高額な経費の支払いや、納税をビジネスカードで行う場合、利用限度額が不足することも考えられますが、審査結果に応じた一時的な限度額の増額によって対応可能です。
本会員と同様の機能を有した社員用追加カードは9枚まで発行できるので、発生した経費の一括管理が可能です。
また、支払いには有効期限のない永久不滅ポイントが貯まるので、貯め続けられることから期限を気にせずに着実に経費を節約できます。
マネーフォワード クラウド、モノタロウ(事業者向けサイトのみ対象)などのビジネスに役立つサービスを提供している特定加盟店を利用すると、永久不滅ポイントが最大2%相当還元(※)されます。
(※)通常の4倍、1,000円(税込)ごとに4ポイント還元します。また、他のカードでSAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)にご加入いただいている場合、本特典は対象外となります。
>>詳細はこちら
まとめ
個人事業主が法人化すると節税効果だけでなく、社会的信用性が高まるなどの効果が期待できます。
また、信用性が高まることで従業員を雇用しやすくなり、金融機関からの融資も受けやすくなります。
個人事業主であっても一定以上の売上が見込まれるようになったら、法人化の検討をしてみると良いでしょう。
クレディセゾンのビジネスカードを利用してお得に法人設立を目指してください。
(※)「QUICPay」「QUICPay+」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。
(※)iPhone、Apple Watch、Apple Payは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。TM and © 2020 Apple Inc. All rights reserved.
(※)Google Pay 、Google Pay ロゴ、Google Play 、Google ロゴ、Android はGoogle LLC の商標です。
(※)Google Pay は、おサイフケータイ(R) アプリ(6.1.5以上)対応かつAndroid5.0以上のデバイスで利用できます。
(※)「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
この記事を監修した人

【保有資格】
CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー