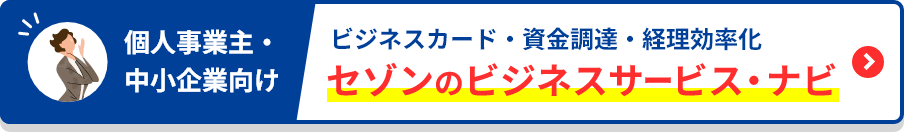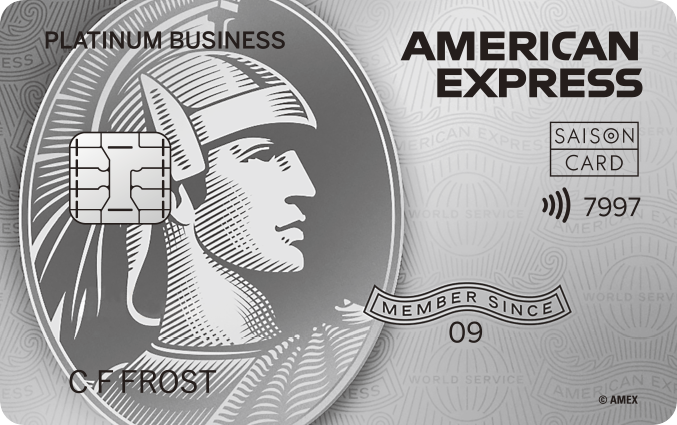事業計画書とは?項目別の書き方、作成するメリットや注意点について徹底解説
本記事では、事業計画書の概要や作成が必要な理由、書き方や作成時の注意点などについて解説します。書き方は項目別にわかりやすく紹介しているので、これから事業計画書を作る予定の方はぜひ参考にしてください。

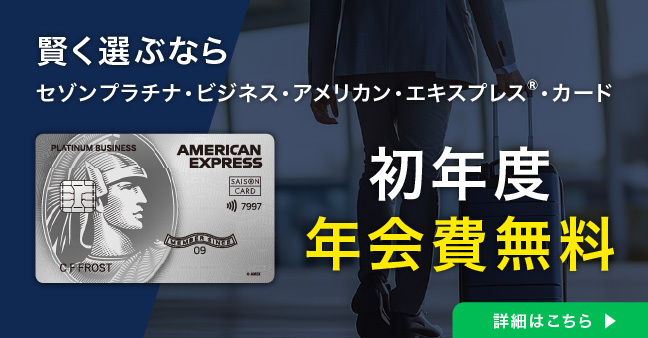
事業計画書とは事業内容や収益の見込みなどを具体的に示す計画書のこと
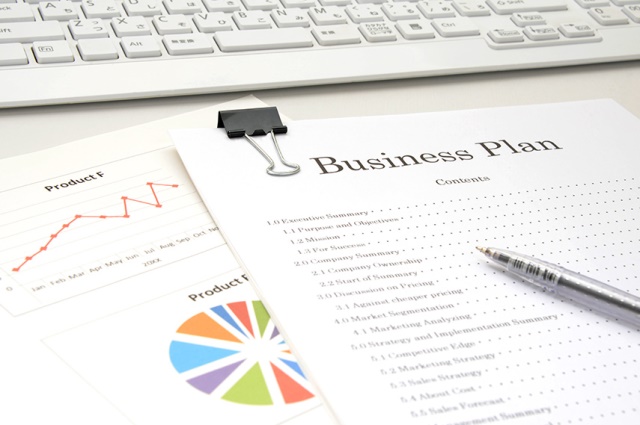
事業計画書とは、今後どのように事業を運営していくのかについてを、事業内容や企業の戦略、収益の見込みなどから具体的に示す計画書のことです。英語では”business plan”といいます。
事業計画書を作成すると、企業の存在意義を明確にして、企業を取り巻く環境や進むべき方向性を示すことができます。また、頭の中でイメージしている構想を具体的にまとめてみることで、本当に実現可能かどうかを客観的に判断する機会にもつながります。
事業計画書を作成する目的

事業計画書を作成する目的は、大きく分けて以下の2つです。
金融機関や投資家からの資金調達を実現させる目的
1つ目は、金融機関や投資家からの資金調達を実現させる目的です。
金融機関からの融資には返済義務があるので返済能力が低いとみなされる企業は融資を受けにくく、また成長性に期待できないような企業は投資家からの出資も受けにくいでしょう。
そこで、説得力のある事業計画や継続的な収益の見込みが記載された事業計画書を金融機関や投資家に示すことで、相手に「この企業に融資(出資)したい」と思わせることができます。
創業者自身の見取り図とする目的
2つ目は、創業者自身の見取り図とする目的です。
事業について最も理解していないといけないのは創業者なので、事業計画書は今後事業を運営していくうえでの見取り図としても役立ちます。
これまで事業についての理解が不足していた部分も事業計画書を作成することで明確になり、より計画的に事業を進められるようになるでしょう。
事業計画書に記載すべき10項目の書き方

ここでは、実際に事業計画書を作成する際に記載するべき10項目を紹介します。項目ごとに書き方のポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
1.創業者(創業メンバー)のプロフィール
1つ目は、創業者(創業メンバー)のプロフィールです。
「この人なら事業を成功させられそうだ」と思わせられるようなプロフィールを記載して、頼もしさを与えましょう。事業内容と結びつくような、個人の魅力や過去の経験を伝えることも大切です。
2.ビジョン・理念・目的
2つ目は、ビジョン・理念・目的です。
どのような気持ちで事業を始めて、今後どうなることを目指しているのか、また、事業の社会的存在意義についても記載しましょう。事業に対する本気度を伝えられるようにすることが大切です。
3.事業の概要
3つ目は、事業の概要です。
どのような顧客に、どのような商品またはサービスを、どうやって提供するのかを明確に記載しましょう。詳しくない人でもイメージしやすいように、端的に伝えることが大切です。
4.自社のサービスや商品の強みや特長
4つ目は、自社のサービスや商品の強み、特長です。
事業によっては、同業他社が存在する場合があります。その場合は、他社との差別化が必要です。
「他社とは違って、自社はこう」というように、自社の商品やサービスならではの強みや特長を積極的に伝えましょう。これらをはっきり浮かび上がらせるには、他社を熱心に研究する必要があります。
社会的意義や独自性があるな、と金融機関や投資家に興味を持ってもらえるようにすることが大切です。
5.市場環境、競合について
5つ目は、市場環境、競合についてです。
ターゲットとする顧客市場におけるニーズや事業に関連する政策の動向、競合他社についてなど、事業に影響を与えうるさまざまな要素について伝えましょう。
6.販売やマーケティング戦略
6つ目は、販売やマーケティング戦略です。
商品やサービスを顧客に知ってもらうには、適切な販売方法やマーケティング施策が必要です。どのようなルートで、どのようなチャネルで、どれくらいお金をかけて販売やマーケティングを行っていくのかを現実的に伝えましょう。
7.生産方法、仕入先について
7つ目は、生産方法、仕入先についてです。
すでに生産方法や仕入先が明確になっており、さらにそれらが確保できていると、それだけ事業に対する本気度を伝えられます。実際に商品やサービスを生み出すことができるかどうかを示すためにも、重要な項目です。
8.売上予測、売上計画
8つ目は、売上予測、売上計画です。
ここまで記載してきた項目から、売上予想や売上計画を導き出して記載します。どちらかいうと厳しめに、現実的な数値を記載するようにしましょう。
売上を記載する際は、それぞれの売上に対して「なぜこれだけの売上が生み出せると考えられるのか」という根拠が示せると、より信頼性が高まります。
9.予想損益計算書
9つ目は、予想損益計算書です。
創業1年目から数年間にかけての予想損益計算書を作成して記載します。先ほど売上予想を行いましたが、事業の運営にはコストもかかるので、費用予想も欠かせません。生産方法や仕入先が明確になっていると、よりスムーズに予想ができるかと思います。
そのほか、売上を伸ばすためにかける費用(広告宣伝費)などに関しての記載も必要ですが、その際売上に対してどれくらい成果が出ることが予想されるかを示せると、より具体的な損益計算書を完成させることができます。
10.開業資金
最後は、開業資金です。
事業を行うのにどれくらい資金が必要なのかを示します。創業~創業後半年間程度について、家賃や売上原価、人件費や光熱費など、発生すると考えられる費用をすべて記載しておきましょう。
あわせて手元にある自己資金を記載しておき、融資を希望する場合などは今回どれくらいの融資を受けたいのかという希望額を添えておくと、より具体的で担当者もイメージしやすくなるのでおすすめです。
事業計画書を作成する3つのメリット
事業計画書を作成することには、さまざまなメリットがあります。事業計画書を作成するメリットを、以下で説明します。
起業にあたってのイメージを整理できる
起業して事業を始めたいと考えている方の頭のなかには、事業に関するさまざまなイメージが浮かんでいることでしょう。
しかし、そのようなイメージはときに漠然とし過ぎていたり、現実的には不可能な要素が含まれていたりすることも往々にしてあるため、実際に起業する前に一度きちんと整理しておく必要があります。
事業計画書を作成して頭のなかのイメージを書面に起こすことで、事業内容や売上目標などが可視化できて整理しやすくなり、起業に向けてのステップを一歩進められます。
見える化することで事業計画が共有できる
事業の規模が小さい場合は、事業計画や事業の全体像を把握しているのは創業者だけでかまわないケースもありますが、事業規模が大きくなってくると関係者が多くなるため、創業者以外も全体像を把握している必要があります。
そういった際に事業計画書があり、事業の全体像が見える化されていれば、関係者が共通認識を持つことができて、視座・視線を揃えて事業運営ができます。
事業計画書を基にして事業を着実に前へ進めているという姿勢は、社外へアピールする材料になります。
資金調達がしやすくなる
事業展開や規模拡大のために資金調達をする必要がある場合、金融機関などの資金提供者に対して、事業内容や資金が必要な理由を説明しなければなりません。
その際、口頭で説明するよりも事業計画書を提出したうえで説明するほうが、より納得感のある説明が可能ですし、信憑性も高まります。
資金調達は事業を行ううえで大きなハードルのひとつです。事業計画書の作成によりそのハードルをクリアしやすくなることは、見逃せないメリットです。
事業計画書を作成する際の注意点
事業計画書に記載すべき項目は上述したとおりですが、必要な項目をただまとめただけでは、伝わりにくい書類になってしまいます。
事業計画書を作成する際にはどのような点に注意すべきかについて、以下で説明します。
要点を整理する
事業計画書に記載すべき項目のなかには、「自社のサービスや商品の強みや特徴」と「販売やマーケティング戦略」といったように、内容が若干重複する可能性もあります。
内容が重複してしまうとわかりにくくなってしまい、事業計画書としての要点をつかみにくくなります。
事業計画書は読みやすさも重要な要素のひとつなので、要点がきちんと伝えられるような構成にしましょう。
細かい内容も記載する
事業計画書には、事業に関するありとあらゆることを記載すべきという意識を持つことが重要です。
創業者や創業メンバーのプロフィールなどは、一見すると事業の内容自体に直接関係しないようなものに思われますが、創業者のバックボーンが事業の方向性に大きく関わっているようなことがあると、事業に対する思い入れがより伝わりやすくなります。
また、ポジティブなことだけでなく現在認識している問題点や課題なども記載することによって、事業の状況や全体像をきちんと把握できていることを示せますし、すべてを開示しようとしているというこちらの姿勢・誠意も伝えられます。
ただし、要点が整理されていないと、情報量が多くてわかりにくい事業計画書になってしまうので注意しましょう。
数値を入れるときは根拠も忘れずに記載する
売上予想や売上計画などでは、数値を用いて説明する必要があります。
ビジョンや理念・目的などに関しては、創業者の想いがベースになっていても問題ありませんが、数値を用いる必要がある部分に関しては、その根拠や実現可能性などをベースにしなくてはいけません。
数値は金融機関が融資の判断を行う際の重要な要素なので、厳しくチェックされる可能性が高いことを、念頭に置きましょう。
競合の内容についても記載する
事業を行ううえで競合の存在は無視できない要素なので、事業計画書には競合について触れる部分も作っておくと良いでしょう。
競合の事業モデルや販売戦略などが、自社の戦略や収益目標に活用できることもあります。その場合は、競合のデータを用いて説明することで、より説得力が増すという効果も期待できるかもしれません。
特に創業して間もない会社の場合、自社の商品やサービスのことばかりを考えてしまいがちですが、競合との違いや市場における両者の立ち位置などを把握できていれば、俯瞰で物事を把握できているということのアピールにもなります。
事業計画書のテンプレートはある?
事業計画書の内容は各企業で異なるため、決まったテンプレートはありません。必要な項目さえ盛り込まれていれば、自由なフォーマットで作成できます。
0から事業計画書を作成するのが手間に感じる場合は、書式を日本政策金融公庫のホームページからダウンロードする、または専用ソフトを利用するのがおすすめです。以下では、それぞれの作成方法を解説します。
日本政策金融公庫のホームページからダウンロード
日本政策金融公庫のホームページからは、事業計画書の書式をダウンロードできます。書式に沿って必要な情報を記入していけば、事業計画書の作成が初めての方でもわかりやすい書類を作成できるでしょう。
ただし、インターネット上からダウンロードできる書式には、必要最低限の項目しか盛り込まれていません。実際に作成する際は、自社の状況に合わせて必要な事項を追加しながら作成していきましょう。
専用ソフトを利用する
少ない手間で事業計画書を作成したい方には、書類作成専用ソフトの利用がおすすめです。専用ソフトには事業計画書の作成に役立つさまざまなツールが搭載されており、効率良く作成作業を進められます。
また、ソフトの種類によっては事業計画書以外の書類も作成可能です。ただし、ほとんどのソフトは有料なので、コストが負担にならないかどうかも考えたうえで導入しましょう。
事業計画書を作成する方におすすめのビジネスカード
事業を始めたばかりの段階では、事業計画書をはじめとしたさまざまな書類を作成しながら業務に取り組まなければいけません。場合によっては書類作成に多くの手間がかかってしまい、事業の中心となる業務に着手できる時間が確保できない場合もあるでしょう。
このような悩みの解消には、ビジネスに関する特典が付帯したビジネスカードが役立ちます。ビジネスカードによっては業務の効率化に役立つ特典が数多く付帯しており、上手に活用することでスムーズに仕事に取り組めるようになります。
以下では、ビジネスに役立つ特典が付帯するおすすめのビジネスカードを2枚紹介します。
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、年会費無料で保有ができるビジネスカードです。事業を始めたばかりだと経済的な負担が気になりやすいですが、本カードならコストを気にせずに発行できます。
本カードのほか、最大9枚まで発行できる追加カードも年会費無料です。追加カードの利用分は本カードの利用分と合わせた一括支払いとなるため、従業員に持たせれば経費精算の手間を減らせます。
>>詳細はこちら
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
特典内容を重視する方には、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードがおすすめです。ビジネスの効率化に活用できる特典からプライベートで役立つものまで、プラチナカードならではの充実した数々の特典を利用できます。
年会費は初年度無料、2年目以降は33,000円(税込)です。最初の1年はコストを気にせず利用できるため、できるだけ年会費をかけずにプラチナカードを保有したいという方にもおすすめです。
>>詳細はこちら
事業計画書についてのまとめ

本記事では、事業計画書について詳しく解説しました。創業をする際、金融機関からの融資や投資家からの出資をしてもらう必要が出てきた際には、事業計画書の作成が必要です。事業計画書の品質が投融資の可否を左右する可能性もあるので、より具体的で説得力のある事業計画書を作成するようにしましょう。
また、創業したあとは、経費の支払いなどを効率的に行うためにビジネスカードが1枚あると便利です。
セゾンカード発行の「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」や「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」は、経費精算をはじめとした業務の効率化に役立つ特典が数多く付帯しています。登記簿謄本・決算書不要で申し込めるので、ぜひ発行をご検討ください。
この記事を監修した人

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士