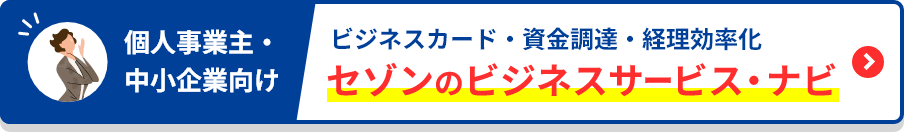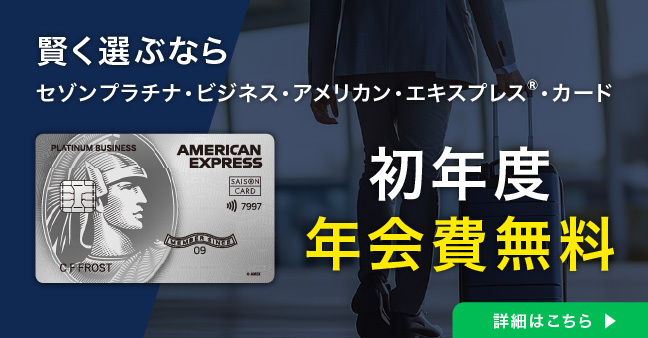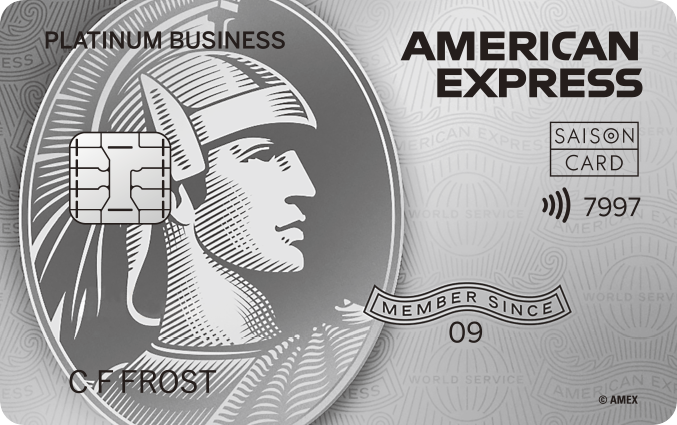消費税の中間申告、中間納付とは?仕訳や計算方法、支払う時期を解説
しかし、個人事業主のなかには、「中間申告・中間納付が必要になるらしいけれど、仕組みがよくわからない」「中間申告・中間納付に必要な手続きを知りたい」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
本記事では、個人事業主に向けて、中間申告の概要や仕組みを解説しつつ、中間納付の税額の算出方法やスムーズに納付する方法を紹介します。
消費税の基本的な仕組み
消費税とは、一般に広く課される間接税であり、標準税率は10%、軽減税率は8%(※)となります。なお、消費税を負担するのは消費者ですが、申告・納付するのは事業者です。
さまざまな商品は、「原材料を作る業者」「完成品を作る業者」「卸売業者」「小売業者」といった流れを通じて、最終的に消費者に届きます。
そのため、「取引のたびに消費税がかかり、流通の過程で何度も税金が積み重なり、消費者に近い業者ほど負担が重くなる」と誤解されるケースもあります。
実際には、「課税売上にかかる消費税」から「仕入れにかかった消費税」を差し引ける「仕入税額控除」という仕組みが存在するため、消費税の累積を解消することが可能であることを理解しておきましょう。
(※)「酒類・外食を除く飲食料品」および「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」が対象
消費税の中間申告・中間納付とは

消費税を納付する義務は、法人だけでなく個人事業主に対しても課せられます。個人事業主の場合、原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えると消費税を納付しなければなりません。
原則として個人事業主に対する消費税の課税期間は1月1日から12月31日であり、年に1回だけ申告・納付を行うことになります。ただし、前年の確定消費税額(※)によっては年の途中に申告・納税をする必要がある点にご留意ください。
なお、年の途中で申告・納税する仕組みは「中間申告」「中間納付」と呼ばれます。
中間申告・中間納付は、消費税の納付を年1回ではなく複数回に分けることにより、納税者の負担を軽減する目的で行われます。また、「納税者が消費税を納めやすくなれば、国が確実に税金を徴収できるようになり、財政が安定化する」という狙いもあります。
(※)確定申告によって確定した消費税の年税額のこと
消費税の中間申告・中間納付が必要なケース
前年の確定消費税額が48万円を超える場合は中間申告が必要です。ただし、ここでいう「消費税」には「地方消費税」を含みません。
スーパーなどでお買物をする際、軽減税率が適用される商品(食品)には8%、適用されない商品には10%の消費税がかかりますが、8%や10%は消費税(国税)と地方消費税(地方税)を合わせた税率です。
「地方消費税額=消費税額(国税) ÷ 78 × 22」であり、軽減税率8%のうち「6.24%が消費税、1.76%が地方消費税」、10%のうち「7.8%が消費税、2.2%が地方消費税」となります。
| 税率 | 消費税(国税)の場合 | 地方消費税の割合 |
|---|---|---|
| 税率8% | 6.24% | 1.76% |
| 税率10% | 7.8% | 2.2% |
なお、地方消費税は自治体に納付するのではなく、消費税と併せて国(税務署)に納付する必要があることにご留意ください。
中間申告による消費税額の算出方法とメリット・デメリット
中間納付税額の算出方法は「予定申告方式」と「仮決算方式」の2種類です。方式は自由に選択可能であり、事前の届出は必要ありません。
| 算出方法 | 特長 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
予定申告方式 |
前年の消費税額から月割計算で中間納付税額を算定する方法 | 申告書作成の手間がかからない | 業績によっては仮決算方式よりも中間納付税額が大きくなる可能性がある |
仮決算方式 |
中間申告の対象期間に対して仮決算を実施して、中間納付税額を算定する方法 | 業績によっては、中間納付税額を低減できる | 申告書作成の手間がかかり、計算した税がマイナスになっても中間申告の時点では還付を受けられない |
表中の「簡易課税制度」とは、「売上に係る消費税額」を基礎として「仕入れに係る消費税額」を算出することができる仕組みであり、経理処理の負担を軽減できます。
具体的には、「売上に係る消費税額」に「みなし仕入率(事業区分に応じ、40%~90%)」を乗じて算出した金額を「仕入れに係る消費税額」としたうえで、「売上に係る消費税額」から控除することが可能です。
なお、簡易課税制度の適用を受けられるのは「課税売上高5,000万円以下の事業者」であり、あらかじめ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
以下、各方法のメリット・デメリットを説明します。
予定申告方式
予定申告方式とは、前年の消費税額から月割計算で中間納付税額を算定する方式です。税務署から送付される納付書(中間納付税額が記載)を使って納税するため、申告書作成の手間がかからないことがメリットになります。
しかし、「去年の消費税額が大きかった」「今年の売上がものすごく減少した」「今年の仕入れが大幅に増加した」「今年になって多額の設備投資を実施した」場合、仮決算方式よりも中間納付税額が大きくなるデメリットがあります。
仮決算方式
仮決算方式とは、前年の消費税額に関係なく、中間申告の対象期間に対して仮決算を実施して中間納付税額を算定する方式です。
「去年の消費税額が大きかった」「今年の売上がものすごく減少した」「今年の仕入れが大幅に増加した」「今年になって多額の設備投資を実施した」場合、中間納付税額を低減できることがメリットです。
ただし、仮決算および申告書作成に手間がかかることがデメリットです。計算した税額がマイナスになっても、中間申告の時点では還付を受けることができません。
また、簡易課税制度が適用された場合、課税仕入に対する課税売上の割合によっては負担が増えるケースがある点にもご留意ください。
中間申告・中間納付の回数
中間申告・中間納付の回数および税額は、前年の確定消費税額によって下表のように変動します。
| 前年の確定消費税額 | 中間申告・中間納付の回数 | 中間納付税額 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 不要 | |
| 48万円超から400万円以下 | 年1回 | 前年の確定消費税額の12分の6の消費税額、およびその78分の22の地方消費税額 |
| 400万円超から4,800万円以下 | 年3回 | 前年の確定消費税額の12分の3の消費税額、およびその78分の22の地方消費税額 |
| 4,800万円超 | 年11回 | 前年の確定消費税額の12分の1の消費税額、およびその78分の22の地方消費税額 |
なお、消費税と併せて地方消費税も納付する必要があることを忘れないようにしましょう。
中間申告・中間納付の期限
中間申告・中間納付の期限は、回数によって異なります。1回・3回・11回、それぞれのケースでの期限は、国税庁のウェブサイトに記載されているので、納付回数の把握と併せて確認しておきましょう。
次の表は、令和8年分の中間申告・中間納付の期限をまとめたものです。
| 回数 | 納期等の区分 | 法定納期限 | 振替日 |
|---|---|---|---|
| 年1回必要な方 | 中間1回目 | 令和8年8月31日(月) | 令和8年9月29日(火) |
年3回必要な方 |
中間1回目 | 令和8年6月1日(月) | 令和8年6月25日(木) |
| 中間2回目 | 令和8年8月31日(月) | 令和8年9月29日(火) | |
| 中間3回目 | 令和8年11月30日(月) | 令和8年12月24日(木) | |
年11回必要な方 |
中間1~3回目 | 令和8年6月1日(月) | 令和8年6月25日(木) |
| 中間4回目 | 令和8年6月30日(火) | 令和8年7月24日(金) | |
| 中間5回目 | 令和8年7月31日(金) | 令和8年8月26日(水) | |
| 中間6回目 | 令和8年8月31日(月) | 令和8年9月29日(火) | |
| 中間7回目 | 令和8年9月30日(水) | 令和8年10月26日(月) | |
| 中間8回目 | 令和8年11月2日(月) | 令和8年11月26日(木) | |
| 中間9回目 | 令和8年11月30日(月) | 令和8年12月24日(木) | |
| 中間10回目 | 令和9年1月4日(月) | 令和9年1月27日(水) | |
| 中間11回目 | 令和9年2月1日(月) | 令和9年2月26日(金) |
出典:国税庁「中間申告分の納期限及び振替日について」
なお、11回のケースでは、「中間1~3回目」の期限がひとまとめになっており、ほかの納期よりも長めの期間が設けられています。
中間申告・中間納付の仕訳
消費税の中間申告・中間納付をした場合の仕訳は税抜処理、税込処理で異なります。
処理方法は届出を出さずに事業者が自由に選択できますが、仕訳の仕方が異なるので注意しましょう。
| 処理方法 | 特長 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
税抜処理 |
取引時の代金から、消費税分だけを分けて処理する方法 消費税が損益に影響しない 一般(原則)課税で多く採用 |
消費税が損益に影響しない 資産購入関連の課税が軽くなる 税率が変動しても対応できる |
仕訳が煩雑になる |
税込処理 |
取引時の代金から、消費税分を組み入れた形で処理して、決算時に精算する方法 消費税が損益に影響する 免税事業者や簡易課税の多くで採用 |
仕訳が少なく済む |
消費税が損益に影響する 資産購入関連の課税が重くなる 税率が変動すると過去の数値と比較しにくい |
表中の「免税事業者」とは、消費税の納税義務を免除される事業者のことです。
原則として、前々年(個人事業主の場合)または前々事業年度(法人の場合)の課税売上高が「1,000万円以下」で、インボイス制度登録(適格請求書発行事業者の登録)をしていない事業者が該当します。
税抜処理の場合
税抜処理とは、預かった消費税を「仮受消費税」、支払った消費税を「仮払消費税」と区分して、決算時に相殺します。
まず、借方勘定科目に納付した中間消費税を「仮払消費税等」、あるいは「仮払金」と仕訳します。
例えば、中間消費税20万円を現金で支払った場合は次のとおりになります。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 仮払消費税等 もしくは、仮払金 |
20万円 | 現金 | 20万円 |
次に、決算時に中間消費税を含む「仮払消費税等」(支払った消費税)を、「仮受消費税等」(預かった消費税)で相殺します。
例えば、決算時の仮受消費税等を100万円とし、仮払消費税等29万9,000円、中間消費税として支払った仮払金20万円の場合の仕訳は次のとおりです。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 仮受消費税等 | 100万円 | 仮払消費税等 | 29万9,000円 |
| 仮払金 | 20万円 | ||
| 未払消費税等 | 50万円 | ||
| 雑収入 | 1,000円 |
未払消費税等は、仮受消費税から仮払消費税と中間消費税として支払った仮払金との差額になります。なお、仮払消費税等と仮払金、未払消費税等の合計は仮受消費税と必ず一致するとは限らないため、差額を雑収入または雑損失として処理します。
税込処理の場合
税込処理では、中間消費税を納付したときはすべて「租税公課」とします。例えば、中間消費税20万円を現金で支払った場合は次のとおりになります。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 20万円 | 現金 | 20万円 |
決算時での仕訳は、納付した確定納付額のみを仕訳します。例えば、確定納付額が50万円だった場合は、以下のとおりです。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 20万円 | 現金 | 20万円 |
決算時の仕訳は、納付した確定納付額のみを仕訳します。例えば、確定納付額が50万円だった場合は、以下のとおりです。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 50万円 | 現金(または未払金、未払消費税等) | 50万円 |
税込処理の方が税抜処理に比べて処理がしやすいです。
ただし、税込処理だと、消費税が損益に影響する、資産購入関連の課税が重くなるなどのデメリットがあります。
中間申告の提出方法
中間申告の提出方法は、以下の3種類から選べます。
● 所轄税務署の窓口
● 所轄税務署へ郵送
● e-Taxで電子申請
e-Taxだと、24時間いつでも申告できて便利です。利用するためには事前登録が必要になるので、申請前に手続きを済ませておきましょう。
消費税の納付方法
消費税の納付方法は、振替納税やダイレクト納付などから選べます。
| 種類 | 内容 | 事前の手続きなど |
|---|---|---|
| 振替納税 | 預金口座からの振替日に引き落とし | 振替依頼書の事前提出 |
| ダイレクト納付 | 預金口座から即時引き落とし | e-Tax利用開始手続き ダイレクト納付利用届の提出 |
| インターネットバンキング等(※1) | ネットバンクやATMから納付 | e-Tax利用開始手続き |
| クレジットカード納付(※1) | 「国税クレジットカードお支払いサイト」から納付 | 特になし |
| スマートフォンアプリ納付(※2) | 「国税スマートフォン決済専用サイト」から納付 | 電子マネーのインストールと利用者登録、入金 |
| コンビニ納付(QRコード)(※2) | QRコードを利用してコンビニで納付(現金) | 国税庁システムでQRコードを発行 |
| 現金納付 | 納付書を使って、所轄税務署や金融機関などで納付 | 特になし |
(※1)手数料がかかる場合があります。
(※2)納付可能額は30万円までです。
上記のように、消費税はさまざまな方法で納付できます。クレジットカード納付やスマートフォンアプリ納付など、いつでもどこでも納付できる方法もあるので、活用しましょう。
消費税の中間申告・中間納付をスムーズに実施するには?
中間申告・中間納付をスムーズに実施する方法を2つ紹介します。
クレジットカードでの納付を検討してみる
クレジットカードで消費税を納付できます。インターネットから24時間いつでも納付できるので、事業の経営で忙しい方にとって便利な納付方法です。
また、クレジットカードのポイントを獲得できることも魅力です(※)。
(※)クレジットカードで税金を納付した場合、手数料が発生する。
会計ソフトをクレジットカードと紐付ける
さまざまな業務を1人で遂行しなければならない個人事業主の方には、クレジットカードと会計ソフトを連携させて経理を効率化することをおすすめします。
なお、クラウド型会計ソフトの「マネーフォワードクラウド」や「かんたんクラウド(MJS)」の利用料金を、「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」で支払うと、永久不滅ポイントが通常の4倍貯まるのでお得です(※1)(※2)。
(※1)ほかカードにてSAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)へご入会いただいている方は本サービスの対象外となります。
(※2)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
消費税の中間申告をする個人事業主におすすめのクレジットカード
中間申告・中間納付をする個人事業主におすすめのビジネスカードを2枚紹介します。
いずれも、国内利用では1,000円(税込)につき1ポイント、海外利用では1,000円につき2ポイントの永久不滅ポイントが貯まりますが、年会費や優待特典に差があるのでご自身に適したものをお選びください。
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、年会費無料で利用できるビジネスカードです。
申込時は決算書や登記簿謄本の提出が不要なため、起業して間もない会社や個人事業主の方でも気軽にお申し込みできます。
また、一時的な増額申請に対応しているため、高額になりやすい税金も無理なく支払えます。支払額に対してはポイントが還元され、節約や経費削減につながります。
このほか、会計・給与計算のクラウドサービス「かんたんクラウド(MJS)」の月額利用料2ヵ月無料という特典が付帯しているのも魅力です。本サービスには自動仕訳作成機能が搭載されており、経理業務の効率化を行えます。
さらに、特定のビジネス関連のサービスでカードを利用すると、通常のポイント還元率0.5%の4倍である2%のポイント還元が受けられます(※1)(※2)。以下は、ポイント4倍サービスの対象になるサービスの一例です。
● アマゾンウェブサービス(AWS)
● エックスサーバー
● お名前.com
● かんたんクラウド(MJS)
● クラウドワークス
● サイボウズ
● マネーフォワード クラウド
● モノタロウ(事業者向けサイトのみ対象)
● Yahoo!ビジネスサービス
日常生活で役に立つセゾンカード会員限定の特典も充実しており、例えば、毎週木曜日に全国のTOHOシネマズでお好きな映画を1,200円(税込)で鑑賞いただける「セゾンの木曜日」があります。
セゾンカードのスマートフォンアプリ「セゾンPortal」からクーポンを取得いただき、WEB(インターネットチケット販売“vit®”)または劇場でのチケット購入時にクーポンをご利用いただくことで特別料金で映画鑑賞が可能です。
(※1)ほかカードにてSAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)へご入会いただいている方は本サービスの対象外となります。
(※2)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
>>詳細はこちら
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、初年度年会費が無料、翌年以降は33,000円(税込)の年会費で保有できるビジネスカードです。
本カードは、プラチナカードならではの豪華特典やビジネスに役立つ特典など、さまざまな特典を利用できる点が魅力です。以下は、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードに付帯する優待特典やサービスの一部になります。
● 「セゾン・アメックス・キャッシュバック」の対象カード
● 旅行傷害保険として海外旅行傷害保険は最高1億円、国内旅行傷害保険は最高5,000万円補償(※1)(※2)
● 「デジタル会員証(プライオリティ・パス アプリ)」に年会費無料でお申し込みできる(※3)(※4)(※5)
● 「SAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)」に登録可能
● 複数のビジネス優待がセット「ビジネス・アドバンテージ」
● セゾン弁護士紹介サービス(※6)
● 法人向け顧問弁護士サービス「リーガルプロテクト(※7)」優待
● 毎週木曜日に全国のTOHOシネマズで映画をお得に楽しめる「セゾンの木曜日」
●「セゾンフクリコ」が入会費・年会費無料で利用可能
また、海外でのカード利用時は永久不滅ポイントの還元率が2倍(※8)(※9)にアップするため、海外でお買物する機会が多い方にも向いています。
そのほか、セゾンカード会員限定の特典として、「セゾンの木曜日」の利用で映画がお得に楽しめたり、「セゾンフクリコ」が入会費・年会費無料で利用できたりします。
「セゾンフクリコ」とは、全国25,000以上の施設を最大66%OFFで使える優待割引サービスです。特別優待として映画鑑賞券が1,300円(税込)からご購入可能です(お一人様20枚/年まで)。
ほかにも、レジャーやグルメ、トラベルなどさまざまな優待割引を、専用サイトからいつでもご利用いただけます。
(※1)航空券代や宿泊費などのお支払いに本カードを利用した場合に適用されます。
(※2)傷害死亡・後遺障害保険金額
(※3)通常年会費 469米ドル(プレステージプラン)
(※4)別途「デジタル会員証(プライオリティ・パス アプリ)」へのお申し込みが必要となります。
(※5)プライオリティ・パスのプラン内容はカードによって異なります。
(※6)紹介料はかかりませんが、別途、弁護士相談料が発生します。
(※7)顧問契約に関するご相談ではない場合、弁護士との面談時に、相談料金が発生する可能性がございます。相談料金につきましては、ベリーベスト法律事務所のスタッフにお問い合わせください。
(※8)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
(※9)小数点以下は繰り上げになります。
>>詳細はこちら
よくある質問
以下、消費税の中間申告・中間納付に関する「よくある質問」をまとめて紹介します。
Q1 いくらから消費税の中間申告・中間納付が必要になる?
前年の確定消費税額が48万円を超える場合には、消費税の中間申告・中間納付を行わなければなりません。
1年間に何回も申告・納付の作業が必要になるので、会計ソフトを導入して経理処理を効率化することをおすすめします。
Q2 簡易課税制度を選択した場合の「みなし控除率」はいくら?
下表に示すように、事業区分によって異なります。
| 事業区分 | みなし仕入れ率 |
|---|---|
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)) | 80% |
| 第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業以外)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
| 第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
| 第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業は第4種事業に該当)) | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% |
どの区分に該当するのか判断できない場合は、税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。
Q3 期限までに申告・納付を行わなかった場合、どうなる?
定められた期限までに中間申告・中間納付を行わなかった場合、延滞税が課される場合があります。
「振替口座の残高不足などで振替納税ができない」という事態が発生しないようにご注意ください。
Q4 消費税 中間納付の納付書郵送は廃止?いつ届く?
令和6年(2024年)5月から、キャッシュレス納付促進の観点で紙の納付書は廃止となりました。しかし、消費税の中間納付など一部の書類については、これからも従来どおり郵送されます。
郵送時期は税務署によって異なりますが、最初の納付期限よりも余裕をもって郵送されるはずなので、遅れずに納付しましょう。
納付が遅れると、ペナルティとして追加の税金(延滞税)が課されるケースがあります。もし、住所変更等で正しく郵送されていない可能性があったら、すぐに所轄税務署に相談してください。
まとめ
消費税とは、消費一般に課される間接税であり、標準税率は10%、軽減税率は8%となっています。前年の確定消費税額が48万円を超える個人事業主は、中間申告・中間納付をしなければなりません。納付が遅れると延滞税を課される場合があるので注意しましょう。
なお、前年の確定消費税額によって、中間申告・中間納付の回数は1回・3回・11回の3パターンに分かれます。回数が多くなると経理の手間が増大するので、ビジネスカードと会計ソフトを紐付けて処理を効率化しましょう。
おすすめのカードは、「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」の2枚です。優待特典を活用して経理を効率化し、消費税の中間申告・中間納付にお役立てください。
(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
(※)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
この記事を監修した人

【保有資格】
CFP、税理士