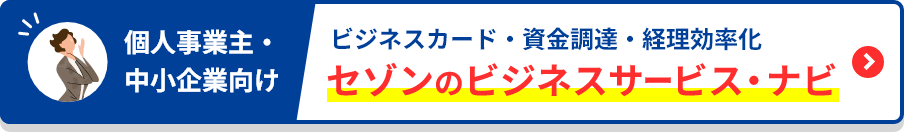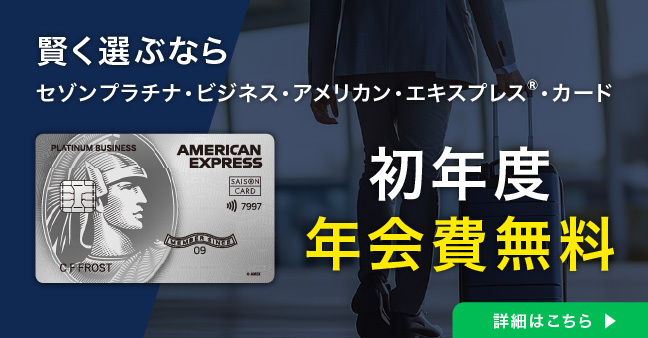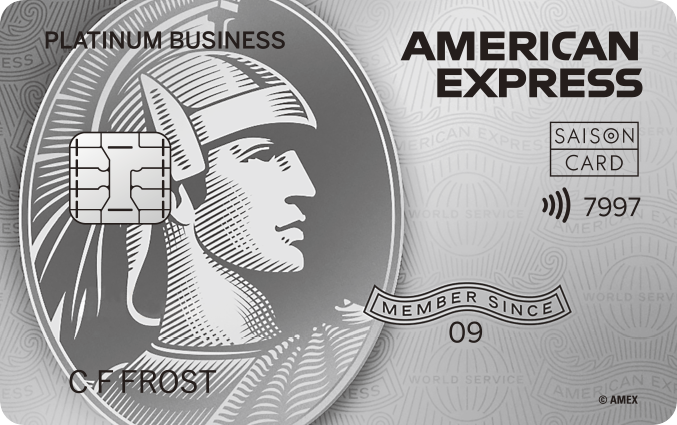顧問弁護士とは?役割や費用、メリットや選び方のポイントなどをわかりやすく解説
「安心して経営を行いたい」とお考えの事業者は、万一の事態に備えて顧問弁護士をつけておくと良いかもしれません。日頃からアドバイスを受けていれば、トラブルを未然に防いだり、迅速に解決したりすることが可能です。
本記事では、事業を営んでいる方に向けて、顧問弁護士の役割や費用相場、メリット、選び方について徹底解説します。
顧問弁護士とは?
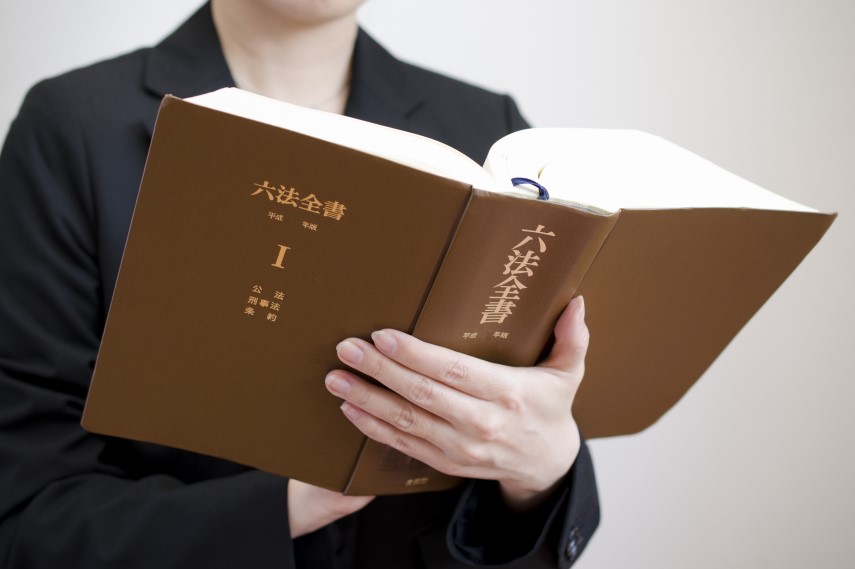
顧問弁護士とは、契約した企業のために法律上の助言や支援を継続的に提供する弁護士のことです。「かかりつけ医」のような存在であり、企業にとってさまざまなメリットがあります。
顧問弁護士がいない場合、法的トラブルが起こってから慌てて弁護士を探さなければなりません。
しかし、自社が抱える問題を解決できる弁護士を見つけるのに時間がかかってしまう可能性があります。トラブルを未然に防いだり、問題を迅速に解決したりするためには、顧問弁護士をつけておくほうが良いでしょう。
顧問弁護士と専任弁護士の違い
顧問弁護士と似たような役割を持つ弁護士に、「専任弁護士」と呼ばれる弁護士もいます。顧問弁護士と専任弁護士は、どちらも企業の法的な面をサポートする点は同じです。
ただし、顧問弁護士と専任弁護士では、それぞれ企業との関わり方が異なります。
顧問弁護士は「企業と契約を結んで業務を行う弁護士」です。一方で、専任弁護士は「企業に雇用されている弁護士」のことを指します。
専任弁護士は企業内に常駐しているため、トラブルが発生した際はより迅速なサポートに期待できます。ただし、顧問弁護士と違って毎月給与を支払う必要がある分、コストはかかりやすいです。
顧問弁護士の役割・業務内容
以下は、顧問弁護士の主な役割・業務内容です。
①契約書の作成
②就業規則の制定
③企業法務部としての活動
④事業内容や契約内容のチェック
⑤法的紛争・トラブルへの対応
それぞれについて詳しく説明していきます。
①契約書の作成
企業を経営していると、取引をしたり従業員を雇ったりする際に契約書を作成することになります。法律の専門家からのアドバイスをもらわずに契約書を作成すると、不適切な内容になってしまい、自社が不利益を被るかもしれません。
自社の状況を把握している顧問弁護士からリーガルチェックを受けるようにすれば、損害を被るリスクを低減できるほか、自社の状況や相手企業との関係性を十分に理解したうえでのアドバイスをもらえます。
②就業規則の制定
常時10人以上の従業員を使用している事業所では、「就業規則」を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法89条)。なお、作成・届出を行わないと30万円以下の罰金刑を科されます(労働基準法120条)。
顧問弁護士をつければ、労働基準法などの各種法律・法令と就業規則を照らし合わせて、適切な内容になっているかどうかをチェックしてもらうことが可能です。
③企業の法務部としての活動
企業経営には「労働基準法」「会社法」「景品表示法」など、さまざまな法律が関わるため、日常的に法律面に関する疑問や問題が生じます。
そうした事例に対応する「法務部」を設置するためには、専門的な知識を有する人材を雇用しなければなりません。中小企業の場合、「人材確保が難しい」といった事情から、法務部が存在しないケースも多いでしょう。
顧問弁護士をつけていれば、法務部としての役割を果たしてもらうことも可能です。日常的に法律に関する相談ができるほか、紛争やトラブルにつながる要素をあらかじめ対処する「予防」も可能となるでしょう。
社内に法務部を設置する余裕がない中小企業の経営者は、顧問弁護士の活用を検討してみてください。
④事業内容や契約内容のチェック
「事業内容や取引先との契約内容は、法的に大丈夫だろうか」「顧客に信用不安が生じ、取引を継続すべきか迷っている」などの不安をお持ちのケースがあるかもしれません。
違法なまま事業を継続していると、行政処分を受けたり、刑事罰を科されたり、損害賠償の請求をされたりする可能性があります。
不安がある場合は、違法営業となるリスクを回避するために、法的な観点からチェックしてもらいましょう。
日頃から付き合いがある顧問弁護士なら、企業の活動内容や業界の慣行を深く理解しているため、初対面の弁護士よりも迅速かつ的確な判断を行えます。
また、法律のプロがチェックした結果の指摘・判断であると伝えることは、取引先や従業員からの信頼感を高める要素にもなるでしょう。
⑤法的紛争・トラブルへの対応
事業を営んでいると、「労働者とのトラブル」「顧客からのクレーム」「不良債権の発生」といった問題に直面することがあります。
例えば、社員が業務のストレスでうつ病を発症した場合、安全配慮義務に違反しているとして損害賠償を請求される可能性があります。
こうした事態に法的知識を有さない者が自己判断で対応すると、問題が深刻化してしまうかもしれません。顧問弁護士をつけておけば、法的紛争の拡大を防止し、迅速かつ適切に解決することが可能です。
顧問弁護士の費用相場
弁護士の顧問料は自由に設定することが可能で、弁護士によって異なります。
ただし、相場が存在しないというわけではなく、日本弁護士連合会が2009年度に実施したアンケート調査(※)によれば、月額3~5万円のケースが多いようです。
なお、顧問契約を締結する際は、サービス内容・業務量によって費用が変動することにご留意ください。例えば、より手厚いサービスやサポートを希望する場合、月額10万円以上の顧問料がかかるケースもあります。
(※)日本弁護士連合会「アンケート結果にもとづく中小企業のための弁護士報酬の目安(2009年度アンケート結果版)」
顧問弁護士のメリット
顧問弁護士と契約を締結すると、どのようなメリットが生まれるのでしょうか。前述の役割や業務内容を踏まえた、顧問弁護士のメリットをご紹介します。
①さまざまな問題を気軽に相談できる
②有事の迅速なレスポンス、コスト抑制
③企業の信頼性向上
以上3点について、詳しく説明していきます。
①さまざまな問題を気軽に相談できる
顧問弁護士がいれば、日常的に発生するさまざまな悩みを気軽に相談し、法的アドバイスを受けることが可能です。訴訟などの紛争に発展する前に、専門家と一緒に問題に対処できることがメリットです。
日本弁護士連合会の「第2回中小企業の弁護士ニーズ全国調査報告書」によると、中小企業が顧問弁護士に相談する内容は以下のようになっています。
■雇用問題
■債権回収
■契約書相談・作成
■社内規定・ルール整備
■経営改善・再建・資金繰り
■事業承継
■クレーマー対策
■債権管理・保全
■各種情報管理
■知的財産権問題
■総会、役員会の運営
■課税問題
■商品・製品トラブル
■M&A
■ハラスメントなど社内問題
■下請け・不公正問題
■海外取引
■詐欺・悪徳商法問題
■インターネット問題
■海外進出
■海外トラブル
■その他
いずれの問題についても、7割から9割程度が「相談した結果、満足した(大いに満足+まあ満足)」と回答しており、満足度が高いことがわかります。
また、顧問弁護士は継続的に企業に関わるため、業界の慣行について理解が深まり、次第にアドバイスの質が向上していきます。
②有事の迅速なレスポンス、コスト抑制
顧問弁護士をつけておけば、法的に気になることが生じた際や何らかのトラブルが発生した際に、迅速にアドバイスをもらえます。
「行政による立入検査」といった緊急時には弁護士を探している時間的余裕がありませんが、顧問弁護士がいれば時機を逸することなくサポートを受けることが可能です。
また、コストや説明に要する時間を低減できることも顧問弁護士のメリットです。
単発で相談する場合は相談料が毎回発生するため、回数が多くなると月額制の顧問弁護士よりもコストが増大します。
また、自社の状況や業界の慣行をいちから説明しなければなりません。顧問弁護士なら、背景事情を説明する手間なく、適切な助言を受けられます。
③企業の信頼性向上
近年、「コンプライアンス」の強化が重視されるようになり、事業を営む際に法令や倫理を遵守する姿勢が求められるようになりました。
顧問弁護士がいれば、「コンプライアンスの推進に取り組んでいる」と対外的にアピールすることが可能です。企業の信頼性を高め、取引先や消費者からの評価を向上させたい企業は、顧問弁護士をつけるという選択肢がおすすめです。
顧問弁護士を選ぶポイント
顧問弁護士を選ぶ際は、以下4つのポイントに注目しましょう。
● 法律事務所の規模
● 実績
● 自社の業界に対する理解の深さ
● コミュニケーションの取りやすさ
上記のポイントを意識しておくと、自社の環境やニーズに適した顧問弁護士を選びやすくなります。以下で顧問弁護士を選ぶポイントを詳しく解説します。
法律事務所の規模
顧問弁護士を探す際は、まず法律事務所の規模や所属している弁護士の人数をチェックしましょう。
顧問弁護士の対応力やレスポンスの早さは、法律事務所に所属する弁護士の人数に左右される場合もあります。規模が大きい法律事務所で所属する弁護士の人数も多い場合は、その分対応力が高く、より迅速なサポートに期待できます。
実績
法律事務所の実績もチェックしたいポイントのひとつです。
実績豊富な法律事務所であったとしても、顧問弁護士としての経験も豊富にあるとは限りません。なかには個人向けのトラブル解決が中心で、企業案件の経験は少ない弁護士もいます。
一方で、企業案件の実績が豊富にある弁護士なら、これまでの経験を活かした的確なサポートに期待できます。
契約後に期待通りの活躍をしてもらうためにも、企業の顧問弁護士としての経験があるかどうかは事前に確認しましょう。
自社の業界に対する理解の深さ
業界によっては、その業界特有の商慣習やルールが存在することもあります。より的確なサポートを受けるには、自社の業界の商慣習やルールに関して深い理解を持つ弁護士を頼りたいところです。
同業界の企業の顧問弁護士としての経験がある場合は、その商慣習やルールにも詳しい可能性が高いです。顧問弁護士を探す際は、過去にどのような業界で顧問弁護士をしていたかもチェックしておくと良いでしょう。
コミュニケーションの取りやすさ
日常的に顧問弁護士を頼りたいなら、コミュニケーションの取りやすさも重視しましょう。
レスポンスが早くてコミュニケーションを取りやすい相手なら、より気軽にさまざまなことを相談できます。
「弁護士紹介サービス」が付帯するビジネスカードがある
クレディセゾンのビジネスカードには、以下に示すように、顧問弁護士を探すのに役立つサービス・優待特典が付帯しています。
■セゾン弁護士紹介サービス:相談内容に合わせて、第一東京弁護士会を通じて弁護士を紹介するサービス(紹介に関する費用はゼロ)
■法人向け顧問弁護士サービス「リーガルプロテクト*」優待:法人向け顧問弁護士サービスの月額費用が割引
自社に適した顧問弁護士を探す際は、これらをぜひご活用ください。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
顧問弁護士をつけることを検討している事業主におすすめのビジネスカードは「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」です。
年会費は初年度無料、翌年以降は33,000円(税込)です。追加カードは1枚3,300円(税込)の年会費で、最大9枚まで発行可能です。
海外でのショッピング利用時は2倍(※1)の永久不滅ポイントが貯まるので、海外出張が多い方にもおすすめです。
貯まったポイントは、2万点以上の人気アイテムが出品中のセゾンカードの総合通販サイト「STOREE SAISON(ストーリーセゾン)」で使えます。
さらに、プラチナカードならではの充実した付帯サービス・優待特典も魅力です。「セゾン弁護士紹介サービス」や「リーガルプロテクト(※2)」、ビジネスに役立つサービスが優待価格で利用できる「ビジネス・アドバンテージ」など、さまざまな特典が付帯しています。
また、旅行傷害保険が付帯しており、海外旅行中の事故については最高1億円まで、国内旅行中の事故については最高5,000万円まで補償されます(※3)。
(※1)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
(※1)小数点以下は繰り上げになります。
(※2)顧問契約に関するご相談ではない場合、弁護士との面談時に、相談料金が発生する可能性がございます。相談料金につきましては、ベリーベスト法律事務所のスタッフにお問い合わせください。
(※3)傷害死亡・後遺障害保険金額
(※3)海外旅行傷害保険は、本カードで指定の旅行代金等の決済があった場合、保険適用となります。
>>詳細はこちら
まとめ
顧問弁護士は、企業にとって「かかりつけ医」のような存在です。日常的に相談を行うため、自社の内情や業界の慣行を熟知することになり、トラブルが発生した際に迅速・的確な解決に結びつきます。
顧問料は月額3~5万円のケースが多く見受けられますが、サービス内容・業務量によって変動することにご留意ください。
顧問弁護士の主な役割・業務内容は、「契約書の作成」「就業規則の制定」「企業法務部としての活動」「事業内容や契約内容のチェック」「法的紛争・トラブルへの対応」の5つです。
初対面の弁護士とは異なり、「さまざまな問題を気軽に相談できる」「有事の迅速なレスポンス、コスト抑制」「企業の信頼性向上」といったメリットがあります。これらのメリットを最大限活かすためにも、自社の環境や業界に適した顧問弁護士を探しましょう。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードには「セゾン弁護士紹介サービス」や法人向け顧問弁護士サービス「リーガルプロテクト(※)」の優待が付帯しており、自社に適した弁護士を顧問に据えるのに役立ちます。
これら以外にもビジネスに役立つサービス・優待特典が数多く付帯しているので、企業を経営している方はぜひ申し込みを検討してください。
(※)顧問契約に関するご相談ではない場合、弁護士との面談時に、相談料金が発生する可能性がございます。相談料金につきましては、ベリーベスト法律事務所のスタッフにお問い合わせください。
この記事を監修した人

【保有資格】
弁護士、宅地建物取引士