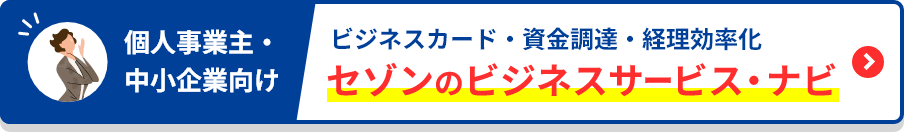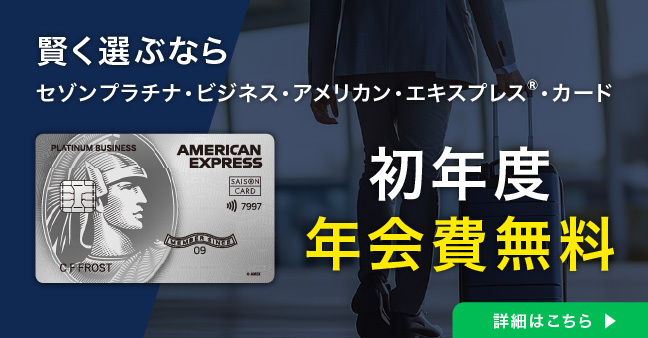住宅借入金等特別控除申告書とは?住宅ローン控除の要件や書類の記載方法を解説
しかし、なかには「制度の仕組みや内容、手続きについてよくわからない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
本記事では、住宅ローン控除を受けるために提出する「住宅借入金等特別控除申告書」の書き方を詳しく解説します。必要な書類や適用要件など、経理・労務・総務担当者が知っておくべきことも紹介するため、ぜひ参考にしてください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは?
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローンなどを利用してマイホームの新築・取得・増改築などを行い、一定の要件を満たす場合に、所得税または住民税から控除を受けられる仕組みです。
支払った税金の一部が戻ってくる制度で、一般的には「住宅ローン控除」と呼ばれています。
以下で適用条件などを紹介するので、従業員から相談を受けた際に対応できるよう、内容を正確に把握しておきましょう。
住宅借入金等特別控除の適用要件
以下、住宅借入金等特別控除の適用要件を、「共通の要件」と「住宅などの区分に応じた要件」の順に紹介します。
共通の適用要件
まず、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、以下の9要件をすべて満たす必要があります。
1. 住宅の新築などの日から6ヵ月以内に居住の用に供している
2. 控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供している
3. 「住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上を専らご自身の居住の用に供している」かつ「控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下」(※)
4. 新築・取得のために、10年以上にわたって分割して返済する一定の借入金または債務がある
5. 2つ以上の住宅を所有している場合は、「主として居住の用に供する」と認められる住宅であること
6. 居住年、および、その前2年の計3年間に、所定の「譲渡所得の課税の特例」の適用を受けていない
7. 居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について所定の「譲渡所得の課税の特例」を受けていない
8. 取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得ではない
9. 贈与による住宅の取得ではない
上記はあくまで概略です。簡単に説明すると、ご自身が住むためのマイホームを購入し、住宅ローンを組んでいて所得が一定以下の方が対象です。
税制については都度改正される可能性があるため、詳細は国税庁や国土交通省の公式WEBサイトなどでご確認ください。
(※)特例居住用家屋または特例認定住宅などの場合は、「住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で、床面積の2分の1以上を専らご自身の居住の用に供している」かつ「控除を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下」
住宅などの区分に応じた適用要件
前述した「共通の適用要件」に加えて、下表に示す「住宅などの区分に応じた適用要件」も満たさなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
| 住宅などの区分 | 適用要件 |
|---|---|
| 認定長期優良住宅 | 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」11条1項で規定されている「認定長期優良住宅」に該当 |
| 低炭素建築物 | 「都市の低炭素化の促進に関する法律」2条3項で規定されている「低炭素建築物」に該当 |
| 低炭素建築物とみなされる特定建築物 | 「都市の低炭素化の促進に関する法律」12条で規定されている「認定集約都市開発事業により整備された特定建築物」で、同法16条の規定によって「低炭素建築物」とみなされる建築物に該当 |
| 特定エネルギー消費性能向上住宅 | 「エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅」の用に供する家屋として、所定の基準に適合 |
| エネルギー消費性能向上住宅 | 「エネルギーの使用の合理化に資する住宅」の用に供する家屋として、所定の基準に適合 |
また、住宅借入金等特別控除を受けるには、確定申告の際に都道府県や市区町村、建築士事務所などが発行する通知書や証明書の写しを提出する必要があります。
詳細は、国税庁や国土交通省の公式WEBサイトなどでご確認ください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるための手続き
控除を受ける際の手続きは、「初年度」と「2年目以降」で内容が異なるためご注意ください。以下でそれぞれの内容を説明します。
初年度:会社員も確定申告が必要
住宅借入金等特別控除の初年度は、会社員の方もご自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告の提出期限は、通常、毎年2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌平日)です。
確定申告書に必要事項を記入したうえで、後述する書類を添付し、納税地(原則として住所地)の所轄税務署に提出しなければなりません。
年末調整では手続きを行えないため、給与所得者(会社員、公務員など)も、初年度は確定申告をする必要があります。
なお、従来は税務署に行き、所定の申請書類を入手したうえで、必要事項を記入して確定申告を行う必要がありました。
近年では、パソコンやスマホからオンラインでの確定申告が可能です。確定申告の手続き内容については、国税庁の公式WEBサイトなどでご確認ください。
2年目以降:会社員なら年末調整で手続き可能
給与所得者(会社員、公務員など)の場合、2年目以降は年末調整で手続きが可能です。しかし、事業所得者の場合、2年目以降も確定申告を行わなければなりません。
勤務先または税務署に提出する書類は、次項で紹介します。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるために必要な書類

ここからは、初年度に必要になる「共通の提出書類」「住宅などの区分に応じた提出書類」、および、2年目以降に必要になる書類(「事業所得者の場合」と「給与所得者の場合」)を紹介します。
共通の提出書類
初年度は、以下に示す書類を確定申告書に添付して税務署に提出する必要があります。
● 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(※1)
● ローンを組んだ金融機関などから交付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
● 家屋の「登記事項証明書」など(床面積が50平方メートル以上(※2)であることを明らかにする書類)
● 家屋の「工事請負契約書」または「売買契約書」の写しなど(家屋の取得対価の額を明らかにする書類)
● 土地の購入に関する住宅借入金などについて控除を受ける場合は、土地の「登記事項証明書」など(敷地の取得年月日を明らかにする書類)、および、土地の「売買契約書」の写しなど(土地の取得対価の額を明らかにする書類)
● 国または地方公共団体などから補助金などの交付を受けた場合は、市区町村からの「補助金決定通知書」など(補助金などの額を証する書類)
● 住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合は、「贈与税の申告書」など(住宅取得等資金の額を証する書類)の写し
提出書類は、家を建てた建設会社から受け取った書類に含まれているケースが一般的です。
そのほか、家屋に関する書類は法務局、ローンに関することは銀行や金融機関の担当窓口までご確認ください。
(※1)国税庁公式WEBサイトからダウンロード可能
(※2)特例居住用家屋または特例認定住宅などの場合は、40平方メートル以上50平方メートル未満
住宅などの区分に応じた提出書類
初年度は、前述した「共通の書類」に加えて、下表に示す「住宅などの区分に応じた書類」も、確定申告書に添付して税務署に提出する必要があります。
| 住宅などの区分 | 適用要件 |
|---|---|
認定長期優良住宅 |
● 都道府県または市区町村などの長期優良住宅建築等計画などの「認定通知書」の写し ● 市区町村の「住宅用家屋証明書」(「認定長期優良住宅に該当する」などの記載があるもの)、または、建築士などが発行した「認定長期優良住宅建築証明書」 |
低炭素建築物 |
● 都道府県または市区町村などの低炭素建築物新築等計画の「認定通知書」の写し ● 市区町村の「住宅用家屋証明書」(「認定低炭素住宅に該当する」などの記載があるもの)、または、建築士などが発行した「認定低炭素住宅建築証明書」 |
| 低炭素建築物とみなされる特定建築物 | ● 市区町村の「住宅用家屋証明書(特定建築物用)」 |
特定エネルギー消費性能向上住宅 |
● 建築士などが発行した「住宅省エネルギー性能証明書」、または、登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し(断熱等性能等級に関する評価が等級5以上、および、一次エネルギー消費量等級に関する評価が等級6以上であるもの) |
エネルギー消費性能向上住宅 |
● 建築士などが発行した「住宅省エネルギー性能証明書」、または、登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し(断熱等性能等級に関する評価が等級4以上、および、一次エネルギー消費量等級に関する評価が等級4以上であるもの) |
なお、上表はあくまで「概略」「原則」です。詳細は、国税の庁公式WEBサイトなどをご覧ください。
2年目以降の提出書類(事業所得者の場合)
事業所得者の場合、2年目以降は、以下の書類を確定申告書に添付して税務署に提出する必要があります。
● 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
● ローンを組んだ金融機関などから交付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
なお、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は国税庁の公式WEBサイトからダウンロード可能です。印刷して必要事項を記入しましょう。
2年目以降の提出書類(給与所得者の場合)
給与所得者の場合、2年目以降は、勤務先に以下の書類を提出することで、年末調整により控除を受けることが可能です。
● 「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(税務署から交付された用紙に、控除を受ける方や給与の支払者が必要事項を記入)
● 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(ローンを組んだ金融機関などから交付される)
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の書き方は、次項で詳しく説明します。
住宅借入金等特別控除申告書の記載方法
2年目以降、年末調整で控除を受けるために勤務先に提出する「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に記入する主な事項を、下表にまとめました。
| 控除を受ける従業員が記入する項目 | ● 本人の氏名 ● 世帯主の氏名、本人との続柄 ● 住所または居所 ● 新築または購入に係る借入金などの計算(「住宅借入金などの年末残高」「控除額」など) |
|---|---|
| 給与の支払者が記入する項目 | ● 給与の支払者の名称(氏名) ● 給与の支払者の法人番号 ● 給与の支払者の所在地(住所) |
勤務先(給与の支払者)が記入する欄と、控除を受ける方が記入する欄が存在するためご注意ください。なお、一定の要件を満たす借換えをした場合は、以下の式で計算した金額を「住宅借入金などの年末残高」の欄に記入します。
本年の住宅借入金などの年末残高 × (借換え直前の当初残高÷新たな住宅借入金などの当初残高)
なお、住宅借入金等特別控除申告書は国税庁の公式WEBサイトでダウンロード可能です。
詳細は、国税庁の公式WEBサイトにある「記載例」などをご確認ください。
業務の効率化につながるサービスも検討しよう
企業で経理や労務、総務などを担当している方は、多種多様な業務に追われているのではないでしょうか。
取り扱う文書の種類は多岐に渡り、住宅借入金等特別控除申告書を始めとして、さまざまな書類への対応に多大な時間を費やしているかもしれません。
近年、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)という考え方が注目されています。業務を効率化するために、「手作業での事務処理」から「システムを活用した事務処理」への移行を進めましょう。
例えば、ご利用明細書の発行から回収業務(督促)までを株式会社クレディセゾンが代行する「セゾンインボイス」を利用すれば、請求業務を最短15分に短縮することが可能になりますので、ぜひ導入をご検討ください。
>>詳しくはこちら
業務効率化に役立つおすすめのセゾンカード
経費管理を行う際には、業務効率化に役立つビジネスカードを利用するのがおすすめです。
クレディセゾンではさまざまなビジネスカードを発行していますが、そのなかでも特におすすめのクレジットカードとして、以下の2種類が挙げられます。
● セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
● セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
それぞれの特長を解説します。
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、年会費無料で利用できるビジネスカードです。
決算書や登記簿謄本の提出が不要なので、起業して間もない会社や個人事業主の方でも気軽にお申し込みできます
また、一時的な増額申請に対応しているため、高額になりやすい税金も無理なくお支払いできます。お支払い額に対してはポイントが還元され、節約や経費削減につながります。
このほか、会計・給与計算のクラウドサービス「かんたんクラウド(MJS)」の月額利用料2ヵ月無料という特典が付帯しているのも魅力です。本サービスには自動仕訳作成機能が搭載されており、経理業務の効率化を行えます。
さらに、特定のビジネス関連のサービスでカードを利用すると、通常のポイント還元率0.5%(※)の4倍である2%のポイント還元が受けられます。以下は、ポイント4倍サービスの対象になるサービスの一例です。
● アマゾンウェブサービス(AWS)
● エックスサーバー
● お名前.com
● かんたんクラウド(MJS)
● クラウドワークス
● サイボウズ
● マネーフォワード クラウド
● モノタロウ(事業者向けサイトのみ対象)
● Yahoo!ビジネスサービス
日常生活で役に立つセゾンカード会員限定の特典も充実しており、例えば、毎週木曜日に全国のTOHOシネマズでお好きな映画を1,200円(税込)で鑑賞いただける「セゾンの木曜日」があります。
セゾンカードのスマートフォンアプリ「セゾンPortal」からクーポンを取得いただき、WEB(インターネットチケット販売“vit®”)または劇場でのチケット購入時にクーポンをご利用いただくことで特別料金で映画鑑賞が可能です。
(※)ほかカードにてSAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)へご入会いただいている方は本サービスの対象外となります。
(※)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
>>詳細はこちら
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの特長は、次のとおりです。
● 年会費は初年度無料、翌年度以降33,000円(税込)
● 追加カードは最大9枚まで発行可能(1枚につき年会費3,300円(税込))
● サービス年会費5,500円(税込)の「SAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)」の登録でJALのマイル最大1.125%還元(※1)(※2)
● クレジットカードの利用限度額を高額に設定できる可能性がある
● プラチナカードならではの「コンシェルジュ・サービス」や「旅行傷害保険(※3)」なども利用可能
年会費は初年度無料、2年目以降は33,000円(税込)で利用できます。
個人用カードと異なり、引き落とし口座を「個人名義口座」と「法人名義口座(代表者名併記のもの)」から選べることがビジネスカードの魅力です。法人名義口座を選べば、経費管理がスムーズになるでしょう。
国内ショッピングでは税込1,000円につき1ポイント、海外ショッピングでは通常の2倍(1,000円につき2ポイント)の永久不滅ポイントが貯まるので、事業で使う物品やサービスを購入する際もお得です。
なお、1枚あたり3,300円(税込)の年会費で最大9枚までの追加カードを発行可能です。追加カードでのお支払いも、永久不滅ポイントの付与対象です。ビジネスで使う物品・サービスのお支払いに備えて、社員に追加カードを持たせておきましょう。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの最大の特長は、ビジネスに役立つ優待特典・サービスが充実していることです。
また、ビジネス用カードでありながら「SAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)」を優待価格の年会費5,500円(税込)で利用できる点もうれしい特長のひとつです。
なお、「旅行傷害保険の補償額」「プライオリティ・パスへの無料登録」「海外でのサポート体制」については、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カードと同じ内容です。
補償や優待、サポートが手厚いため、海外出張の際にも安心の1枚です。ほかにも、「セゾンの木曜日」の利用で映画がお得に楽しめたり、「セゾンフクリコ」が入会費・年会費無料で利用できます。
「セゾンフクリコ」とは、全国25,000以上の施設を最大66%OFFで使える優待割引サービスです。特別優待として映画鑑賞券が1,300円(税込)からご購入可能です(お一人様20枚/年まで)。
ほかにも、レジャーやグルメ、トラベルなどさまざまな優待割引を、専用サイトからいつでもご利用いただけます。
(※1)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
(※2)小数点以下は繰り上げになります。
(※3)海外旅行傷害保険は、航空券代や宿泊費などのお支払いに本カードを利用した場合に適用されます。
>>詳細はこちら
まとめ
ローンを組んで住宅を購入し、一定の要件を満たす場合は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けることが可能です。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、ご自身で手続きを行う必要があります。「初年度と2年目以降」「事業所得者と給与所得者」で、手続きが異なるため注意しましょう。
所定の申請書類を作成する必要があるため、必要事項の記入・提出時には、本記事や国税庁の公式WEBサイトなどを参考にしてください。
企業で経理や労務、総務などを担当している方は、従業員から申請があった際にスムーズに対応できるよう、記入方法や提出手順などを正確に把握しておく必要があります。
不明な点がある場合は、1人で抱え込まず、税務署や税理士などに相談しましょう。
なお、経理や労務、総務などの担当者は、住宅借入金等特別控除への対応を始め、日々さまざまな業務に追われ、大きな負担を感じているのではないでしょうか。
例えば、「セゾンインボイス」なら、請求業務を最短15分に短縮でき、ヒューマンエラーの低減や業務効率化に役立ちます。
また、クレディセゾンでは、業務効率化に役立つビジネスカードを発行しています。担当者の負担を軽減するために、ぜひセゾンカードのお申し込みをご検討ください。
(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。