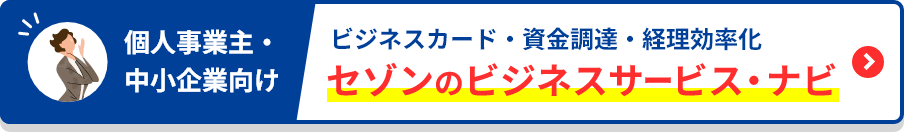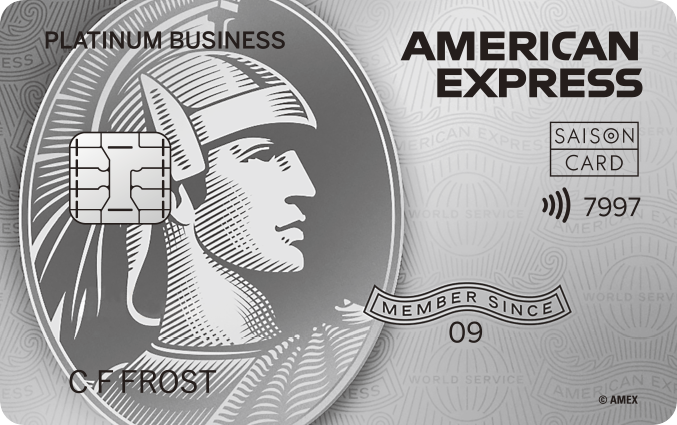個人事業主が経費にできるもの・できないものは?どこまで計上できるのかを解説
経費を適切に計上すれば節税につながりますが、すべての支出が経費として認められるわけではありません。例えば、所得税や住民税などの納税や私的な支出は、経費の対象外です。
個人事業主として正しく経費の判断をするためには、経費にできるもの・できないものの基本的な区別を理解しておくことが必要です。
本記事では、経費の判断基準や、個人事業主が経費にできるもの・できないものの具体例、経費計上の注意点などを紹介します。
個人事業主の経費とは?
個人事業主が事業を進めるうえで、必ず出てくる話題が「経費」です。経費とは、個人事業主が事業を進めるうえで必要となる費用のことです。いわゆる「必要経費」や「コスト」と表現すれば、わかりやすいかもしれません。
材料や商品の仕入れはもちろん、事務所の家賃や水道光熱費も経費に含まれます。
経費は事業にかかるコストのため、所得税の計算のときには、事業の収入(売上)から差し引くことができます。経費をしっかり管理して確定申告に計上すれば、節税につながります。
個人事業主が経費にできる判断基準とは?
個人事業主の支出が経費としてどこまで認められるのかは、事業の支出であるかどうかが判断の基準になります。判断のポイントや上限の有無について、以下で見ていきましょう。
事業に必要な支出は経費として認められる
事業に必要な支出は、基本的に経費として認められます。事業で利用する事務用品やパソコンの購入費用、広告宣伝費、外注費など事業にかかわる費用はいずれも経費計上が可能です。
また、自宅兼事務所の家賃・水道光熱費など、事業とプライベートで兼用するものの支出は、事業で利用する割合を計算(家事按分)し、その割合に応じた金額を経費に計上できます。
一方で、事業で利用しない自家用車などプライベートな支出は、経費として認められません。また、所得税・住民税などの税金や国民年金・国民健康保険料などのお支払いも、事業上の支出ではないため、経費として認められません。
個人事業主の経費に上限は設定されていない
個人事業主の経費に上限はなく、事業上で必要な支出である限り、金額が大きくなる場合も経費として認められます。
一方で、中小企業の場合は接待交際費に上限があります。接待飲食費の50%または接待交際費の年間800万円までのいずれかを上限として選択し、その範囲内で経費計上を行います。
個人事業主が経費にできるもの一覧
個人事業主にとって経費は「事業につながる出費」であれば、すべて当てはめることができます。経費は前述のとおり、確定申告で収入から差し引いて計上すれば節税につながります。少額の経費でもしっかりと管理することが大切です。
経費の分類としてわかりやすいのが、確定申告書に記載されている「勘定科目」です。
どんな出費が経費として認められるのか、見ていきましょう。
● 租税公課:個人事業税や固定資産税、自動車税といった税金
● 荷造運賃:宅配便や郵便物の梱包材や送料など
● 水道光熱費:水道料金、電気料金、ガス料金など
● 旅費交通費:公共交通料金、タクシー代、駐車場代、宿泊費など
● 通信費:電話代、インターネット料金、切手、サーバー代など
● 広告宣伝費:名刺、パンフレット制作費など
● 接待交際費:顧客との飲食やお祝い金、贈答品など
● 損害保険料:火災保険、自動車保険など
● 修繕費:事務所や自動車の修繕など
● 消耗品費:事務用品や電球、USBメモリなど
● 減価償却費:パソコンやカメラ、自動車など、高額な固定資産を一定期間にわたり計上する費用
● 福利厚生費:慶弔見舞金、慰安旅行、従業員の健康診断費など
● 給料賃金:従業員、スタッフに支払う給料
● 外注工賃:外注スタッフなどに支払うギャランティ
● 利子割引料:借り入れした運転資金やローンなどの利息
● 地代家賃:事務所の家賃や駐車場代など
● 貸倒金:売掛金や貸付金などの回収できなくなった金額
● 雑費:クリーニング代やゴミ処理費用など、どの項目にも該当しない少額の費用
● 専従者給与:青色事業専従者(家族など)に支払う給料
個人事業主の出費で経費にできないもの
個人事業主の事業にかかわるコストは、原則としてすべて経費になります。個人事業主としては、少しでも多くの経費を計上して節税につなげたいものです。
しかし、なかには経費として認められないものもあります。いくつか例を出してみましょう。
私的な購入や飲食などの費用
私的な目的で購入した物品の費用は、経費に計上できません。また、プライベートな飲食費や交際費なども同様に経費計上の対象外です。
もちろん、事業のための物品の購入費用や交際費などは、経費に計上できる可能性があります。その場合は、金額や内容を示す領収書・レシートを保管し、帳簿に記録して、事業上の支出であることを説明できるよう備えておきましょう。
福利厚生費
福利厚生費は、従業員の慰労や労働環境の改善、生活の向上などを目的として企業や事業主が支出する費用です。
個人事業主は従業員ではないため、本人のための支出を福利厚生費として経費に計上することはできません。
一方で、個人事業主が従業員を雇っている場合は、従業員のための福利厚生費が要件を満たせば、経費に計上できます。
健康診断にかかる費用
個人事業主には、健康診断を受ける法律上の義務はなく、健康診断にかかる費用は経費計上できません。また、健康診断の費用は、原則として医療費控除の対象外である点にも注意が必要です。
なお、従業員を雇っている場合、事業主は従業員に年1回の健康診断を受けさせる義務があります。従業員の健康診断の費用は、要件を満たせば経費として認められます。
国民年金保険料・国民健康保険料
個人事業主自身の国民年金保険料・国民健康保険料は、事業上の支出ではないため経費に計上できません。ただし、国民年金保険料・国民健康保険料はいずれも社会保険料控除の対象であり、その金額分が所得額から差し引かれ、所得税や住民税の納税額が少なくなります。
なお、個人事業主が従業員を雇う場合、従業員の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)の雇用主の負担分は、経費に計上できます。
また、事業用自動車の保険料、事業用の店舗・事務所の火災保険料や地震保険料は、事業上の支出となるため、経費計上が可能です。
税金のお支払い
個人事業主の所得税と住民税は、事業に関係なく支払う義務があります。そのため、経費としては計上できません。
ただし、事業用の印紙税や個人事業税といった税金は、経費として計上が可能です。
生計をともにする家族・親族へのお支払い
個人事業主と生計をともにする家族や親族は、事業主と家計が同じとみなされます。
そのため、給料を支払っていても、経費として計上できません(青色事業専従者給与を届け出て、条件を満たした家族や親族は、給与を経費に計上できます)。
資産と見なされるもの
パソコンなど1点10万円を超える機材などは、経費ではなく個人事業主の「固定資産」として計上されます。そのうえで、法定耐用年数に応じて「減価償却費」として経費に計上します。
また、入居時の敷金は、退去時に返ってくることを前提とするコストのため、「資産」として見なされます。
礼金は、20万円未満の場合は「地代家賃」として経費計上ができます。20万円以上の場合は資産として処理し、賃借期間(または5年間)で減価償却します。
プライベートと経費を分ける「家事按分」
家事按分とは、プライベートな生活費と必要な経費が混在している費用から、事業に利用した経費部分を算出することです。
家事按分には法的ルールはありませんが、仮に税務署から説明を求められたとき、個人事業主としてハッキリと答えられる根拠を示せることが大切です。
(例1)家賃
個人事業主の事務所が住居と一体化している場合は、住居全体の面積と事務所スペースの面積の割合を割り出し、その数値から経費分としての家賃を算出します。
例えば、全面積が80平方メートルのマンションに居住している場合、6畳の1部屋(約10平方メートル)を事務所として利用しているなら、割合はおよそ12.5%となります。
家賃が10万円だとして、経費として計上できる家賃は12,500円です。
(例2)水道光熱費
個人事業主が契約している水道光熱費のうち、家事按分として割合を出しやすいのは電気代でしょう。自営業の業種によっても異なりますが、就業時間やコンセントの数など、さまざまな家事按分の考え方があります。
あくまで一例ですが、室内でパソコンを使う作業が多い仕事は、就業時間を1日8時間とすると、1日で利用する電気代の3分の1を経費として計上できるでしょう。
水道代やガス代は、業務で多用する職種以外は、家事按分としては少額になるのが一般的です。
(例3)通信費
個人事業主が利用している携帯電話の料金やインターネットプロバイダの契約費などは、仕事に不可欠なものです。理想は、プライベート用と業務用の電話を別々に分けておくことです。
しかし、上記が難しい場合は、これも家事按分する必要があります。
携帯電話なら「通話履歴からプライベート通話と業務用の通話の割合を出す」、インターネットなら「プライベートタイムの利用時間と就業時間の利用時間を比較して割合を出す」など、根拠を示して家事按分をしましょう。
(例4)自動車関連
個人事業主が利用する自動車も、携帯電話と同様にプライベート用と業務用の2台を所有するのが理想ですが、小規模事業者が多い個人事業主にとっては非現実的です。
プライベートでの走行距離と業務での走行距離を計算して、家事按分の割合を決定しましょう。
自動車関連の経費としては、自動車本体の購入代金、ガソリン代、駐車場費用、自動車税、車検代など、多くのものが含まれます。
なお、購入代金は資産に計上し、減価償却で家事按分するのが一般的です。
また、仕事で自動車をよく利用するのであれば、ETCカードも必要になる場合があります。個人で利用しているETCカードを利用した場合、日時や走行距離、高速の利用料金を個人利用とは分けて管理しなくてはならないため、利用分を思い出すのも手間になります。
法人カードと一緒にETCカードを発行して利用すれば、プライベートと経費で利用した料金を区別しやすくなります。クレディセゾンが発行するビジネスカードはETCカードが無料で発行できるため、仕事で車をよく利用する方はご検討ください。
個人事業主が経費計上するときの注意点
個人事業主が経費計上するときの注意点をいくつか紹介します。領収書・レシートの保管、経費として説明できるようにする準備など、日頃から意識しておくことが大切です。
以下で詳しく解説します。
領収書・レシートをしっかり保管する
経費に該当するお支払いをした場合は、その証明としてレシートや領収書を保管しておきましょう。領収書やレシートの保管がない場合、経費計上できません。
クレジットカードの利用明細書もお支払いの証明書類として利用できます。利用明細書には決済日、購入者の氏名、購入金額、発行元の情報、但し書き(サービスの内容、飲食代であれば同伴相手や目的など)などの記載が必要なため、お支払いの証明書類にする場合は確認しておきましょう。
経費が事業に関連することを説明できる準備をしておく
費用を経費にする際は、事業に関連する支出であることを日頃から十分に確認しておくことが必要です。「売上と比較して大きすぎる支出ではないか」「私的な支出と疑われる部分はないか」などを確認し、税務調査の際にも説明できる準備をしておきましょう。
また、事業の支出を明確にし、管理方法を整備しておくことも重要です。支出の管理のための基本的なポイントとしては、例えば以下が挙げられます。
● 事業用の専用口座・専用クレジットカードを用意する
● 領収書を年度ごとなどで整理して保管する
● 帳簿に取引日・相手先・金額などをしっかり記載する
帳簿付けの方法や領収書の管理などをあらためて見直しておきましょう。
個人事業主の経費計上で節税効果を高める方法
個人事業主の経費計上で節税効果を高める方法は2つあります。
・青色申告をする
・税理士に相談する
それぞれ詳しく解説します。
青色申告をする
節税効果を高めるのであれば、確定申告の方法を白色申告ではなく青色申告に切り替えることで、青色申告特別控除が受けられます。
青色申告特別控除では、55万円または65万円の控除を適用する際に複式簿記が必要になるなど、税務のための手間は増えますが、いくつかの税制上の優遇措置が受けられます。
まず、青色申告特別控除として所得金額から最大65万円の控除が受けられます。
また、赤字を最大3年間にわたり繰り越しできる繰越控除や、30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる少額減価償却資産の特例などの優遇措置も適用が可能です。
開業して青色申告する場合、開業後1ヵ月以内に開業届を提出し、開業後2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出することが必要です。それぞれ期限内に書類提出を進めていきましょう。
税理士に相談する
事業を進めるなかで、一般的でないケースにおいて経費にできるか判断が難しい場合があります。また、ご自身では考えつかない視点で節税できる方法が存在する場合もあります。
税理士に相談することで、一般的でないケースでも正しい税務判断を知ることが可能です。税理士への相談により、節税に関するアドバイスをもらえます。
相談には費用がかかりますが、税理士に支払う報酬は経費計上が可能です。一度相談することで、今後の節税に役立つ情報が得られる可能性もあり、長期的に節税効果を高めることが期待できます。
個人事業主の経費はビジネスカードを利用すると便利

個人事業主が経費を管理する場合、領収書の管理などは非常に煩雑です。
領収書の管理の手間を削減したいときは、業務用の経費を法人カードでお支払いをまとめると、経費が一元管理でき、格段に管理しやすくなります。
法人カードで経費を支払えば、何にいくら、どこで使ったのかも利用明細でわかるため、レシートを取っておいたり、領収書を保管しておいたりする手間も省けます。
法人カードの利用明細書は保存しておき、内容照合のために活用しましょう(※)。
なお、ポイントの貯まる法人カードなら、経費を支払うことでポイントが貯まるので、コスト節減にもつながるメリットもあります。
例えば、クレディセゾンのビジネスカードは、ポイントに有効期限がない「永久不滅ポイント」が貯まります。ご自身のペースでポイントを貯めたり、利用したりすることが可能です。
貯めたポイントは2万点以上の人気アイテムが出品中のセゾンカードの総合通販サイト STOREE SAISON(ストーリーセゾン)で使えます。
(※)会計士、税理士によって明細書が領収書の代替になると判断される場合があります。ご担当の会計士、税理士に確認してみましょう。
個人事業主におすすめのビジネスカード
中小企業や個人事業主の方を対象に発行されるビジネスカードは、一般の個人カードと異なり、ビジネスに特化した特典・サービスが利用できます。ここからは、個人事業主の方におすすめのビジネスカードを2種類紹介します。
● セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
● セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
| 年会費 | 無料 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 海外利用で2倍(※1)(※2) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay™、QUICPay™(クイックペイ) |
| 追加カード | 年会費無料で9枚まで発行可能 |
| 主な特典 | ・「かんたんクラウド(MJS)」月額利用料 2ヵ月無料ご優待 ・4倍ポイントサービス ・セゾンビジネスサポートローン ・エクスプレス予約サービス(プラスEX会員) ・エックスサーバーご優待 |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、年会費無料で利用できるビジネスカードです。
申込時は決算書や登記簿謄本の提出が不要なため、起業して間もない会社や個人事業主の方でも気軽にお申し込みできます。
また、一時的な増額申請に対応しているため、高額になりやすい税金も無理なく支払えます。支払額に対してはポイントが還元され、節約や経費削減につながります。
このほか、会計・給与計算のクラウドサービス「かんたんクラウド(MJS)」の月額利用料2ヵ月無料という特典が付帯しているのも魅力です。本サービスには自動仕訳作成機能が搭載されており、経理業務の効率化を行えます。
さらに、特定のビジネス関連のサービスでカードを利用すると、通常のポイント還元率0.5%の4倍である2%のポイント還元が受けられます(※1)(※2)。以下は、ポイント4倍サービスの対象になるサービスの一例です。
● アマゾンウェブサービス(AWS)
● エックスサーバー
● お名前.com
● かんたんクラウド(MJS)
● クラウドワークス
● サイボウズ
● マネーフォワード クラウド
● モノタロウ(事業者向けサイトのみ対象)
● Yahoo!ビジネスサービス
日常生活で役に立つセゾンカード会員限定の特典も充実しており、例えば、毎週木曜日に全国のTOHOシネマズでお好きな映画を1,200円(税込)で鑑賞いただける「セゾンの木曜日」があります。
セゾンカードのスマートフォンアプリ「セゾンPortal」からクーポンを取得いただき、WEB(インターネットチケット販売“vit®”)または劇場でのチケット購入時にクーポンをご利用いただくことで特別料金で映画鑑賞が可能です。
(※1)ほかカードにてSAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)へご入会いただいている方は本サービスの対象外となります。
(※2)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
>>詳細はこちら
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
| 年会費 | 初年度無料、2年目以降は33,000円(税込) |
|---|---|
| ポイント還元率 | 海外利用で2倍(※1)(※2) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay™、QUICPay |
| 追加カード | 年会費3,300円/枚(税込)で9枚まで発行可能 |
| 主な特典 | ・コンシェルジュ・サービス ・「デジタル会員証(プライオリティ・パス アプリ)」に年会費無料でお申し込み可能(※3)(※4)(※5) ・セゾン弁護士紹介サービス ・法人向け顧問弁護士サービス「リーガルプロテクト」ご優待 ・各種のビジネスサポート特典 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、手厚いビジネス向けの特典が付帯したプラチナビジネスカードです。
プラチナカードならではの特典として、専任スタッフが24時間365日対応(※6)する「コンシェルジュ・サービス」が利用でき、ビジネスでもプライベートでもサポートが受けられます。
世界に広がる1,700ヵ所以上の空港ラウンジをご利用いただける「デジタル会員証(プライオリティ・パス アプリ)」に年会費無料でお申し込み(※3)(※4)(※5)ができ、フライト前の待ち時間もゆったり過ごせます。
ビジネス向けの特典としては「セゾン弁護士紹介サービス」が利用でき、弁護士に相談したいときには第一東京弁護士会を通じて弁護士の紹介を受けることが可能です(※7)。
ほかにも、ビジネスに役立つさまざまなサービスを優待価格で利用できる「ビジネス・アドバンテージ」も付帯しています。
さらに、日常生活で役に立つ特典も充実しており、「セゾンの木曜日」の利用で映画がお得に楽しめたり、「セゾンフクリコ」が入会費・年会費無料で利用できたりします。
「セゾンフクリコ」とは、全国25,000以上の施設を最大66%OFFで使える優待割引サービスです。特別優待として映画鑑賞券が1,300円(税込)からご購入可能です(お一人様20枚/年まで)。
ほかにも、レジャーやグルメ、トラベルなどさまざまな優待割引を、専用サイトからいつでもご利用いただけます。
(※1)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
(※2)小数点以下は繰り上げになります。
(※3)通常年会費 469米ドル(プレステージプラン)
(※4)別途「デジタル会員証(プライオリティ・パス アプリ)」へのお申し込みが必要となります。
(※5)プライオリティ・パスのプラン内容はカードによって異なります。
(※6)「カードのご利用に関するお問い合わせ」のみ、10:00〜17:00の対応とさせていただきます。
(※7)別途、弁護士相談料が発生します。
>>詳細はこちら
よくある質問
以下では、個人事業主の経費に関するよくある質問を紹介します。
Q1 個人事業主の経費とは?
経費とは、個人事業主が事業を進めるうえで必要となる費用を指します。
Q2 個人事業主の出費が「経費」として認められるポイントは?
「経費」と「プライベートな出費」はきちんと区別することが大切です。
プライベートな生活費と必要な経費が混在している事務所と住居が一体化した家賃などの費用は、家事按分により経費部分を算出します。
まとめ
本記事では、個人事業主の経費について解説しました。
個人事業主が支出を経費に計上できるかどうかは、事業の支出であるかどうかが主な判断基準です。事業に関係のない私的な支出や税金のお支払いなどは経費に計上できません。
経費の計上が不適切だと、税務調査で指摘を受ける可能性もあります。事業の支出を明確にし、適切な経費計上を心掛けましょう。
経費と個人の出費をしっかり区別したい場合は、法人カードを発行するのがおすすめです。法人 カードはビジネスに役立つ特典が付帯していたり、ポイントやマイルを貯めることもでき、経費削減にもつながります。
ビジネスカードを検討しているのであれば「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」と「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」がおすすめです。
それぞれの特長は異なるため、ご自身に合ったカードをぜひご検討ください。
(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
(※)Apple、Appleのロゴ、Apple Payは、Apple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。TM and © 2025 Apple Inc. All rights reserved.
(※)Google Pay 、Google Pay ロゴ、Google Play 、Google ロゴ、Android はGoogle LLC の商標です。
(※)Google Pay は、おサイフケータイ(R) アプリ(6.1.5以上)対応かつAndroid5.0以上のデバイスで利用できます。
(※)「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です
(※)「QUICPay」「QUICPay+」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。