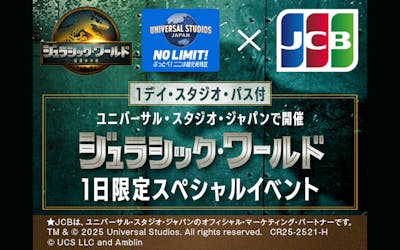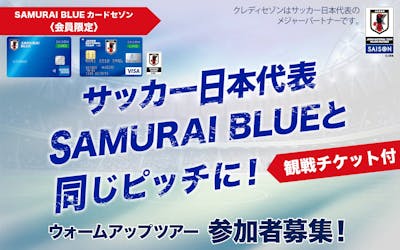少子高齢化の問題点!高齢化社会の現状・対策と私たちができること
掲載日:

ニュースでも度々話題にあがる「少子高齢化」ですが、「どれだけ深刻な状態なんだろう?」と疑問を抱いている方もいるでしょう。
2025年には、65歳以上の後期高齢者3,657万人に達すると見込まれており、また、75歳以上の後期高齢者2,000万人を超えて「超高齢化社会」になると言われています。一方で出生数は年々下がり、2023年の合計特殊出生率は1.20と統計を取り始めてから最も低い数値となりました。そして、企業の人手不足や医療費の増加などを背景に国民の負担はどんどん増えており、1970年には約24%だった国民負担率(※)は2023年には約46%にまで膨れ上がっています。
現在、国や企業でさまざまな取り組みがされていますが、私たちにもできることはないのでしょうか。
この記事では、少子高齢化の問題点や自分たちで対策できる取り組みについて解説します。
※個人や企業などの国民全体における所得に占める税金および社会保険料の負担の割合
日本が抱える社会問題「少子高齢化」とは


少子高齢化を簡単に言うと、子どもが少なくなる「少子化」と高齢者が増える「高齢化」が同時に起きている状態を指します。
少子化の原因には、子どもの人口が少なくなる、すなわち出生率の減少が挙げられます。
日本の出生数は、第1次ベビーブーム期(*1)には年間で約270万人、第2次ベビーブーム期(*2)の1973年には約210万人でしたが、その後減少し続け、2021年には81万1,622人となりました。
そして、合計特殊出生率(*3)も、第1次ベビーブーム期には4.3を超えていましたが、1950年以降急激に低下し、1975年以降は2.0を下回り、2005年には過去最低の1.26を記録しました。その後多少の上下があるものの、2023年には1.20となっています。
合計特殊出生率とは、ひとりの女性が一生の間に産む子どもの平均数を示す指標です。この指標は、人口の世代間再生産の程度を評価するために用いられます。
出生率が減少しているのは、未婚率の上昇や結婚する年齢があがる晩婚化などが原因として考えられます。
逆に、高齢者の割合は増えてきています。第一次ベビーブームに生まれた団塊の世代が75歳以上の高齢者になることも要因のひとつです。2025年には、65歳以上の高齢者全体の人口は3,657万人に達すると見込まれており、これは人口の30%を占める割合です。
さらに、この少子高齢化に伴って出生数よりも死亡数が上回っているため、人口も減少してきています。厚生労働省の調査によると、2023年の出生数は約76万人、死亡数は約159万人で、約83万人の人口が減少していることがわかりました。
※1:第一次ベビーブームは1947~1949年
※2:第二次ベビーブームは1971~1974年
※3:15~49歳までの女性における年齢別出生率を合計したもの。仮にひとりの女性がその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。
少子高齢化の問題点


日本では、少子高齢化がどんどん進んでいますが、少子高齢化になるとどのような問題点が考えられるでしょうか。具体的には次のような問題点が浮上します。
✓ 労働人口の減少
✓ 医療費の増加や介護領域の拡大
✓ 地域間の医療格差
少子高齢化が進むと、少ない労働力で高齢者を支えていかなくてはいけないため、各地域で人手不足が問題となるでしょう。特に、都市部と人口の少ない過疎地域では医療格差が生まれる可能性があります。
労働人口の減少
少子高齢化による労働人口の減少は、少子高齢化の問題点のひとつだと言えるでしょう。
人は誰しも年齢を重ねると体が思うように動かなくなったり病気になったりするリスクが高まり、労働が難しくなってきます。こうして労働人口が減ってくると、日本の経済を支えることも困難になっていくでしょう。また、高齢者を支えるための年金は今の労働者が支払っています。労働人口が減ってくると年金の支給額も減ってしまう可能性があります。
特に、国民の生活を直接支えていくエッセンシャルワーカーの人口が減ってしまうことは非常に大きな問題となるでしょう。エッセンシャルワーカーとは、医療や福祉、行政、物流、小売業などの職種で働く人々です。エッセンシャルワーカーが減ることで高齢者のケアが行き届かなくなるなど、国民全員の生活が不便なものになっていく可能性があるでしょう。
医療費の増加や介護領域の拡大
少子高齢化によって医療費が増加したり介護領域が拡大したりすることも問題です。
年齢を重ねて病気になったり日常生活の動作がスムーズにいかなくなったりすると、医療や介護の手助けが必要となります。高齢者の人口が増えることで、自然と医療・介護の費用が増加していくでしょう。
現在、75歳以上である後期高齢者の窓口負担をのぞいた医療費の約4割を現役世代が負担しています。そして、少子高齢化に伴って現役世代の負担がより大きくなっていることから、後期高齢者の保険料も2024年度から徐々に引き上がっていく方針です。このように、少子高齢化によって医療・介護費は膨れ上がっており、高齢者の負担も増えている状況です。
また、医療や介護を支える人手も今まで以上に必要となっていきます。少子化による労働人口の減少によって、医療者や介護者の確保はどんどん難しくなっていくでしょう。
地域間の医療格差
地域間の医療格差も、少子高齢化による問題点のひとつだと言えるでしょう。
少子高齢化が進むなか、現役世代は都市部へ流入していて、高齢者ばかりで現役世代がほとんどいない地域もあります。結果、医療従事者の人員が不足している地域もあります。
そのため、都市部と比べて、高齢者ばかりの地域では医療の発達が進んでいない現状です。最近では、医療機関がほとんどないへき地(※)へ医師が巡回診療やオンライン診療を実施することによって、医療格差をなるべく減らしていく取り組みがされています。ですが、病気の精密な検査や最先端の治療法を受けるためには、都市部の医療機関へ足を運ばなくてはならず、適切な治療が遅れてしまう原因にもなるでしょう。
※へき地:山間地や離島などで医療の確保が困難な地域のこと
高齢化社会に対する国の対策


日本では、急速に進む少子高齢化の対策として「高齢社会対策基本法」が1995年に制定されました。高齢社会対策基本法をもとに、国民一人ひとりが生涯やりがいを持ちながら安心して暮らせる社会を目指しています。
高齢社会対策基本では、高齢者に対して次のような施策を規定しました。
✓ 公的年金と雇用で連携を取り、高齢者の所得水準を確保する
✓ 高齢者が意欲と能力に応じた就業ができるような多様な機会を支援する
✓ 高齢者が適切な医療と介護サービスを受けられるよう体制を整備する
✓ 高齢者のボランティア活動参加に向けた基盤を整える
✓ 高齢者のための住宅を確保し、円滑な生活ができるよう公的施設の整備も整える
また、これらの施策をすすめていくにあたって高齢社会対策会議を定期的に開催しています。2024年2月には第36回の高齢社会対策会議が開催され、新たな高齢化社会の対策について話し合われました。
高齢化社会に対する企業の取り組み


高齢化社会は、国だけでなく企業によっても支えられています。
例えば、近年では高齢者の雇用が増加傾向にあり、2022年の高齢者の就業率は65〜69歳は約50%、70〜74歳では約34%、75歳以上でも約11%で、いずれも前年より上回りました。
また、少子高齢化による労働力の減少については、次のような取り組みが注目されています。
✓ ライドシェア・・・一般のドライバーが自家用車で乗客を運ぶ取り組み。現在解禁に向けてさまざまな議論がされています。
✓ 宅配サービスによる置き配・・・玄関や指定の場所に配達物を置くことで、再配達をなくすサービス。労働力の削減につながる。
✓ 宅配サービスによる見守りサービス・・・独居の高齢者宅に異常を検知できる機会を設置し、異常を察知した際に家族の代わりに宅配スタッフが高齢者宅を訪問するサービス。
✓ 外国人労働者の受け入れ・・・労働人口の確保のため、外国人労働者の受け入れを積極的に行う。
高齢化社会において私たちが自分でできることは?


ここまで少子高齢化社会における問題点や国・企業の取り組みについて解説しました。では、私たちが自分でできることはないのでしょうか。
実は、自分でできる対策もいくつかあります。次のような自分に対することや高齢者に対することに今から取り組めますよ。
✓ 未病と向き合う
✓ 定期検診を受ける
✓ 高齢者のQOL向上
まずは自分の体と向き合い、健康的に過ごせる期間(健康寿命)を延ばすことが大切です。そして、現在の高齢者の方たちのQOLを向上させていくことで、少子高齢化による問題点を対策していけるでしょう。
未病と向き合う(もしくは、「未病」を知る)

まずは、未病と向き合うことが重要です。未病とは、簡単に言うと「健康と病気の間にある状態」です。未病の状態になると「病気というほどではないけれど、なんだか心身の調子が悪い」ということが増えて日常生活の質が悪くなってしまいます。
未病を放っておくと、最終的には生活習慣病やその他さまざまな疾患へとつながってしまうでしょう。逆を言うと、未病と向き合うことによって生活習慣病などを予防できるかもしれないのです。
未病と向き合うには、健康的な生活習慣を心がけることが最も大切です。バランスの良い食事・規則正しい生活リズム・適度な運動は、体や心に健康をもたらしてくれるでしょう。
年齢や性別によって、未病の原因が異なることもあります。例えば、40代女性が原因もないのにのぼせやすくなったりイライラしやすくなったりするのは、更年期の症状であることも多いです。「なんだか調子が悪いな」と感じたら、自分で調べてみるか、1人で抱え込まずに専門家に相談してみると良いでしょう。
定期検診を受ける
定期検診を受けることで、生活習慣病をはじめとしたさまざまな疾患を早期発見でき、高齢化社会における負担を減らすことができるでしょう。疾患による自覚症状は、病状が進んでからやっと気がつくということが多いです。そのため、定期検診で疾患の早期発見が大切です。
市町村の健康診断では生活習慣病になっていないか確認できるほか、年齢に応じて胃がんや乳がんなどのがん検診も受けられます。より詳細な検査をしたい場合には、各医療機関でおこなっている人間ドックの利用がおすすめです。年齢を重ねると気になってくる認知症の検査もできる人間ドックもあるため、自分で気になる疾患を検査できる医療機関を選ぶと良いでしょう。
健康診断や人間ドックは、最低でも1年に1回、定期的に受けることがおすすめです。定期的な検診で疾患の早期発見や治療中の疾患の進行具合を知ることにつながります。
高齢者のQOL向上
高齢者のQOLを向上させることは、介護の負担を減らすことにつながり高齢化社会の対策になります。
QOLとはQuality of lifeの略で「生活の質」という意味です。「快適に生活できる」以外にも「生きがいを持っている」「いきいきと生活している」などもQOLの向上にあてはまると考えられます。高齢者が生きがいを持てず、QOLが低下してしまった状態だと、精神的な健康の悪化(うつ病や不安障害)が懸念されるだけでなく、活動しなくなることで身体的な健康の悪化(免疫力が下がる、高血圧や糖尿病などの持病)も心配されます。
また、社会的な孤立(孤独感、コミュニケーションの減少)や、認知機能の低下なども心配されます。
周囲の人たちが取り組むことができる高齢者のQOL向上には「規則正しい生活へ誘導する」「高齢者のやる気を出す」「生活の中に楽しみを増やす」などが挙げられます。例えば、高齢者のご家族と同居している場合では「朝は決まった時間に起床するよう促す」「朝ごはんだけでも同じ時間に一緒に食べる」「家事をしてくれたら感謝する」「週に1回は一緒に出かける」などができるでしょう。
高齢者のQOLを向上させて自発的な行動を促すことが、介護が必要な状態にならないような予防対策となるのです。
その他
その他にも、高齢化社会において私たちが自分でできることはたくさんあります。
✓ 少子化対策ができる政治となっていくように選挙に参加する
✓ 労働力の減少に対応できるようなシステムを積極的に取り入れる
✓ 自分に合った働き方を見つけて、定年後の所得を確保しつつ、就労期間を延ばして経済を支える
上記のように、自分1人でもできる行動があります。小さな行動でもみんなが行えば、国を支える大きな力となるでしょう。
ヘルスケアについてクレディセゾンだからこそできること


クレディセゾンでは、少子高齢化社会に対してできることとしてヘルスケア関連の情報を発信していきたいと考えています。健康や相続、身寄りがない方へのサポートなど、少子高齢化が進む人生100年時代の現代に合った最新情報をお伝えします。
また、健康的な生活をサポートするための食品やアイテムを紹介しています。これらを取り入れることで、日常生活の質を高める一助となるかもしれません。
クレディセゾンが取り組むヘルスケアに興味がある方はこちらをぜひご覧ください。
まとめ

少子高齢化は何年も前から問題視されていますが、私たちで対策できることもたくさんあります。子どもや高齢者を支えることはもちろんですが、まずは自分たちが豊かに暮らせる工夫も大切です。
未病を治したり定期検診を受けたりして、健康に生きられる「健康寿命」を伸ばしていきましょう。規則正しくメリハリを持った生活を送り、楽しく健康な生活を手に入れられると良いのではないでしょうか。
他の記事でもヘルスケア情報をチェックできます!日々の暮らしに役立てていきましょう!






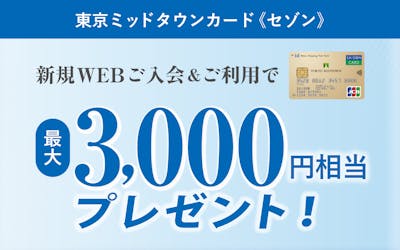
.jpg?auto=compress%2Cformat&w=400)